EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
四半期 第4回:四半期財務諸表の会計処理(3)(法人税等、税効果)
公認会計士 山岸 聡
法人税等および繰延税金資産・負債
- 原則として、年度決算と同様に算定。ただし、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定することを容認 (適用指針15)
- 繰延税金資産の回収可能性の判断における前年度に使用した業績予測等の利用 (適用指針16、17)
- 年間見積実効税率の利用 (基準14、適用指針18,19)
- 重要性の乏しい連結会社における簡便的な会計処理 (適用指針20)
- 未実現利益の消去に係る税効果は年間見積課税所得額を限度 (適用指針22、97)
- 連結納税制度における年間見積実効税率の利用 (適用指針23)
1. 年度と同様の方法による場合の簡便的な取り扱い
法人税等の計算は、原則として年度と同様の方法によることとされています。ただし、開示の迅速性の要請により、簡便的な会計処理として加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定することが認められています。
(原則的な会計処理)
年度決算と同様の方法により計算します。つまり、当四半期会計期間における利益を基礎として所得計算を行い、当四半期会計期間が負担する税額を計上する方法です。
ただし、税率については、累進税率が適用されるような場合には、年度の法人税等の計算に適用される税率を予測し、当該税率によって法人税等を計算することになります。
(簡便的な会計処理)
所得計算における加減算項目や、税額計算における税額控除項目を、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、重要なものに限定することができます。
また、税金費用について四半期特有の処理を採用した場合も同様に、見積実効税率の算定において財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、一時差異に該当しない差異や税額控除等の算定を、重要な項目に限定して行うことができます。
2. 繰延税金資産の回収可能性の判断における簡便的な取り扱い
繰延税金資産の回収可能性は、原則として年度決算と同様に検討します。ただし、前年度末から業績や経営環境に大幅な変更がなく、かつ、一時差異の発生状況に大幅な変更がない場合には、回収可能性の判断を、簡便的に行うこともできます。
(原則的な処理)
繰延税金資産および繰延税金負債を、年度決算と同様に、四半期末における一時差異等について、回収可能性を検討した上で計上します。
(簡便的な処理)
経営環境の著しい変化が生じておらず、かつ一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がない場合には、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができます。「経営環境の著しい変化」には、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転または悪化などがあります。
なお、経営環境に著しい変化が生じた場合、または一時差異等の発生状況について前期末から大幅な変動が認められる場合でも、繰延税金資産の回収可能性の検討に当たっては、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著しい変化または大幅な変動による影響を加味したものを利用することができます。
また、税金費用について四半期特有の処理を採用している場合でも、前年度末に計上した繰延税金資産の回収可能性を四半期末に見直す必要がありますが、同様の方法によって簡便的に検討を行うことができます。
3. 年間見積実効税率を適用する場合と適用にあたっての留意点
四半期決算における税金費用の会計処理は、年度決算と同様の方法により行うことを原則としますが、四半期特有の方法として四半期会計期間を含む年度の税効果適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて計算することができます。ここでいう見積実効税率とは、当四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の税金費用の負担率を合理的に見積もったものをいいます。また、第2四半期および第3四半期において四半期会計期間の損益を開示する場合の各四半期会計期間の税金費用は、累計期間の税金費用から直前の四半期末までの累計期間の税金費用を控除して計算します。
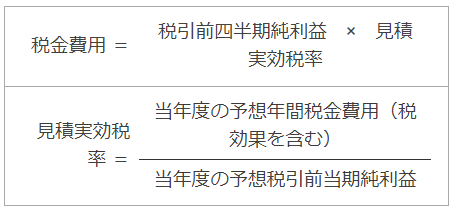
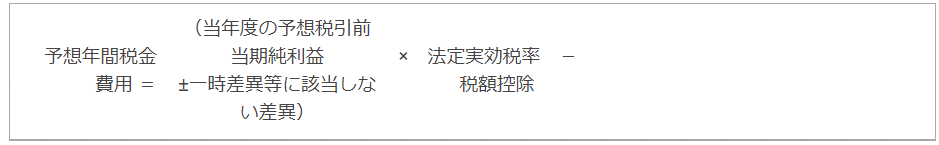
【図表1】の例では、四半期において、当年度の予想税引前純利益4,000(A)および一時差異等に該当しない差異800を見積もり、課税所得見込額4,800に、法定実行税率40%を乗じた額から税額控除を引いて、予想年間税金費用1,800を算出します。さらに、予想年間税金費用1,800を(A)で除して、見積実効税率45%を算出し、四半期の税金費用の金額は、 360(=税引前四半期純利益800×45%) と計算されます。
【図表1】
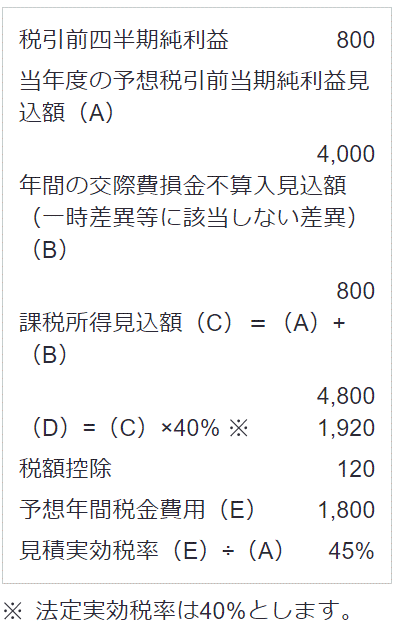
(仕訳) (借)法人税、住民税および事業税 360 (貸)未払法人税等 360
この方法による場合には、前年度末の繰延税金資産・負債がそのまま計上されることから、繰延税金資産の回収可能性を判断することが必要です。なお、この場合の回収可能性の判断においても、2.の簡便的な方法によることが認められます。
(適用にあたっての留意点)
(1) 見積もりに必要な項目
見積実効税率の算定のためには、年間の税引前当期純利益のほか、交際費などの一時差異に該当しない差異、および税額控除の年間発生額を見積もる必要があります。なお、四半期決算では簡便的な会計処理が認められ、一時差異に該当しない差異および税額控除の見積もりを、重要な項目に限定することができます。
一時差異に該当する差異は、税効果の対象となりますので、税効果会計適用後の見積実効税率の算定に当たっては、税引前当期純利益に加減する必要はありません。ただし、当四半期を含む年度において発生する重要な将来減算一時差異で、解消のスケジューリングが見込めない(繰延税金資産を計上しない)ものは、一時差異に該当しない差異と同様に、税引前当期純利益に加算する必要があると考えられます。
(2) 繰延税金資産および繰延税金負債
前期末に計上された繰延税金資産および繰延税金負債については、繰延税金資産の回収可能性を四半期末で見直した上で貸借対照表に計上します。見直した結果、回収可能と認められなくなった額については、繰延税金資産の計上を取り崩すことになります。なお、四半期決算では簡便的な会計処理が認められており、前年度末の検討を基礎として繰延税金資産の回収可能性の判断を行うことができます。
(3) 第2四半期以降における見積実効税率の見直し
見積実効税率は第2四半期および第3四半期決算において見直しを行い、見直された見積実効税率に基づいて税金費用を計上する必要があります。その上で各四半期の税金費用計上額は、原則として、次のように計算します。

(4) 損益計算書の表示
四半期特有の処理では、税金費用を、法人税等と税効果とを区分せずに一体として計算します。そのため表示上も「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」とに区分せず、一括して記載することになります。このとき、一括して記載した旨を注記することが求められます(四半期連結財務諸表規則第77条2項)。
(5) 評価差額にかかる税効果
その他有価証券などの評価差額にかかる税効果は、税金費用の計算には関係なく、年度決算と同様に、四半期ごとに時価評価に基づき、繰延税金資産または繰延税金負債の計上額を洗い替える必要があります。
(6) 見積実効税率が使用できない場合
以下のような場合には、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると、著しく合理性を欠く結果となるため、見積実効税率でなく、法定実効税率を用いて税金費用を計算するものとされています。
①予想年間税引前当期純利益がゼロまたは損失となる場合
②予想年間税金費用がゼロまたはマイナスとなる場合
③四半期ごとの利益と損失が相殺されるため、一時差異等に該当しない差異に係る税金費用の影響が、(予想)年間税引前当期純利益に対して著しく重要となる場合
(設例)
|
第1四半期実績 |
第1四半期実績 |
|
|---|---|---|
|
①税引前当期純利益 |
1,000 |
600 |
|
②交際費(一時差異等に該当しない差異) |
150 |
600 |
|
③=①+② |
1,150 |
1,200 |
|
④税金費用(法定実効税率40%とします) |
480 |
|
|
⑤見積実効税率(④÷①) |
80% |
上記の例では第1四半期の利益と第2四半期以降の損失とが相殺されることで、一時差異等に該当しない差異に係る税金費用の影響が著しく重要になり、見積実効税率は80%となっています。この場合には当該見積実効税率による税金費用の計算は適当ではなく、法定実効税率を用いて税金費用を計算します。
(法人税、住民税及び事業税) 460 / (未払法人税等) 460
(1,000 + 150)×法定実効税率40% = 460
4. 重要性の乏しい連結会社における簡便的な会計処理と回収可能性判断
(1)簡便的な会計処理による税金費用の会計処理は、原則的な処理または四半期特有の処理のいずれかを採用することができます。加えて、重要性の乏しい連結会社については、以下の要件を満たした場合、簡便的な会計処理を採用することも認められています。親子会社で統一することも要求されていないため、連結会社ごとにどの方法を採用するか検討することになります。
なお、重要性が乏しい連結会社には、連結子会社で重要性が乏しい会社のほか、例えば純粋持株会社であって重要性の乏しい親会社も該当する場合があります。
(簡便的な会計処理)
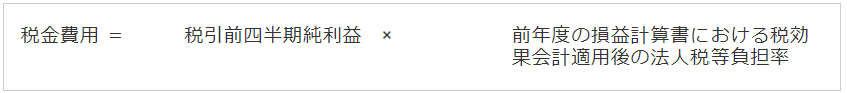
(適用要件)
- 重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転または悪化およびその他の経営環境の著しい変化が生じていないこと
- 一時差異等の発生状況について前期末から大幅な変動がないこと
(2)簡便的な会計処理を採用した場合の回収可能性判断
重要性の乏しい連結会社について簡便的な会計処理を採用した場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断結果が継続していると考えられることから、前年度末の繰延税金資産・負債をそのまま同額で貸借対照表に計上することが認められます。(適用指針96)
5. 未実現利益の消去に係る税効果
四半期会計基準では、連結上で消去した未実現利益が、売却元の年度の見積課税所得を上回る場合に、将来減算一時差異の金額は 年度の見積課税所得を限度 とするとされています。これは、同一年度内で期首から累計期間に係る課税所得が四半期を経るごとに変動することに伴い、繰延税金資産に計上できる一時差異の限度額が変動し、税金費用の計上をゆがめてしまうことを回避するためです。
【図表2】の例では、見積課税所得80が未実現利益200より小さくなっていますが、四半期会計基準の考え方によると、年度の課税所得320が未実現利益の金額200より大きいことから、繰延税金資産80(=200×40%)が計上されます。
【図表2】
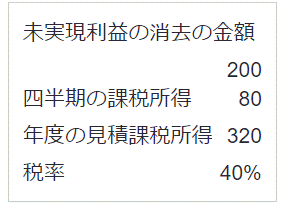
| (仕訳) | (借)売上原価 | 200 | (貸)棚卸資産 | 200 |
| (借)繰延税金資産 | 80 | (貸)法人税等調整額 | 80 |
6. 連結納税制度を採用している場合
連結納税制度を採用している場合においても、予想年間税金費用と予想年間税引前当期純利益を合理的に見積もることができる場合には、年度の税効果適用後の実効税率を見積もって税金費用を計算することが認められています。
四半期
- 第1回:四半期報告制度の概要および四半期財務情報の概要 (2011.04.22)
- 第2回:四半期財務諸表の会計処理(1)(債権、有価証券、棚卸資産) (2011.04.22)
- 第3回:四半期財務諸表の会計処理(2)(原価計算、固定資産等) (2011.04.22)
- 第4回:四半期財務諸表の会計処理(3)(法人税等、税効果) (2011.04.22)
- 第5回:四半期連結財務諸表の会計処理および四半期財務諸表の表示 (2011.04.22)
- 第6回:四半期財務諸表の注記(1)(会計方針の変更等) (2011.04.22)
- 第7回:四半期財務諸表の注記(2)(継続企業の前提等)との関係 (2011.04.22)
- 第8回:非財務情報の概要 (2011.04.22)
- 第9回:四半期レビューの概要(1) (2011.04.22)
- 第10回:四半期レビューの概要(2) (2011.04.22)




