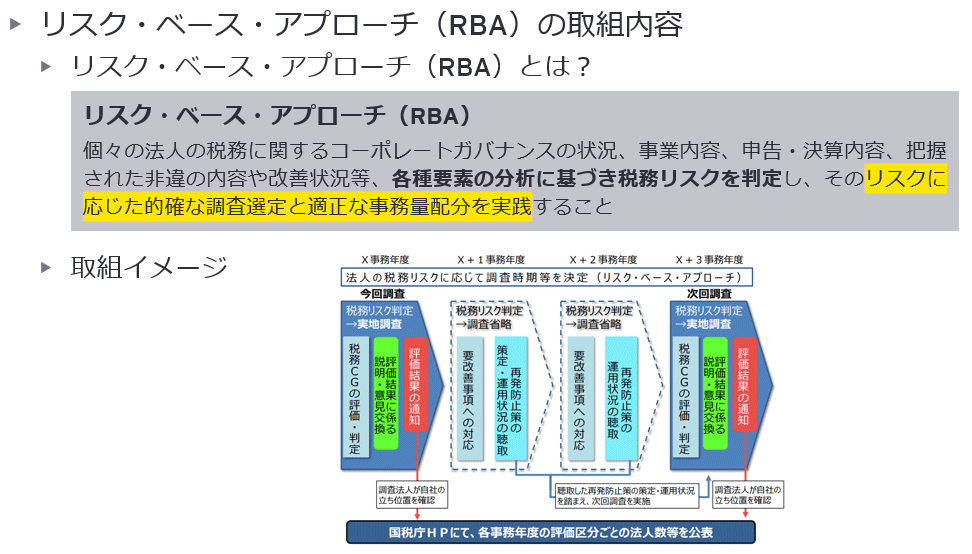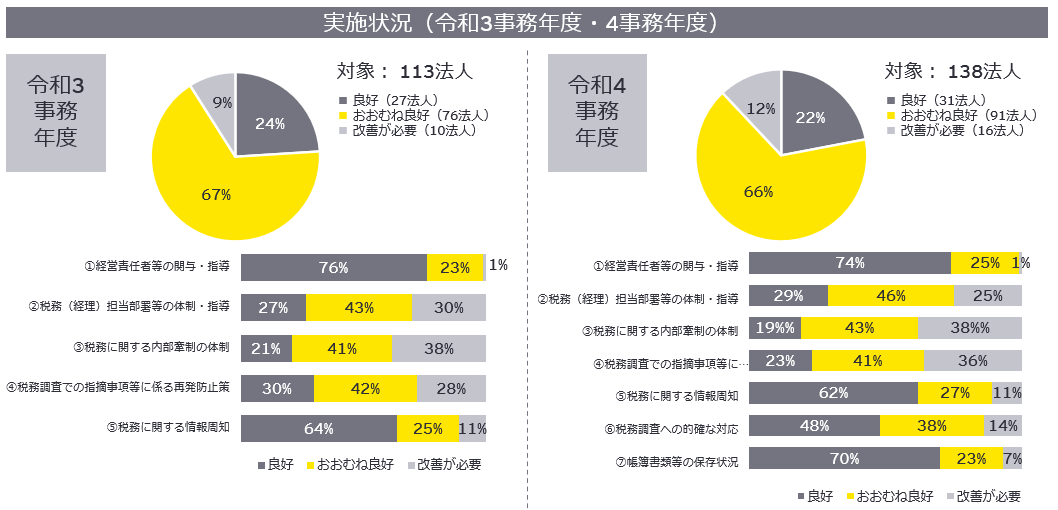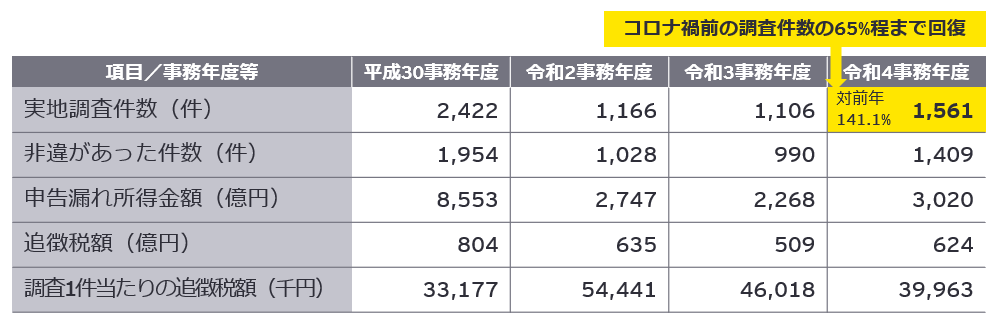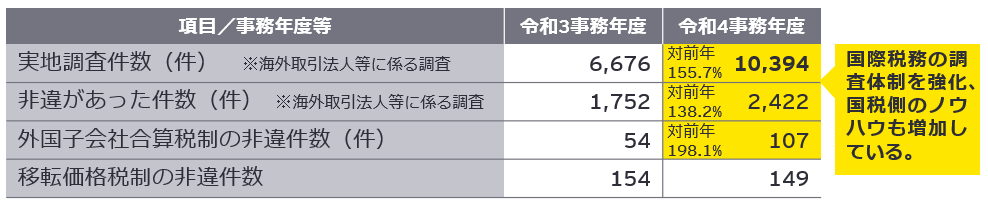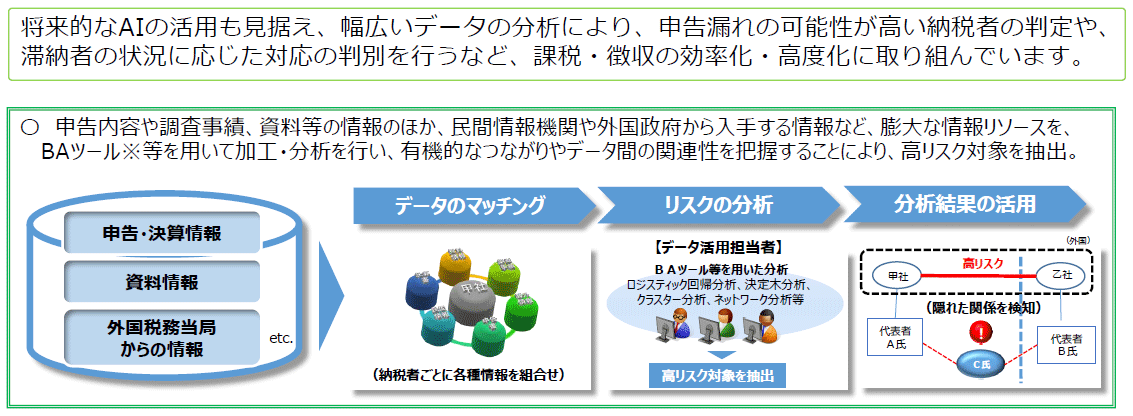EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYの関連サービス
-
EY審理戦略室は、税務リスクへの対応支援を強化する目的から国税庁に勤務経験のあるメンバーのほか、弁護士、各特殊分野の税務専門家など、経験豊富な総勢約50人が1つのチームとなり、取引の税務上の審理にとどまらず、法務的な観点も踏まえた上での多角的な分析によるサポートを行います。
続きを読む
(2) J-CAP制度(Compliance Assurance Program of Japan)
J-CAP制度とは、2023年10月から実施された取組で、「新規性の高い形態の取引等に関する個別確認プログラム」のことで、税務CGの充実に向けた取組の一環として、国税当局が、新規性の高い形態の取引につき、リーディングカンパニー、上場企業等の大企業(東京国税局調査部特官所掌法人が対象)と協力・対話しながら、対象とする取引の税務上の取扱いについて、早期に回答(受付から45日以内)を行うことにより、税務リスクを低減させるというものです。
後述で説明する事前照会との違いについては、回答が早い点(受付から45日以内)、国税当局の審理担当部署も積極的に協力・対話に参加される点が挙げられ、EYで関与した案件の経験を踏まえると事前照会よりも国税当局が前向きに協力・対話される印象があります。
J-CAP制度は、納税者にとっては、非常にメリットが大きい制度であると率直に実感しています。今後は、東京国税局調査部特官所掌法人以外も活用できるよう範囲拡大が期待されます。