EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
建設業 第4回:建設業における収益認識(3)~独立販売価格に基づく配分、履行義務の充足パターン、事後的に信頼性がある見積りができなくなる場合~
EY新日本有限責任監査法人 建設セクター
公認会計士 今村 裕宇矢/川井田 直人/竹俣 勝透/橋之口 晋
1. はじめに
収益認識会計基準及び収益認識適用指針が、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されました。これに伴い、工事契約会計基準及び同適用指針が廃止されました。
第2回から第4回の「建設業における収益認識」では、収益認識会計基準及び収益認識適用指針の適用による影響について、3回に分けて解説します。本稿では、収益認識の5ステップのうち、(Step4)取引価格を履行義務に配分する、に関連して、独立販売価格に基づく配分に関する論点、(Step5)履行義務を充足又は充足するにつれて収益を認識する、に関連して、履行義務の充足パターン及び事後的に信頼性がある見積りができなくなる場合に関する論点を解説します。
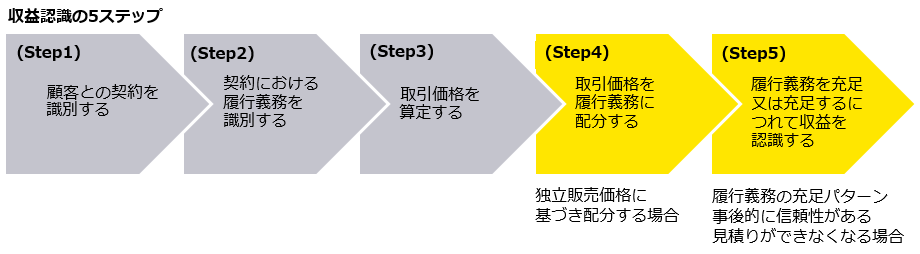
2. 独立販売価格に基づく配分
(1) 概要
(Step2)契約における履行義務を識別する、で解説のとおり、1つの工事契約に対して1つの履行義務を識別する場合もあれば、複数の履行義務を識別する場合もあります。例えば、建物を建設して、建物の竣工・引渡後に追加でアフターサービスを実施するような保証サービスを提供する約束を顧客と交わし、建物の建設と保証サービスを別々の履行義務として識別する場合には、「建物の建設」の収益計上と、竣工・引渡後に提供される「保証サービス」の収益計上の金額及びタイミングは異なります。
そのため、履行義務が複数あれば、履行義務ごとに収益を認識するために各履行義務へ取引価格を割り当てる必要があります。
(2) 収益認識会計基準及び収益認識適用指針の取扱い
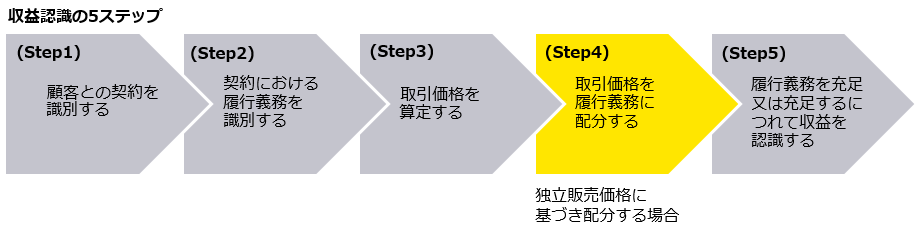
それぞれの履行義務に対する取引価格の配分は、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を描写するように行います。そのため、契約におけるそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財又はサービスについて、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づき配分します(収益認識会計基準第65項、第66項、第68項)。
財又はサービスの独立販売価格を直接観察できない場合には、市場の状況、企業固有の要因、顧客に関する情報等、合理的に入手できるすべての情報を考慮し、観察可能な入力数値を最大限利用して、独立販売価格を見積ることが求められており(収益認識会計基準第69項)、独立販売価格を見積る方法として、下記3つの方法が例示として挙げられています(収益認識適用指針第31項)。
a. 調整した市場評価アプローチ
財又はサービスが販売される市場を評価して、顧客が支払うと見込まれる価格を見積る方法
b. 予想コストに利益相当額を加算するアプローチ
履行義務を充足するために発生するコストを見積り、当該財又はサービスの適切な利益相当額を加算する方法
c. 残余アプローチ
契約における取引価格の総額から契約において約束した他の財又はサービスについて観察可能な独立販売価格の合計額を控除して見積る方法
なお、c. 残余アプローチは、次のいずれかに該当する場合に限り、使用できます。
- 同一の財又はサービスを異なる顧客に同時又はほぼ同時に幅広い価格帯で販売していること(すなわち、典型的な独立販売価格が過去の取引又は他の観察可能な証拠から識別できないため、販売価格が大きく変動する。)
- 当該財又はサービスの価格を企業が未だ設定しておらず、当該財又はサービスを独立して販売したことがないこと(すなわち、販売価格が確定していない。)
上記の3つの方法は例示であり、それ以外にも合理的な見積方法があればその方法を用いることも可能ですが、恣意性を排除するため、類似の状況においては首尾一貫した見積方法を適用する必要があります(収益認識会計基準第69項)。
3. 履行義務の充足パターン
(1) 概要
従来の工事契約会計基準及び同適用指針では、工事進行基準又は工事完成基準により収益を認識していました。収益認識会計基準及び収益認識適用指針では、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものは一定期間にわたって収益を認識し、履行義務が一時点で充足されるものは一時点で収益を認識します。
(2) 収益認識会計基準及び収益認識適用指針の取扱い
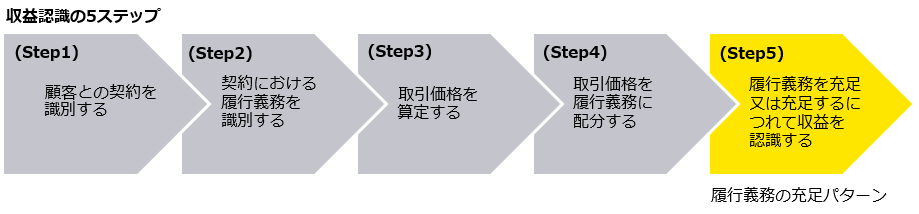
a. 一定の期間にわたり充足される履行義務に該当するかの検討
契約における取引開始日に、識別された履行義務が、一定の期間にわたり充足されるものか一時点で充足されるものかを判定します(収益認識会計基準第36項)。取引開始日に以下の3要件のいずれかを満たす場合には、資産に対する支配を顧客に一定期間にわたって移転することにより、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識します(収益認識会計基準第38項)。いずれの要件も満たさず、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識します(収益認識会計基準第39項)。
(ⅰ) 企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること
(ⅱ) 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配すること
(ⅲ) 次の要件のいずれも満たすこと
(一) 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること
(二) 企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること
(ⅱ) に関連し、資産に対する支配とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんど全てを享受する能力(他の企業が資産の使用を指図して資産から便益を享受することを妨げる能力を含む)をいいます(収益認識会計基準第37項)。例えば、顧客が所有している土地に、顧客の本社ビルを建築する場合は、(ⅱ) に該当するものと考えられます。
(ⅲ) (一)に記載の、別の用途に転用することができない資産が生じることとは、別の用途に容易に使用することが契約上制限されている場合、あるいは別の用途に転用するためには実務上制約されている場合をいいます(収益認識適用指針第10項)。実務上制約されている場合とは、別の用途に使用するために重要な経済的損失が生じる場合です。例えば、新しい高速道路を建設する場合は、(iii)(一)に該当するものと考えられます。
また(ⅲ) (二)に記載の、義務の履行完了部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していることとは、契約期間にわたり、企業が履行しなかったこと以外の理由で契約が解約される際に、少なくとも履行を完了した部分についての補償を受ける権利を有している場合です(収益認識適用指針第11項)。履行を完了した部分についての補償額は、合理的な利益相当額を含む、現在までに移転した財又はサービスの販売価格相当額となります(収益認識適用指針第12項)。
工事契約は、(ⅱ) 又は(ⅲ) の要件を満たし、一定の期間にわたり履行義務を充足する場合が多いものと考えられます。ただし、工事の内容は様々であり、実態に応じて慎重に検討する必要があります。
b. 履行義務の充足に係る進捗度の見積り
一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合、進捗度に基づき、収益を一定の期間にわたり認識します(収益認識会計基準第41項、第44項)。履行義務の充足に係る進捗度の適切な見積り方法には、アウトプット法とインプット法があります。インプット法には、発生したコストを使った方法等が例示されています(収益認識適用指針第15項、第20項)。これまでの建設業会計における実務では、発生原価と工事原価総額を用いて進捗度を測定するいわゆる「原価比例法」を採用している会社が多く、収益認識会計基準においても、原価比例法は「コストに基づくインプット法」と定められていることから、実務上は大きな相違がないものと考えられます。ただし、以下の2点に該当する場合には、進捗度の見積りを修正するかどうかの判断が必要です(収益認識適用指針第22項)。
(ⅰ) 発生したコストが、履行義務の充足に係る進捗度に寄与しない場合
(ⅱ) 発生したコストが、履行義務の充足に係る進捗度に比例しない場合
(ⅰ)に記載の、発生したコストが、履行義務の充足に係る進捗度に寄与しない場合とは、施工上の不具合を原因として、既施工部分の取壊し及び再施工を行う際に発生する原価などが該当するものと考えられます。
c. 履行義務の充足に係る進捗度を見積ることができない場合
一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により処理します(収益認識会計基準第45項)。原価回収基準とは、履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法をいいます(収益認識会計基準第15項)。
ただし、詳細な予算が編成される前等、契約の初期段階において進捗度を合理的に見積ることができない場合には、収益を認識せず、進捗度を合理的に見積ることができる時から収益を認識することができます(収益認識適用指針第99項)。これは、契約の初期段階で発生した費用の額に重要性が乏しいと考えられ、原価回収基準により収益を認識しないとしても、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えられるため、代替的な取扱いが認められたものです(収益認識適用指針第164項、第172項)。当該取扱いについては、詳細な予算が編成される前等、契約の初期段階のみ容認される代替的な処理のため、留意が必要です。
従来の工事契約会計基準における工事進行基準の収益認識の時期と、収益認識会計基準の収益認識の時期
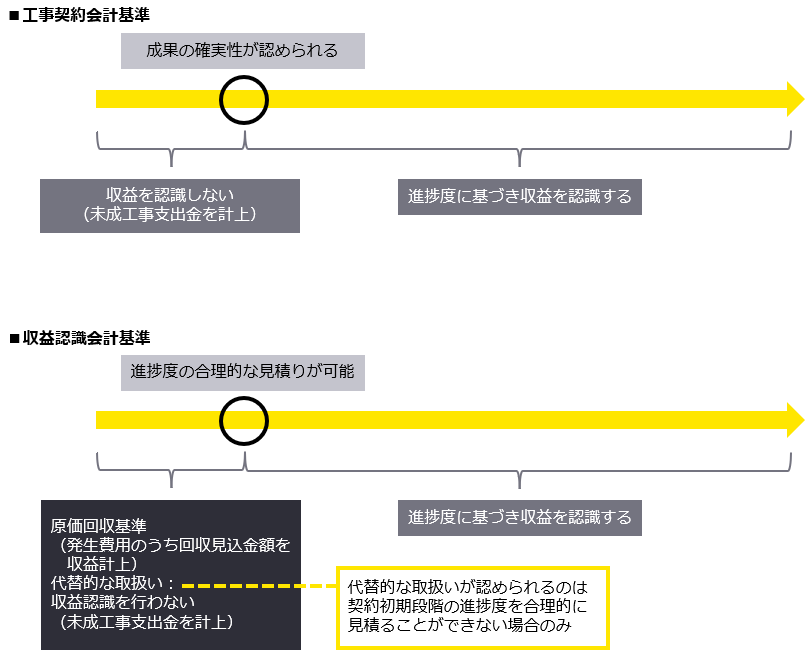
d. 期間がごく短い工事契約
一定の期間にわたり充足される履行義務について、代替的な取扱いとして、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が、ごく短い工事契約は、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することができます(収益認識適用指針第95項)。従来の工事契約会計基準における考え方と同様に、工期がごく短いものは、通常、金額的な重要性が乏しいと想定され、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しても、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えられるため、代替的な取扱いが定められています(収益認識適用指針第168項)。ただし、ごく短いとする期間については、財務諸表間の比較可能性も考慮し、慎重に検討する必要があります。
4. 事後的に信頼性がある見積りができなくなる場合
(1) 概要
事後的な事情の変化により成果の確実性が失われた場合、従来の工事契約適用指針では工事完成基準を適用していました。収益認識会計基準では、発生する費用を回収することが見込まれるときには原価回収基準を適用し、その後の決算日に進捗度を合理的に見積ることができるようになった場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法により収益を認識します。
(2) 収益認識会計基準及び収益認識適用指針の取扱い
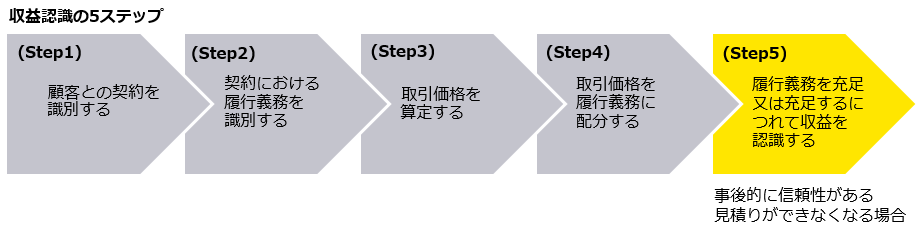
履行義務の充足に係る進捗度は、進捗度を合理的に見積ることができるか否かも含め、各決算日において見直します(収益認識会計基準第43項、第154項)。当該見直しの結果、契約における取引開始日後に状況が変化し、進捗度を合理的に見積ることができなくなった場合で、当該履行義務を履行する際に発生する費用を回収することが見込まれるときには、その時点から原価回収基準により処理します(収益認識会計基準第45項、第154項)。その後の決算日に、進捗度を合理的に見積ることができるようになった場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法により収益を認識します(収益認識会計基準第44項)。いずれの場合においても、会計上の見積りの変更として処理し、それまでに認識された収益を過去に遡って処理するのではなく、進捗度の見積りの変更による影響はその決算日以降において収益に反映させます。
建設業
- 第1回:建設業の概要 (2024.04.24)
- 第2回:建設業における収益認識(1)~工事契約に係る収益認識の単位~ (2024.04.24)
- 第3回:建設業における収益認識(2)~保証サービス、変動対価、重要な金融要素~ (2024.04.24)
- 第5回:建設業の内部統制 (2024.04.24)
- 第6回:建設業会計Q&A (2024.04.24)





