EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

生物多様性を含め、自然関連のフレームワークであるTNFDのコンセプトを盛り込んだ開示をすでに行い、非財務情報の開示で最先端の取組みを行っているキリンホールディングス(株)様に、積極的に開示を進めた背景や取り組み方について伺いました。

キリンホールディングス(株) 執行役員 CSV戦略部長 藤川 宏
1987年キリンビール(株)入社。営業・留学・マーケティング・秘書などを経験後、複数のM&A業務に携わり、豪州、シンガポール、ミャンマーなどに駐在。各地でトップマネジメントに加わり、事業経営を経験。2017年キリンホールディングス(株)人事総務部長、2019年から公益財団法人日本サッカー協会への出向を経て、2022年3月末から現職。
キリンホールディングス(株) CSV戦略部 環境チーム 担当 小此木 陽子
環境技術系のコンサルティング企業、JICAケニア事務所にて気候変動関連の業務に従事後、2021年キリンホールディングス(株)に入社し、現職(CSV戦略部)。10年以上にわたり、自然環境や気候変動に係る業務に携わっており、CSV戦略部においても環境や生物資源関連の取組みを担当。
EY新日本有限責任監査法人 CCaSS(気候変動・サステナビリティ・サービス)事業部 エグゼクティブディレクター TNFD担当 茂呂 正樹
環境・安全衛生(EHS)、サステナビリティデジタルトランスフォーメーションにフォーカスし、サステナビリティアドバイザリー業務をリード。海洋観測技術員、社内環境コンサルタントを経て、EHSコンサルタントとして活躍後、当法人に入社。多くのセクターの専門性、知識を有し、国内外の環境法規制にも明るい。
EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 兼 消費財セクター 非財務情報開示担当 シニアマネージャー 公認会計士 小川 智之
主に消費財メーカーの監査業務に従事。現在は会計監査業務に加え、サステナビリティ開示推進室の業務を手がけ、当法人主導の日経225対象銘柄のTCFD開示調査において消費財分を担当。消費財LTV(長期的価値:Long-term value)チームにも属し、研修やナレッジの発信活動にも携わっている。
要点
- 時間をかけて一つ一つの活動を積み重ね、実践とフィードバックを繰り返すことで、社員のCSVマインドを醸成することができる。
- 事業を継続的に行うためにはローカルな問題とグローバルな問題を両輪として取り組む必要があり、気候変動と生物多様性とを強い関連性があるものとしてとらえることが重要だ。
- 多くの企業が積極的に多様な事例を任意開示することで、フレームワークの整備や改善、あるいは制度化のスピードアップにつながる。
非財務情報の開示が多くの企業で行われていますが、新しい取組みであるため、対応方法を模索している企業も多いと思います。そこで、生物多様性を含め、自然関連のフレームワークであるTNFDのコンセプトを盛り込んだ開示をすでに行い、非財務情報の開示で最先端の取組みを行っているキリンホールディングス(株)様に、積極的に開示を進めた背景や取り組み方について伺い、非財務情報に関する社会的意義についてお伝えします。
【TNFD】
TNFDは、民間企業や金融機関が生物多様性/自然資本に関するリスクや機会を適切に評価し、情報開示をするためのフレームワークを構築する組織です。そのフレームワークは「自然関連」のリスクと機会を特定し、経営の根幹に係る事項として企業戦略に組み込み、対応していくことにより、企業をよりレジリエントなものとする、また機会を生かしビジネスチャンスとしていくことが期待されています。特徴的なコンセプトの一つがビジネスの自然に対する影響と依存度から検討するLEAPアプローチであり、四つのプロセス(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)から構成されています。
Ⅰ 東日本大震災の復興支援がCSV転換のきっかけに
小川 御社は社会的価値と企業価値をつないでいくことに早くから着眼されていましたが、まずは御社のCSV※(Creating Shared Value)戦略に至る経緯についてお聞かせください。
藤川 私たちのグループには公益財団法人キリン福祉財団があり、寄付活動を積極的に行うなど、フィランソロピーやCSRなどへの関心度はもともと高かったと思いますが、大きなターニングポイントとなったのは2011年の東日本大震災でした。当時、CSR部門自体はすでにありましたが、仙台工場が大きな被害を受けたことをきっかけに、社会的責任を果たそうという機運が一気に高まったのです。具体的には、農業や漁業といった一次産業を中心とする東北の復興や若い方々を元気づけるようなアクティビティを多方面で展開しました。震災から3年間で60億円の支援額に達しましたが、まだまだ課題が山積している状態であり、支援を継続するためには経済的価値も一緒に生み出していかなければいけないと、2013年にCSV経営に大きく舵(かじ)を切りました。われわれは農作物を原材料としてものづくりを行うメーカーであり、大量の水を使いますし、酵母も生き物です。プラスチックボトルも使用しています。事業と環境問題との関係性が非常に深いので、過去からの取組みをCSVやTNFDに落とし込みやすかったのです。
小川 東日本大震災後の復興支援という経験によって、CSRからCSVに移行する必要性を感じたということですね。
藤川 そうですね。当社は長期非財務目標として、社会と価値を共創し持続的に成長するために「CSVパーパス」という指針を打ち出しています。アルコールの有害摂取の根絶に向けた取組みを着実に進展させるという酒類メーカーとしての責任を土台に、健康・環境・コミュニティをわれわれが取り組む社会課題として定めたのが2013年であり、こうした取組みへといち早く舵を切るという意思をトップが強く打ち出したことも、CSVを浸透させるという意味では非常に大きい役割を果たしたと思います。
Ⅱ まずはステークホルダーの環境問題に対する感度を高める
小川 多くの企業が「CSR活動をどのように企業価値につなげていくか」という点で頭を悩ませていると思います。例えばCSRを企業価値につなげ、CSVに移行していく際に、リード役となる方と一般の社員の方との温度差があり、一般社員にCSVを啓発することが高いハードルになっているケースが多いのですが、御社はどのように意識を一体化させているのでしょうか。

藤川 多くの企業にとって共通の課題だと思います。社会的価値を見つけ出し、解決すべき課題を整理することができても、それを自社の経済価値につなげるのが非常に難しいです。おっしゃる通り、社会課題の取組みの最前線に立っている者と他の業務を主としている一般社員では互いの熱量に大きな差があり、「課題が大きすぎて、自分一人の力では何もできない」と思われてしまいがちです。実際、ある面でそれが事実だからです。しかし、CSVのマインドを地道に育てることによって、得意先の物流の改善や、GHG(温室効果ガス)の削減、人材不足の解消につながるなど、実はCSVの効果に後から気づくことが多々あります。まずは一人ひとりの力だけではできないことも、まわりの同僚や得意先、あるいは外部の機関を巻き込んで大勢でやれば実現できるという意識づけを行っていくことが重要だと考えています。そこで当社では、CSVとは何かということを知ることからはじめ、イントラネットを中心に社内のCSV活動の事例を発信したり、終業後に他社の取組み事例の紹介を自由参加で行ったりしています。また、CSVにつながるR&Dについても、全社に呼びかけてアイデアやテーマを募集するなどの取組みを行っています。
小川 御社のことを、はるか先を行くトップランナーとして見ている企業が多いと思いますが、ある日を境に急に社員の意識が変わるわけではなく、一つひとつの活動を積み重ねて一般社員とリーダー役となる方とのタッチポイントを増やし、実践とフィードバックを繰り返すことでCSVマインドが醸成され、企業の血になっていく。時間をかけて取り組んできた結果ということですね。
Ⅲ 事業の継続のために、ローカルな課題とグローバルな課題の両輪で取り組む
小川 もう一つお伺いしたいのは、CSVには取り組めても、TNFDとなると多くの企業にとって一気にハードルが高くなるように思います。先ほど、TNFDと御社のビジネスは親和性が高いとお話しされていましたが、実際にどのような経緯でTNFDに取り組まれることになったのでしょうか。
藤川 当社は2013年に、長期環境ビジョンを作っていました。もともと1992年に開催された地球環境サミット以降、環境に対する取組みは着実に進めてきており、製造現場での消費エネルギーや廃棄物、無駄などを減らしていくことへの意識は高かったと思います。そして2011年には仕入れている原料に関するリスク調査をはじめ、2013年には「キリングループ持続可能な生物資源利用行動計画」を策定し、水や紅茶葉、パーム油を重要な生物資源と位置付けました。そして、2019年には新たに「キリングループ環境ビジョン2050」を策定し、「生物多様性」と「水」、「容器包装」と「気候変動」にしっかり取り組んでいくことを明確にしました。この4つのテーマは、当社の事業に直結しているので、取り組みやすかったと思います。また、気候変動があれば農作物がとれなくなりますし、水の渇水や洪水の原因にもなります。容器包装については海洋汚染などに直結するグローバルな課題です。一方で、生物多様性や水は比較的ローカルな問題ですが、事業を継続的に行うためにはローカルな問題とグローバルな問題を両輪として取り組む必要があります。

小川 気候変動と生物多様性を別物として切り離して考えるのではなく、強い関連性があるものとしてとらえることが大切なのですね。
藤川 そういうことです。一方、環境問題への取組みをESG投資の観点から考えると、環境を維持し、リスクを低下させることで、価値の保全につながり、資本コストを下げられるとわれわれは考えています。資本コストが下がると、企業価値が上がるので、経営的にも大きな役割を果たすことになります。つまり、TNFDのフレームワークを活用して自然資本の維持向上に努めれば、持続的な原材料の調達につながり、事業リスクを軽減することになり、企業価値の向上にもつながるということです。実際に、環境にしっかり取り組むことでグリーンボンドのような、多少ではありますが低い利率での発行もできています。
小川 生物多様性の保全がいかに企業価値につながるのかということについては、十分に理解されていない部分も多いと感じています。今、お話しいただいた資本コストの低減が最終的には企業価値につながっていくことについては、現在研究が進んでいます。今後、実証例が増えていくことで、TNFDをテーマにした価値保全への取組みは、社会的責任だけではなく企業価値の向上とイコールであり、広く企業の財務戦略の中に組み込んでいくことで社会的価値が創造されていくのですね。私自身も、理解や実績が積み上がっていくことで、自社の価値につながる取組みとして認識されるようになると期待しています。
Ⅳ キリン独自の醸造哲学がTNFDの土台に
茂呂 TNFDは気候変動に続いて注目されている「自然」にフォーカスした開示フレームワークで、今後の自然との接点、関わり方の機会やリスクをしっかり捉えて開示していきましょうという取組みです。最終版としては2023年に出る予定ですが、現在、β版が3カ月ごとに発行されています。現在は気候変動をテーマとした議論が盛り上がっていますが、気候変動は地球環境問題の一つであり、自然資本からどのような恩恵を与えられているか、しっかりと見定めた上でリスクを捉えていきましょうという流れになってきています。ご指摘の通り、生物多様性に対して、多くの企業が何をどうしたらいいか分からない状況ではないかと推察しますが、すでにさまざまな取組みをされている御社としては、現状をどのように捉えていらっしゃいますか。
藤川 生物多様性はローカルな課題であり、国や地域によって生息している生物がまったく異なります。業界によっても原料として使用している生物資源が違うので、かなり個別性が高いです。われわれは大麦や、茶葉、ホップ、大豆といった自然から得られる原材料を使っていますが、自然資本をあまり使用しない企業によってはどこから手を付けていいか分からないということが往々にしてあると思います。例えば、エネルギーを扱っている会社にしてみれば「生物多様性はあまり関係ない」と思われるかもしれません。ただ、水や紙などは、量の違いはあってもどんな業種の会社でも使用しているはずですし、事業そのものに使わない場合でも、事業にとってどのような自然資本が重要なのかというマテリアリティの視点から考えると、何らかの方針が出せるのではないでしょうか。
茂呂 その点、御社の場合は製造過程においても、大量の洗浄水を使用するので、貴重に使わなければならないという考え方が浸透していたのかもしれませんね。特に日本はもったいない精神が強いですから、工場などの製造現場にも落とし込みやすいと思います。御社のウェブサイトを拝見すると、かなり綿密に水を再利用するなど、1滴たりとも無駄にしない努力をされていますね。
藤川 それは、当社の醸造哲学に、「生への畏敬」という考え方がしっかりと明示されているからかもしれません。「生きとし生けるもののまわりにわれわれは生きるものなので命あるものを大事にしていこう」という意味なのですが、そうした「生への畏敬」が根底にあることがわれわれの事業の特性であり、カルチャーとしても受け継がれています。
茂呂 以前、生麦工場に伺った際も、ゴミが非常に細かく分別されていて、とても感心しました。御社のカルチャーが、目に見える形でちゃんと息づいているのだと思いました。
Ⅴ 多くの企業が任意開示に着手することで、制度化が加速
茂呂 少し前ですがTNFD事務局の方々とお話しする機会があり、日本から来たと伝える度に御社の名前が挙がり、いち早く開示しておられることについて非常に高く評価されていました。それだけ御社の名前が広がっていて、世界に先駆けてTNFDのLEAPアプローチに沿って開示されていることは大きなインパクトになっていると思います。新しいことに取り組む際、他社の様子を見ながら少しずつ進めていく企業もありますが、TNFDを社内で最初に取り組む際は相当ご苦労されたのではないでしょうか。

藤川 私の肌感覚としては、それほど大変ではなかったように感じています。TCFDに早めに取り組み、評価されたこともプラスに働きました。2017年にTCFDが初めて発表されて、2018年には開示フレームワークを使い始めていたので相当に早い決断と着手でしたが、「世界のCSV先進企業へ」と打ち出していたので、それを具現化して行動に移したというところです。最先端のフレームワークを導入すると話題になりますし、大きな反響やコメント、フィードバックが得られます。世界のトップを目指すなら、そういった動きは不可欠です。また、さまざまな評価機関や研究会等のパイロットプログラムに入っていくなど、ルールメイキングに関与することができます。もちろん、相当な実力がないと中心メンバーになることは難しいですが、パイロットプログラムであればわれわれも関与できますし、欧州中心で進めているルールメイキングの部分に、多少なりとも影響力を出せるということもあったので、いち早く着手してしまおうという考えはありました。また、開示してみて間違いがあれば、その時に直していけばいいという考えもあると思います。あくまでも任意開示なので、制度開示ほどコンプライアンスが厳しいわけではないため、その時に直していけばいいという考えもあると思います。逆に、多くの企業が任意開示をして、多様な事例が出てこないと制度開示に発展していかないと思うので、もっと多くの企業が積極的に任意開示していただくことが、フレームワークの整備や改善、あるいは制度化のスピードアップにつながると思います。
茂呂 TNFDのタスクフォースメンバーの方に今後のメッセージを聞いた際も、「恐れずに取り組んでほしい」とおっしゃっていました。2023年を待っていたら遅いと。新しい情報が次々にβ版で出てくるので、様子見をしていると動けなくなってきます。だから恐れることなく、まずはトライしてみて欲しいとのことでした。御社が先駆けとして着手し、先例を見せることは多くの企業に勇気を与えたと思います。
Ⅵ 注力すべき点を再考することで、マテリアリティが明確に
茂呂 御社は以前から環境に対する多様な活動をされているので、実際に開示を進める際、肌感覚レベルでの生命資本、生への畏敬といったカルチャーとそれに付随する取組みがあり、それらを整理することでTNFDの枠にきれいに収まったということだったのでしょうか。
藤川 そうですね。過去の事例のリフレームにトライしてみた感じでしょうか。小此木さん、実際はどうでしたか。
小此木 おっしゃる通りです。SBT(Science Based Targets)のフレームワークで整理した後に、TNFDの支援ツールであるLEAPの枠組みで再整理してみました。過去10年間ぐらい積み上げてきたものを、少しだけ切り口を変えて組み替え直しただけなので、これほどの反響があるとは正直驚きました。

茂呂 LEAPを拝見しましたが、非常に面白かったです。日本の長野の事例、スリランカの茶葉の事例、オーストラリアの水の事例とそれぞれにストーリーがありながら、LEAPでまとめるとこういう形になるのかということも分かりました。私は気候変動・サステナビリティ・サービス(CCaSS)チームとして、いろいろなお客さまとお話ししますが、TNFDや生物多様性に取り組んでいきたいと思われている方は多いものの、まだよく分からなくて及び腰になっているケースが多いです。バリューチェーンの上流側、つまり一次産業に近くなればなるほど肌感覚で危機感を持ち、御社と同様に独自で調査をしたり、リスク分析をされている企業もありますが、さまざまな状況から継続的に実施することが難しい企業も多いと思います。そういった企業も、TNFDのフレームワークで考えていけば、足りない部分が見えてきて、そこを補完していけばリスク回避につながっていくのかもしれません。
小川 先日、ある企業のCFOにTCFDの開示やコーポレートガバナンス・コードへの対応についてお伺いしたのですが、「対応に難しさを感じている」とのことでした。その企業はエンタテインメント系でモノづくりをしている業種ではないため、例えばオフィスで使っている機器類を省エネ対応のものに変えていくことでCO2の削減になることはイメージできても、それによって自分たちの事業がどう変わるか、何が価値になるのかイメージしづらいのだと思います。藤川さんがおっしゃっていた通り、水や紙、電気などはどの企業にとっても事業活動に不可欠なものですが、マテリアリティを判断していく中で任意開示していくという場合は、TCFDという言葉以外にも切り口があるかもしれません。「御社ならこういうところに結び付きがあります」「御社はこの部分はすでに取り組まれていますよね」と具体的に示すことで視点が広がり、企業の特性や強み、価値に気付くお手伝いができると感じました。
藤川 今のお話を聞いて思ったのですが、人的資本や自然資本、製造資本、社会関係、財務資本、知的資本など企業がインプットする経営資源は、企業によって異なります。先ほどのエンタテインメント系の企業であれば、人的資本がかなり重要になってくるでしょう。当社の場合は、自然資本が重要であり、どこに注力すべきかを考えれば、マテリアリティもおのずとはっきりしてくるのかもしれません。また、例えば環境破壊についてはグローバルな課題でもあるので、道徳や倫理に近いところで、皆で取り組むべき問題であることをどれだけ意識するかといったことも、会社によって異なるのかもしれません。いずれにしても、社会の課題だという思いがあれば、なんらかの形で取り組むべきだという方向には進むはずです。
Ⅶ さまざまな立場から、持続性にアプローチする
茂呂 スリランカの茶葉について現地の環境保全のための取組みもされていますが、保全しなければいけない大切なものであると社内に共通の意識として浸透させていくことにもつながっているのでしょうか。
藤川 そうですね。第一次産業の方々と同様に、われわれのビジネスも、茶葉を仕入れられなくなったら事業が成り立たなくなってしまうのです。日本の輸入紅茶葉の50%がスリランカ産ですが、そのうちの25%を当社が使っているので、スリランカの茶葉が手に入らなくなってしまうと『午後の紅茶』が作れなくなります。それは大きなリスクだという話がきっかけになりました。結果、現地の自然環境を良くし、農園で働く方たちの生活環境も見直さなければいけない、経済環境も良くしなければいけないという流れになり、ぜひ取り組もうということになりました。一方で、長野の葡萄農園は自社管理ができ、自分たちが育てた葡萄のクオリティがワインに直接影響します。必然的に、農園周辺の自然環境の重要性を身にしみて理解できます。つまり、原料に関して申し上げると、自社がサプライチェーンの上流であると同時に、茶葉など他社から仕入れてくるものもあり、調達方法も多様です。当社は麦も大量に仕入れていますが、複数の先進国から仕入れているので、スリランカのようなリスクはありません。
茂呂 代替が効くのですね。
藤川 そうです。国もエリアも代替が可能です。ただ、それも今回のウクライナ情勢によって見直しが必要だとあらためて思いました。容易に手に入ると思っていた大麦でさえ、場合によっては飼料に優先的に使われる可能性があり、価格が高騰するリスクがあることも視野に入れておかなければいけません。したがって当社は、サプライチェーンでわれわれがコントロールできるところは責任をもって行いつつ、それ以外の部分ではサプライヤーなど協力会社の方々と一緒にいろいろな部分のチェックを行っています。
茂呂 TCFDで言うと、スコープ1、2をしっかりやって、次に影響力を及ぼすところはどこかを考えると、スコープ3のサプライチェーン、バリューチェーンであり、自分たちのオペレーション、そしてビジネスパートナーたちにも影響していくということですね。御社の活動範囲とつながる部分は非常に広範囲なので、かなりの影響力があるはずです。
藤川 GHGもそうですが、「私たちも減らしていきます。だから皆さんも一緒にやっていきましょう」というのが当社の基本的な考え方です。自社の削減と、スコープ3の方々の削減を一緒に取り組んでいます。先ほども申し上げた通り、自分たちで原料を作る以外に、仕入れもあり、仕入れのサポートをお願いする場合もあるなど、さまざまなパターンがある中で、皆さんと一緒に盛り上げながら持続的な取組みとなるよう尽力しています。
Ⅷ 今後は原材料情報の深掘りと地域的な拡大を視野に
茂呂 TNFDのβ版が次々に出て、前回発行(2022年6月)のβ版ではLEAPアプローチのLとEの考え方が示され、AとPはまた後でという形で予告だけされてきましたが、シナリオがないと難しい将来リスクをどう見ていくかというところが指針として出てくるようです。開示のための情報が順次ガイドラインとして出て来ていますが、御社は今後どのように生物多様性関連の開示を拡張していく予定ですか。
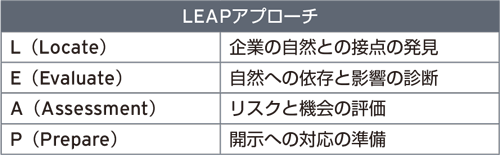
小此木 今回の環境報告書で出したTNFDのβ版に関しては、これまでの活動の切り口を変えて開示をした形です。従ってLとEの部分が十分に検討できているかというと、まだまだやり残していることがあるという認識を持っており、今まさにその部分を改めて深堀りしています。TNFDもSBTN(Science-Based Targets Network)も考え方としてはかなり似ており、両方とも広く事業に対する影響依存を確認した上で自社の事業を切り口として、重点すべき課題を評価し、次の目標設定につなげます。ガイドラインでは、TCFDと同様、TNFDも5年がかりで最終版を作っていくように指示されていますが、できるところから着手し、5年を待つことなく早めに最終版を完成したいと考えています。
茂呂 TNFDの技術ガイドライン、テクニカルガイドラインでも、まずは優先セクターなどやれるところから着手し、そこから徐々に広げていくことを推奨していますね。LとEはある程度そろっているとおっしゃっていましたが、ポートフォリオが地球上のどこにあるかを確認し、それがどういった形で自然界と接点がありそうかというのがLになる。また、そこのセクターでは自然界にどのような影響を与えているか、もしくはどのようなインプットがあって依存しているかの整理は、現状のスナップショットを取るようなものです。オペレーションを正しく理解した上で大きくポートフォリオを持っていれば、俯瞰しながらどこが危険なのかしっかり確認しておくのがLとEになると思います。この点は、御社が各ポートフォリオの上で、各工場、拠点、世界中のロケーションですでに収集していて、ある程度現状が見えていたからこそできると思うのですが、そのような理解でよいでしょうか。
小此木 厳密に言うと、例えば原料を調達する農園レベルまで把握しているかというとそこまでできていない部分もあります。ただ、現在進行形で、今年の原材料の調達において農園レベルまで確認可能かどうかを、メインサプライヤーに問い合わせています。商社を経由して農産物を購入しているため、国はある程度固定されていても農園は固定されていないのが実情です。そこをどう捉えていくかは今後の課題の一つです。
茂呂 商社が原料を集めて御社に卸すので、仕入先の農園は年によって変わってくるということでしょうか。
小此木 当社からクオリティをリクエストするので、クオリティに合致した農園から調達してもらう形になります。同じ農園が、毎年クオリティの基準をクリアできるか保証できないため、場合によっては農園が変わることもあるのです。
茂呂 そうすると、自社のオペレーションだけではなくバリューチェーンの上流までさかのぼるという課題が出てくるのですね。その点も踏まえて、網羅的に見た時、次の開示に何が足りないのかということを抽出していらっしゃるということで、やはり、とても進んでいるなと感じます。
最後になりますが、御社はすでにたくさんの取組みを先進的に行っていますが、これまでの開示内容から見えてくるリスクや機会を踏まえ、今後新たに取り組んでいくアクションについても、ぜひお聞かせください。
藤川 今、小此木が申し上げた原材料の深掘りをするというのが一つと、もう一つは地域の拡大です。現在、紅茶葉に関してスリランカの現地保全に取り組んでいますが、今度はコーヒー豆に関して、ベトナムでも同様にレインフォレスト・アライアンス認証取得支援に取り組んでいきたいと考えています。いずれにしても、これまで社風や文化として環境問題に対する感度が高かったおかげで、こうしたTNFD開示にもスムーズに着手することができました。今後も過去の評価に甘んじることなく、先進的な取組みも含め、全社員一人ひとりが社会的な課題を見つけ、自律的に取り組める組織にしていきたいと思います。
小川 御社の取組みは他の企業の指針として今後も高い関心を集めると思いますし、当法人としても大いに学ばせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
※ 共通価値の創造。社会的ニーズや社会問題の解決に取り組むことで社会的価値の創出と経済的価値の創出を実現し、成長の次なる推進力にしていくこと。
「情報センサー2022年12月号 特別対談」をダウンロード
サマリー
生物多様性を含め、自然関連のフレームワークであるTNFDのコンセプトを盛り込んだ開示をすでに行い、非財務情報の開示で最先端の取組みを行っているキリンホールディングス(株)様に、積極的に開示を進めた背景や取り組み方について伺いました。
情報センサー
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計・税務・アドバイザリーなどの企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。
関連コンテンツのご紹介
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
EYはビジネスがサステナビリティに貢献し、またサステナビリティがビジネスに貢献するよう尽力しています。
長期的価値は、目的を明確にし、幅広いステークホルダーに焦点を当て、長期的にビジネスを維持することから生み出されます。



