EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
わかりやすい解説シリーズ「減損会計」 第4回:減損損失の認識の判定
公認会計士 浦田 千賀子
【ポイント】
減損損失の認識の判定とは、減損の兆候のある資産又は資産グループについて、帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フロー総額を比較して、減損を実施するか否かを判断することです。
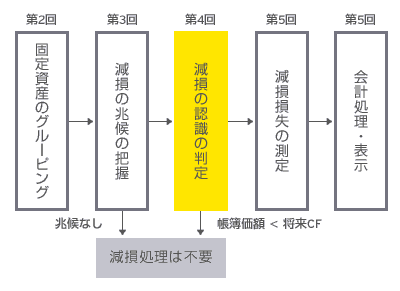
減損会計の第3段階は、減損損失の認識です。このステップでは、減損の兆候を検討した結果、兆候があると判断された資産又は資産グループについて、減損を実施する必要があるかを判断します。
ここで、減損損失の測定の前に、割引前将来キャッシュ・フローを利用して減損損失の認識ステップを経由するのは理由があります。減損損失は将来キャッシュ・フローの見積りに大きく依存し、かつその見積り自体が、経営計画などの経営者の判断に基づいているため、主観的な要素が多くなってしまいます。そのため、認識ステップを経由することで、減損の存在が相当程度に確実かを判断したうえで、減損の測定を実施する必要があるのです。
減損損失の認識は、以下のように行われます。
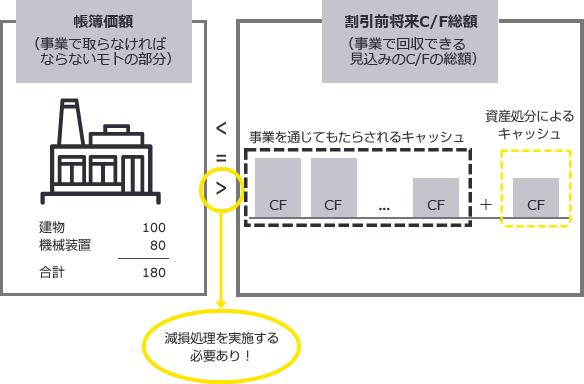
このように、固定資産の帳簿価額(事業で取らなければならないモトの部分)と、将来キャッシュ・フロー(事業で回収できる見込みのキャッシュ・フロー)の割引前の総額を比較し、固定資産の帳簿価額の方が大きければ、減損処理を実施する必要がある、と判断されます。
ここで重要になるのが、割引前将来キャッシュ・フローの算定方法です。算定に当たり、注意すべき要素が2点あります。
【ポイント】
割引前将来キャッシュ・フローの算定方法のポイントは、以下の2点がポイントとなる。
① 見積期間(いつまでを見積期間とするか)
② 見積方法(どのようにして行うか)
まず1点目は、割引前将来キャッシュ・フローの見積期間です。
割引前将来キャッシュ・フローは、資産の経済的残存耐用年数まで見積もることを基本的な考え方としています。
ただし資産の中には、土地のように使用期間が無限になりうるものもあるため、その見積期間を制限する必要があることや、一般に、長期間にわたる将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性が高くなることから、適用指針では、資産又は資産グループの主要な資産の耐用年数が20年を超えるか否かにより、計算方法が異なるとされています。
① 20年を超えない場合
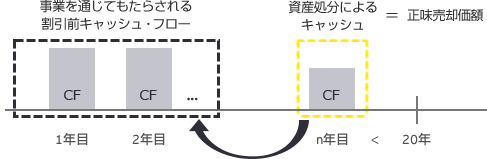
主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超えない場合、経済的残存使用年数が経過した時点(上記図n年)における主要な資産の正味売却価額を、当該経済的残存使用年数までの割引前キャッシュ・フローに加算します。
② 20年を超える場合
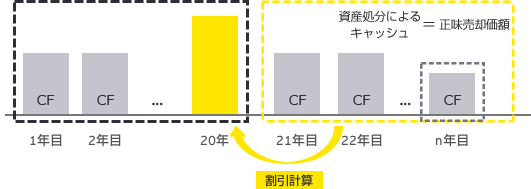
主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超える場合、21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに基づいて算定された20年経過時点(上図黄色点線)における回収可能価額を、20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算します。
基準で見積り期間の最長が20年と決められているのは、無限に認めてしまうと、主要な資産が土地の場合に耐用年数が無限になってしまうこと、あまりにも先の将来予測は市場環境が現在と大きく変わっている可能性があり、その予測が不確実であるためです。
そして2点目は何をもとに割引前将来キャッシュ・フローを見積もるのか、その見積り方です。
具体的に以下の例で、割引前将来キャッシュ・フローの具体的な見積り方について、見ていきましょう。
(前提)
- 会社は、×1年~×6年まで、資産を利用することを予定している(×7年に処分予定)。
- 会社が作成している中期計画は、×1年~×5年の期間である。なお、中期計画は、会社の経営環境や予算等と整合した情報に基づいて作成されている。
- ×3年、×4年の営業CFはそれぞれ200とする。
- ×6年は、成長率が10%としている。従って、売上、売上原価の発生額が×5年度の10%増との仮定を置いている。(販管費は一定とする)
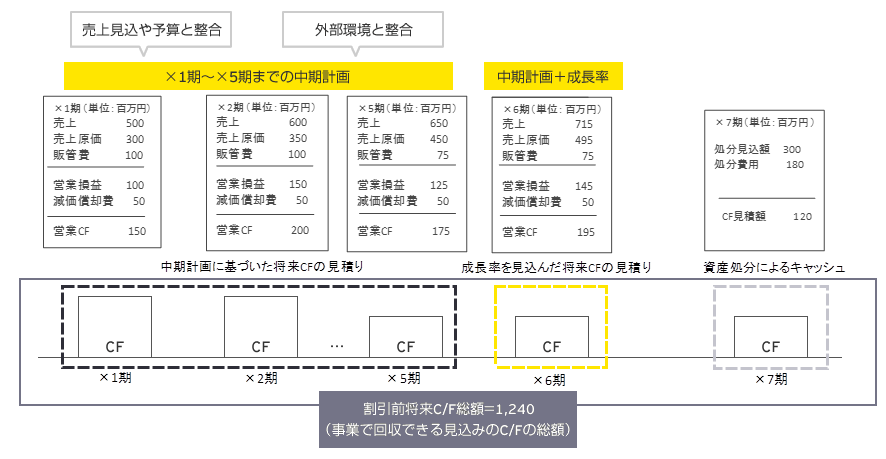
適用指針では、減損損失の認識に用いられる将来キャッシュ・フローを、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積るとされています。その際に留意すべき点として、以下の点が挙げられています。
(1) 経営環境などの外部要因や、売上見込み、予算などの内部の情報と整合した数値を前提として作成された中長期計画に基づいて見積りを行う(上記例×1年~×5年)
(2) 会社に中長期計画が存在しない場合も、経営環境などの外部要因や、売上見込み、予算などの内部の情報に基づいて見積りを行う
(3) 中長期計画の見積期間を超える期間の将来キャッシュ・フローを算定する場合、計画に基づいた一定の成長率の仮定を行って見積もりを行う(上記例×6年)
(4) 将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、現金基準の他、発生基準に基づいて見積った金額に減価償却費などの重要な非資金損益項目を加減した金額を使用することができる(上記例×1年~7年の簡易PL)
わかりやすい解説シリーズ「減損会計」
- 第1回:減損会計の概要 (2015.12.11)
- 第2回:資産のグルーピング (2016.09.07)
- 第3回:減損の兆候 (2016.09.15)
- 第4回:減損損失の認識の判定 (2016.09.26)
- 第5回:減損損失の測定 (2016.09.30)




