EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2024年3月期 決算上の留意事項
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士
加藤 圭介、平川 浩光、久保 慎悟、前川 健太郎、山澤 伸吾、松川 由紀子、浦田 千賀子
この2024年3月期決算においては、実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」及び実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」が原則適用になり、また、改正法人税等会計基準の早期適用が可能となっています。そして、改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」は2023年3月期決算に引き続き適用となります。
本稿では、これらの論点のうち、適用対象となる企業が多いと思われるものについて、基本的な取扱いを中心に、2024年3月期決算での留意事項をQ&A方式で解説します。
また、「2023年3月期 決算上の留意事項」において掲載していたインボイス制度編については、2023年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることを踏まえ、再掲しています。この他、「2023年3月期 決算上の留意事項」又は「2023年6月第1四半期決算上の留意事項及び第1四半期決算でよくあるポイント」において掲載した事項のうち、本稿においても有用と考えられる等により再掲している項目については、【再掲】又は【再掲・一部更新】を付しています。
なお、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」については、2024年3月期決算では適用されませんが、適用初年度の税額の見積方法の検討等に時間を要すると考えられることから、本稿にて紹介することも有用と考えられるため追加しています。
- 会計上の見積りのポイント編
Q1 会計上の見積りの全般的な留意事項【再掲・一部更新】
Q2 固定資産減損会計【再掲】
Q3 外貨建有価証券【再掲】
Q4 関係会社投融資
Q5 税効果会計-企業の分類((分類4)のいわゆる反証規定)【再掲】
Q6 税効果会計-回収可能性の判断手順【再掲】
Q7 退職給付会計
- 電子記録移転有価証券表示権利等編
Q8 電子記録移転有価証券表示権利等に関する取扱い
- 電子決済手段編
Q9 電子決済手段に関する取扱い
- パーシャルスピンオフ編
Q10 いわゆるパーシャルスピンオフ税制の概要
Q11 完全子会社株式に関して一部の持分を残す株式の現物配当の会計処理
- 改正法人税等会計基準編
Q12 改正法人税等会計基準の概要及び適用時期【再掲】
Q13 税金費用の計上区分【再掲】
Q14 グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果【再掲】
Q15 経過措置【再掲】
- インボイス制度編
Q16 インボイス制度の概要【再掲】
Q17 インボイス制度において仕入税額控除を行うことができない消費税相当額の会計処理【再掲】
Q18 インボイス制度下の控除不可消費税相当額を仮払消費税として区分して計上する場合の会計処理【再掲】
- グローバル・ミニマム課税制度編
Q19 グローバル・ミニマム課税制度の概要【再掲・一部更新】
Q20 グローバル・ミニマム課税制度の税効果会計への影響【再掲・一部更新】
Q21 グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)の会計処理及び開示
- 令和6年度税制改正編
Q22 令和6年度税制改正の概要
- 改正四半期開示制度編
Q23 改正四半期開示制度の概要
Q24 中間財務諸表に関する会計基準
- 非財務情報編
Q25 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報等の開示
なお、本稿の本文において、会計基準等の略称は以下を用いています。
|
正式名称 |
本文中の略称 |
|---|---|
|
「税効果会計に係る会計基準」 |
税効果会計基準 |
|
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 |
金融商品会計基準 |
|
企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」 |
四半期会計基準 |
|
企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」 |
企業会計基準第24号 |
|
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」 |
法人税等会計基準 |
|
企業会計基準第28号「税効果会計に係る会計基準」の一部改正 |
企業会計基準第28号 |
|
企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」 |
中間会計基準 |
|
企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」 |
自己株式等会計適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 |
減損適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 |
四半期適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」 |
退職給付適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 |
回収可能性適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 |
税効果適用指針 |
|
企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」 |
中間適用指針 |
|
実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」 |
実務対応報告第43号 |
|
実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」 |
実務対応報告第44号 |
|
実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」 |
実務対応報告第45号 |
|
実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」 |
実務対応報告第46号 |
|
会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 |
外貨建取引等実務指針 |
|
会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」 |
金融商品実務指針 |
|
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 |
資本連結実務指針 |
|
日本公認会計士協会の消費税の会計処理に関するプロジェクトチーム「消費税の会計処理について(中間報告)」 |
消費税中間報告 |
|
監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」 |
後発事象取扱い |
Q1. 会計上の見積りの全般的な留意事項【再掲・一部更新】
ロシア・ウクライナ等の世界情勢を背景としたビジネス環境の変化がある中で、会社(3月末決算)が決算に際して、留意すべき事項を教えてください。
A1.
昨今の環境において、海外を中心とした金利の上昇、為替相場の急激な変動、原材料の価格、燃料・資源価格、輸送運賃価格等の上昇といったビジネス環境の変化が生じており、企業によっては業績に影響が出ていることも考えられます。
業種によって影響度合いは様々ですが、一般的に影響する会計処理や開示の具体例を(図表1)にまとめています。
図表1 一般的に影響する会計処理や開示の具体例
|
勘定科目 |
会計処理・開示への影響 |
|---|---|
|
棚卸資産 |
棚卸資産の評価損 |
|
金融商品 |
外貨建有価証券の評価(Q3)、債券の減損処理、関係会社投融資(Q4) |
|
退職給付会計 |
割引率の見直し(Q7)、長期期待運用収益率(翌期首における見直し)、早期割増退職金(Q7) |
|
減損会計 |
減損の兆候(Q2)、将来C/Fの予測(仮定や基礎データ等への影響(Q2)、割引率 |
|
税効果会計 |
企業の分類(Q5)、回収可能性の判断(Q6) |
|
連結 |
為替相場に重要な変動があった場合の期ズレ決算在外子会社の換算手続 |
|
開示 |
会計上の見積りの開示における言及、継続企業の前提の開示 |
Q2. 固定資産減損会計【再掲】
為替、金利、相場変動が固定資産減損会計に与える影響として、留意すべき事項を教えてください。
A2.
(1) 減損の兆候
資産又は資産グループが使用されている事業に関連して、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっているか、継続してマイナスとなる見込みである場合や、経営環境が著しく悪化したか、又は悪化する見込みである場合には、減損の兆候となるとされています(減損適用指針12項、14項)。また、経営環境が著しく悪化したか、又は悪化する見込みである場合として、材料価格の高騰や、製・商品店頭価格やサービス料金、賃料水準の大幅な下落、製・商品販売量の著しい減少などが続いているような市場環境の著しい悪化が例示されています。このため、例えば、為替、金利、相場変動の影響に伴い、仕入価格が高騰し、営業損益のマイナスが続くことが見込まれるような場合や、材料価格の高騰が続いているような場合には、減損の兆候に該当する可能性があるため、為替、金利、相場変動が将来の企業の経営環境にどのような影響を与えるかについて、慎重に検討する必要があります。
(2) 外貨建ての将来キャッシュ・フローの見積り
将来キャッシュ・フローの見積りにあたり、売価や原材料仕入価格の見積りは、翌期以降の変動見込みを反映させる必要があります。また、将来キャッシュ・フローが外貨建てで見積られる場合、減損適用指針18項及び19項に基づいて算定された外貨建ての将来キャッシュ・フローを、減損損失の認識の判定時の為替相場により円換算し、減損損失を認識するかどうかを判定するために見積られる割引前将来キャッシュ・フローに含めるとされています(減損適用指針20項、35項)。このため、将来キャッシュ・フローが外貨建てで見積られる場合には、将来の為替相場を予想して円換算するのではなく、減損損失の認識の判定時の為替相場により円換算することとされている点、ご留意ください。
Q3. 外貨建有価証券【再掲】
為替変動が外貨建有価証券の評価減に与える影響として、留意すべき事項を教えてください。
A3.
時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下の事実が生じている場合に、評価額の引下げが必要ですが、著しい下落又は低下の判断は、外貨建てで行うとされています。また、外貨建有価証券について時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により評価額の引下げが求められる場合には、当該外貨建有価証券の時価又は実質価額は、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額によるとされています(外貨建取引等実務指針18項、19項)。
このため、円安の状況下で円貨建てでは50%程度以上の下落又は低下がない場合であっても、著しい下落又は低下の判断は外貨建てで行うこととされていますので、外貨建てで50%程度以上の下落又は低下がある場合には、評価の切下げを行うことになります。
その場合には、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額が評価額となりますので、決算日の異なる子会社株式について、決算日の実質価額を基に評価額の切下げを行う場合であっても、親会社の決算時の為替相場により円換算する必要がありますので、ご留意ください。なお、決算日の異なる子会社株式の実質価額の算定については、Q4関係会社投融資A(3)をご参照ください。
Q4. 関係会社投融資
子会社の業績が悪化し、債務超過となりました。子会社株式の減損処理を検討していますが、その際に留意すべき事項を教えてください。
A4.
(1) 市場価格のない株式等の減損処理
株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければなりませんが(金融商品会計基準21項、金融商品実務指針92項)、子会社や関連会社等(特定のプロジェクトのために設立された会社を含む。)の株式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画等を入手して回復可能性を判定できることもあるため、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められます(金融商品実務指針285項)。回復可能性の判定はおおむね5年以内に実質価額が取得原価の100%まで回復することが十分な証拠によって裏付けられることが必要であり、判定の結果、回復可能性が見込まれない場合には、現時点の実質価額まで減損処理することになります。
回復可能性の判断における5年とは、最初に実質価額が取得原価の50%を下回った年から5年間であるという点には留意が必要です。また、実質価額が取得原価の50%を超えても当初から5年間は100%まで回復するかを継続して確認する必要があります。実質価額が取得原価の50%を下回った最初の年に回復可能性があると判断した場合、翌年度においても回復可能性を検討する必要がありますが、翌年度における検討では残り4年で回復するかどうかを検討することになります。そして、検討の結果、実績が計画を下回り、当初の計画通りの回復可能性がないと判断される場合には、その時点の実質価額まで減損処理することになりますので、留意が必要です。
なお、会社の超過収益力や経営権等を反映して、実質価額が1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額となっていることもありますが、超過収益力が見込めなくなった場合には、超過収益力の減少により低下した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている限り、減損処理が必要な点にも留意が必要です。
(2) 関係会社事業損失引当金
子会社の業績が悪化している場合、子会社向け債権の貸倒引当金の計上や、債務保証がある場合には債務保証損失引当金の計上を検討することが必要となります。さらに子会社が債務超過に陥っている場合には、現在保有している投資が回収できないだけでなく、欠損部分を将来的に親会社が負担することがあるため、投資金額を超えて将来負担することとなる金額を見積り、関係会社事業損失引当金を計上することを検討する必要がでてきます。関係会社事業損失引当金の見積りには、損失に対する負担割合や、子会社の資産及び負債の含み損益等を考慮し、当該子会社に対する貸倒引当金や債務保証損失引当金の金額を控除したうえで計上します。
(3) 期ズレ子会社の場合
株式の減損処理における実質価額は、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額をいいますが、算定の基礎とする財務諸表は、決算日までに入手し得る直近のものを使用し、その後の状況で財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していればその事項も加味しなければなりません(金融商品実務指針92項)。例えば、親会社が3月決算で子会社が12月決算の場合、12月の財務諸表を入手することになりますが、3月までに財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していれば、その事項も加味する必要がありますので、留意が必要です。
また、関係会社事業損失引当金は、親会社において発生する引当金の見積りであるため、親会社の決算日時点において将来負担する費用(損失)を合理的に見積る必要があります。よって、親会社の期末時点における子会社の決算状況を何らかの方法で見積り、その時点の債務超過額を基礎として、親会社が将来負担する金額を合理的に見積る必要があります。
一方、連結財務諸表上では、上で述べた株式の評価損も関係会社事業損失引当金等も、戻入処理をすることになりますので、債務超過子会社の場合は、子会社の正規の決算(例えば12月決算の期ズレ子会社の場合は12月決算)を基礎とした債務超過額が計上されることになります。個別財務諸表上で、親会社の決算時点の見積りをしたにもかかわらず、戻し入れすることになりますが、子会社の決算日後、親会社の計算書類に係る監査報告書日までに発生し、連結計算書類に重要な影響を及ぼすと認められる事象が生じている場合、当該事象に関する修正を行う必要がありますので(後発事象取扱い 4.(2)②a.ⅱ2、4.(2)②b(a)1)、連結財務諸表においても、修正後発事象との観点から子会社の決算日後の事象を加味する必要がある点にも留意が必要です。
Q5. 税効果会計-企業の分類((分類4)のいわゆる反証規定)【再掲】
繰延税金資産の回収可能性の判断における企業の分類に関して、(分類4)のいわゆる反証規定を適用する際の留意点を教えてください。
A5.
(1) (分類4)のいわゆる反証規定
回収可能性適用指針29項では、(分類4)から(分類3)として取り扱ういわゆる反証規定の定めがあります。
回収可能性適用指針29項
(分類4)の要件を満たしても、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積る場合、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは(分類3)に該当するものとして取り扱う
(2) 将来の一時差異等加減算前課税所得がマイナスになる年度がある場合のいわゆる反証規定の適用可否
上記(1)のとおり、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときは(分類3)に該当するものとして取り扱います。
この時、(図表2)の(ケース1)のとおり、将来1年目及び2年目は将来の一時差異等加減算前課税所得がプラスですが、3年目はマイナスのケース、また、(ケース2)のとおり、2年目だけマイナスですが、それ以外は5年目までプラスのケースにおいて、それぞれいわゆる反証規定を適用して(分類3)として扱うことができるかが論点となります。なお、マイナスとなる年度は臨時的な要因によるものであることが明らかであるという前提になります。
図表2 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り
|
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
将来の一時差異等加減算前課税所得 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
|
|
ケース1 |
プラス |
プラス |
マイナス |
- |
- |
|
ケース2 |
プラス |
マイナス |
プラス |
プラス |
プラス |
以下の理由から、上記いずれのケースでもいわゆる反証規定を適用することはできないと考えられます。
① 「将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じる」といういわゆる反証規定の要件は、原則とは異なる取扱いを容認するものであることから厳格に捉える必要があると考えられます(※)
② 回収可能性適用指針29項の要件において、臨時的な原因である場合に容認されるような定めとはなっていないことから、(分類2)や(分類3)の要件(臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得)とは異なり、仮に臨時的な原因であったとしても、将来の一時差異等加減算前課税所得がマイナスとなる場合にはいわゆる反証規定の要件を満たしていないと考えられます
※「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』に対するコメント」コメントNo.70参照。
(3) 前期適用したものの、当期実績がマイナスとなった場合、当期において再度いわゆる反証規定を適用することの可否
前期においていわゆる反証規定を適用し、(分類3)としていたものの、当期の一時差異等加減算前課税所得がマイナスとなってしまったとき、合理的な説明が可能であるとして、当期においてもいわゆる反証規定を適用することは可能かどうかが論点となります。
この点、当期における適用は極めて限定的であると考えられ、非常に慎重な検討が必要であると考えられます。
これは、(2)のとおり、いわゆる反証規定は原則とは異なる取扱いを容認するものであることから、その要件は厳格に捉える必要があると考えられるためです。
Q6. 税効果会計-回収可能性の判断手順【再掲】
繰延税金資産の回収可能性の判断手順について、留意点を教えてください。
A6.
(1) 会計処理
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性は、以下の①から③に基づいて、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかを判断することになります(回収可能性適用指針6項)。
① 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得
② タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得
③ 将来加算一時差異
そして、当該回収可能性を判断するにあたっての具体的な手順は(図表3)のとおりです(回収可能性適用指針11項)。
図表3 回収可能性の判断手順
|
① 期末における将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリングを行う |
|
② 期末における将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリングを行う |
|
③ 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを、解消見込年度ごとに相殺する |
|
④ ③で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、解消見込年度を基準として繰戻・繰越期間の将来加算一時差異(③で相殺後)の解消見込額と相殺する |
|
⑤ ①から④により相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額(タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を含む。)と解消見込年度ごとに相殺する |
|
⑥ ⑤で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、解消見込年度を基準として繰戻・繰越期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額(⑤で相殺後)と相殺する |
|
⑦ ①から⑥により相殺し切れなかった将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性はないものとし、繰延税金資産から控除する |
(2) 実務上の留意点
① 将来加算一時差異のスケジューリング
上記のとおり、繰延税金資産の回収可能性の判断手順では、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づく将来減算一時差異の解消見込額との相殺((図表3)⑤)の前段階として、将来加算一時差異のスケジューリングに基づいた解消見込額と、将来減算一時差異の解消見込額とを解消見込年度ごとに相殺((図表3)③)することになります。これは、企業の分類のいかんによらず、将来加算一時差異と相殺可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとするということです。
したがって、例えば、以下の設例のように(分類4)の会社であり、一時差異等加減算前課税所得の見積期間が1年であったとしても、1年を超える期間についても将来加算一時差異と将来減算一時差異が年度ごとに相殺可能である限り、回収可能性があるものと判断され繰延税金資産が計上されることとなります。設例においては、X2年度及びX3年度の将来加算一時差異の解消見込額に基づく相殺額である50ずつに対する繰延税金資産30((50+50)×30%)について回収可能性ありと判断することになる点、ご留意ください。
【設例:前提条件】
X0年度末の関連情報は以下のとおりです
- 将来減算一時差異:540
- 将来加算一時差異:△150
- 企業の分類:(分類4)
- 翌期(X1年度)の一時差異等加減算前課税所得:250
- 法定実効税率:30%
繰延税金資産の回収可能性の判断)
① 将来減算一時差異のスケジューリング
|
X1年度 |
X2年度 |
X3年度 |
|---|---|---|
|
300 |
120 |
120 |
② 将来加算一時差異のスケジューリング
|
X1年度 |
X2年度 |
X3年度 |
|---|---|---|
|
△50 |
△50 |
△50 |
③ 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額との解消見込年度ごとの相殺
|
X1年度 |
X2年度 |
X3年度 |
|
|---|---|---|---|
|
将来減算一時差異 |
300 |
120 |
120 |
|
将来加算一時差異 |
△50 |
△50 |
△50 |
|
相殺可能 |
50 |
50 |
50 |
|
相殺可能 |
250 |
70 |
70 |
④ ③で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額について、解消見込年度を基準として繰戻・繰越期間の将来加算一時差異(③で相殺後)の解消見込額との相殺
該当なし(③で相殺後の将来加算一時差異はゼロであるため)
⑤ ④までで相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額について、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額(タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を含む。)と解消見込年度ごとの相殺
|
X1年度 |
X2年度 |
X3年度 |
|
|---|---|---|---|
|
④までの相殺不能額 |
250 |
70 |
70 |
|
一時差異等加減算前課税所得 |
250 |
- |
- |
|
相殺可能 |
250 |
- |
- |
|
相殺不能 |
0 |
70 |
70 |
⑥ 以降省略
(繰延税金資産計上額)
400(③での相殺可能額150+⑤での相殺可能額250)×30%=120
② 資産除去債務に対応する除去費用(資産)に係る将来加算一時差異のスケジューリング
資産除去債務が新たに認識される際は、資産除去債務(負債)と資産除去債務に対応する除去費用(資産)は同額両建てで計上されることになりますが、それらに係る将来減算一時差異及び将来加算一時差異のスケジューリングは異なるものになることに留意が必要です。
資産除去債務については実際に関連する有形固定資産が除去されるタイミングで負債が取り崩され税務上認容されるため、資産除去債務に係る将来減算一時差異は、除去予定時期にスケジューリングされることになります。
一方で、資産除去債務に対応する除去費用は減価償却を通じて税務上加算調整されるため、その将来加算一時差異については、減価償却期間にわたって減価償却方法に合わせてスケジューリングされることになります((図表4)参照)。
このように両者のスケジューリング期間、方法は異なることになり、資産除去債務に係る将来減算一時差異が、対応する除去費用に係る将来加算一時差異をもって全額回収可能性があると判断されるわけではないと考えられ、両者の慎重なスケジューリングの検討が求められる点にご留意ください。
図表4 会計処理とスケジューリングのイメージ
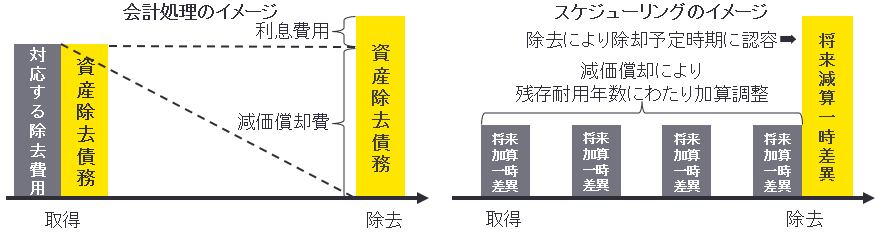
Q7. 退職給付会計
金利が変動する可能性がある場合、退職給付会計において留意すべき事項を教えてください。また、期末近くに早期退職の募集が行われますが、早期割増退職金の見積りへの影響を教えてください。
A7.
(1) 割引率の見直し
退職給付債務の計算における割引率は、期末における安全性の高い債券(国債、政府機関債及び優良社債)の利回りを基礎として決定するため、各年度において割引率を見直す必要があります。割引率の変更については、少なくとも、前期末に用いた割引率により算定した場合の退職給付債務と比較して、期末の割引率により計算した退職給付債務が10%以上変動すると推定されるときに、割引率の変動が退職給付債務に重要な影響を及ぼすものとして期末の割引率を用いて退職給付債務を再計算するという重要性基準を採用することも可能ですが(退職給付適用指針30項)、金利が変動している局面においては、重要性基準を採用している場合、割引率の変更による退職給付債務の再計算の結果、数理計算上の差異が多額に生じる可能性があります。
ここで、数理計算上の差異の費用処理年数は、発生した年度における平均残存勤務期間以内の一定の年数を継続的に適用する必要があり、一度採用した費用処理年数を変更する場合には合理的な変更理由が必要となりますので(退職給付適用指針39項)、退職給付債務の再計算により多額の数理計算上の差異が発生するような状況にあっても、単に金利の変動によって割引率を変更したことのみをもって、数理計算上の差異の費用処理年数を変更する理由とすることはできないと考えられますので留意が必要です(JICPAリサーチ・センター審理情報No.18「退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更について」参照)。
また、割引率の変更に重要性基準を採用する場合は、毎期継続して同様の基準により判断する必要があります。ただし、重要性基準はあくまでも容認規定であることから、容認されている方法である重要性基準から原則的な方法である毎期割引率を見直す方法への変更は、より正確な財務報告を行う変更であるため、合理的なものとして認められると考えられます。当該変更は、会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理の原則及び手続への変更が、会計方針の変更にあたらないとされている考え方に準じて(企業会計基準適用指針第24号第8項(1))、会計方針の変更には該当しないと考えられます。
一方で、毎期割引率を見直す方法から重要性基準を用いる方法に変更することは、原則的な方法から容認される方法への変更であり、より正確な財務報告を行うことに逆行する変更となるため、認められないと考えられます。重要性基準を用いている場合、金利が変動している局面では、退職給付債務の再計算によって将来的に多額の数理計算上の差異が発生することを見越して、変動率が10%以上となっていなくとも早めに割引率を見直すことの可否を検討することがあるかもしれませんが、前述のとおり、10%以上の変動が推定されていないにもかかわらず割引率を変更して退職給付債務を再計算した場合、翌期以降は重要性基準を用いることはできず、毎期割引率を見直す必要があると考えられますので留意が必要です。
(2) 早期割増退職金
組織再編やリストラクチャリングの際に、早期退職の募集が行われて早期割増退職金が支払われることがあります。早期割増退職金は、退職給付見込額の見積りには含めず、従業員が早期退職金制度に応募し、かつ、当該金額が合理的に見積られる時点で費用処理する必要があります(退職給付適用指針10項)。ただし、実務上は後発事象との関係もあり、計上時期が論点となります。決算日をまたいで募集期間が設けられているというようなこともありますので、後発事象との関係を整理したうえで、計上時期を慎重に検討する必要があります。
電子記録移転有価証券表示権利等編
Q8. 電子記録移転有価証券表示権利等に関する取扱い
電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱いについて、その概要及び四半期における開示への影響について教えてください。
A8.
(1) 概要
2022年8月26日に、企業会計基準委員会(ASBJ)から、実務対応報告第43号が公表されており、2024年3月期の期首から原則適用となっています。
(2) 公表の経緯
2019年5月に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)により、金融商品取引法が改正され、いわゆる投資性ICO(Initial Coin Offering(注1))は金融商品取引法の規制対象とされ、各種規定の整備が行われました。
具体的には、これまで流通する蓋然性が低いものとされ、第二項有価証券として分類されてきた金融商品取引法2条2項各号に規定される信託受益権、民法上の任意組合契約に基づく権利、投資事業有限責任組合契約に基づく権利等(以下「集団投資スキーム持分等」という。)について、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合、株式等と同様に事実上流通し得ることを踏まえ、「電子記録移転権利」と定義し、規制が課されています。
また、2020年5月に改正施行された金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)において「電子記録移転権利」よりも広い概念である「電子記録移転有価証券表示権利等」が定められました。これは、集団投資スキーム持分等を含む、金融商品取引法2条2項に規定されるみなし有価証券のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものであり、株式や社債などの有価証券表示権利も、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されるものとして含まれることになりました。
したがって、金融商品取引法上の電子記録移転有価証券表示権利等の分類としては、電子記録移転権利と、トークン化された有価証券表示権利が存在することになります(図表5参照)。
注1 明確な定義はないが、一般に、企業等がトークン(電子的な記録・記号)と呼ばれるものを電子的に発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為の総称するもの(「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書(金融庁2018年12月))
図表5 電子記録移転有価証券表示権利等の権利の内容
|
みなし有価証券の内容 |
権利の主な具体例(※1) |
||
|---|---|---|---|
|
トークン化された有価証券表示権利 |
金融商品取引法2条1項に掲げる有価証券に表示されるべき権利(有価証券表示権利)のうち、当該権利を表示する当該有価証券が発行されていないもの(金融商品取引法2条2項柱書) |
|
|
|
電子記録移転有価証券表示権利等 |
電子記録移転権利 |
金融商品取引法2条2項各号に掲げる権利 |
|
(※1)一部の権利のみ記載している
(※2)金融商品取引法2条2項1号及び2号に該当するものに限る
(※3)金融商品取引法2条2項5号の要件を満たすもの
こうした状況を踏まえ、ASBJにおいて、金商業等府令における「電子記録移転有価証券表示権利等」の発行・保有等に係る会計上の取扱いの検討が行われ、実務対応報告第43号が公表されました。
(3) 範囲
実務対応報告第43号は、「株式会社」が、金商業等府令1条4項17号に規定される「電子記録移転有価証券表示権利等」を発行又は保有する場合の会計処理及び開示を対象としています(実務対応報告第43号2項)。
電子記録移転有価証券表示権利等
金商業等府令1条4項17号に規定される権利をいい、金融商品取引法2条2項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「みなし有価証券」という。)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するもの
(4) 会計処理の基本的な考え方
電子記録移転有価証券表示権利等は、その発行及び保有がいわゆるブロックチェーン技術等を用いて行われる点を除けば、従来のみなし有価証券(電子記録移転有価証券表示権利等に該当しないみなし有価証券を指す。以下同じ。)と権利の内容は同一と考えられるため、実務対応報告第43号では、電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理は、基本的に従来のみなし有価証券を発行及び保有する場合の会計処理((図表6)参照)と同様に取り扱うこととされています。
図表6 みなし有価証券の主な具体例と、金融商品会計基準等における取扱い
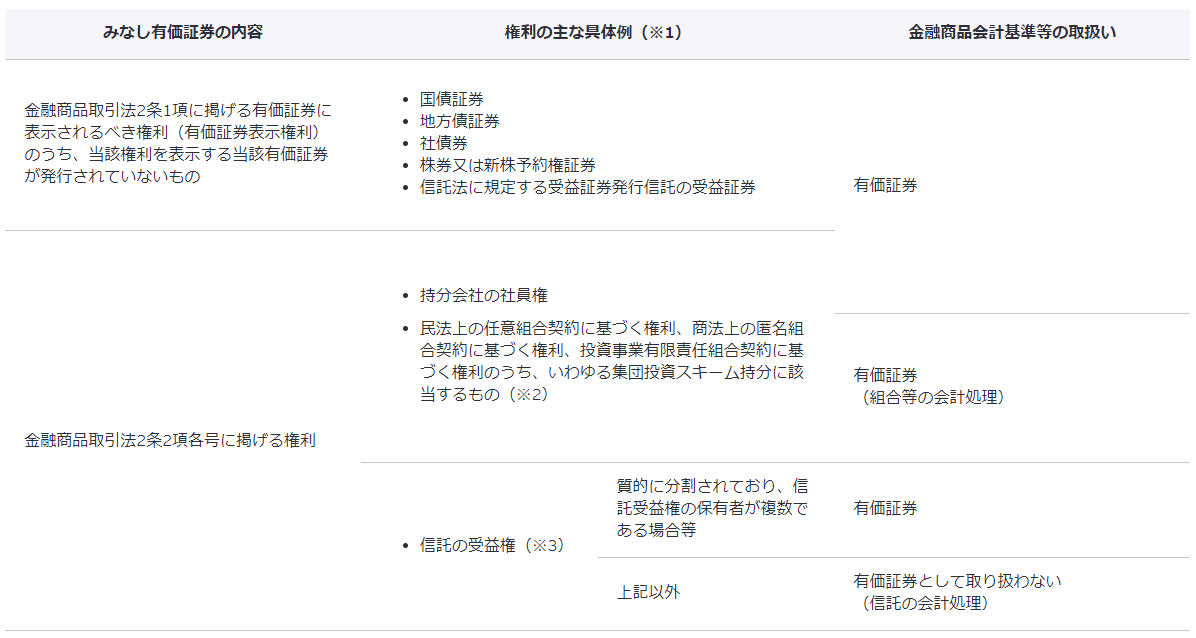
(※1)一部の権利のみ記載している
(※2)金融商品取引法2条2項5号の要件を満たすもの
(※3)金融商品取引法2条2項1号及び2号に該当するものに限る
具体的には、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識については、別途の定めが置かれており、金融商品会計基準が定める原則(金融商品会計基準7項から9項及び金融商品実務指針)に従って行うこととされますが、その売買契約について、契約を締結した時点から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までの期間が短期間である場合に限り、契約を締結した時点において認識することとされています(実務対応報告第43号8項)。
その他、実務対応報告第43号における会計処理及び開示の概要は、(図表7)のとおりです。
図表7 会計処理及び開示の概要
|
金融商品会計基準等上の有価証券に該当する |
金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない(信託の受益権) |
||
|---|---|---|---|
|
発行の会計処理 |
発行の会計処理 |
従来のみなし有価証券を発行する場合と同様 |
実務対応報告第43号の対象外 |
|
保有の会計処理 |
発生及び消滅の認識 |
原則として、金融商品会計基準が定める原則に従う 売買契約について、契約を締結した時点から移転した時点までの期間が短期間である場合、契約を締結した時点に認識する |
原則として、金融商品実務指針及び実務対応報告第23号の定めに従う 金融商品実務指針及び実務対応報告第23号の定めに基づき、結果的に有価証券として又は有価証券に準じて取り扱うこととされているものは、左記の金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識の定めに従う |
|
保有の会計処理 |
B/S価額の算定及び評価差額の会計処理 |
従来のみなし有価証券を保有する場合と同様 |
金融商品実務指針及び実務対応報告第23号の定めに従う |
(5) 開示
電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の表示方法及び注記事項は、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合に求められる表示方法及び注記事項と同様とすることとされています(実務対応報告第43号11項、12項)。このため、電子記録移転有価証券表示権利等は、従来のみなし有価証券に含めて貸借対照表に表示し、金融商品に関する注記事項を開示する場合には、当該注記においても従来のみなし有価証券に含めて注記することになります。
また、電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有しており、この24年3月期から実務対応報告第43号を原則適用する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として注記することになります(企業会計基準第24号10項)。なお、実務対応報告第43号においては、特定の経過的な取扱いが定められていないため、従来から電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになります(実務対応報告第43号13項、企業会計基準第24号6項(1))。
(6) 適用時期
適用時期については、(図表8)のとおり、2023年4月1日以後開始する事業年度の期首から原則適用となります。
図表8 適用時期 |
|
原則適用 |
2023年4月1日以後開始する事業年度の期首から |
|
早期適用 |
実務対応報告第43号の公表日(2022年8月26日)以後終了する事業年度及び四半期会計期間から |
(7) その他
電子記録移転有価証券表示権利等は、今後どのように取引が発展していくかは現時点では予測することが困難であるため、一部の論点については実務対応報告第43号では取り扱わないこととしています(「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」のポイント)。
実務対応報告第43号で取り扱わないこととした論点
① 株式会社以外の信託、持分会社、民法上の任意組合、商法上の匿名組合、投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合における発行及び保有の会計処理
② 株式又は社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合に財又はサービスの提供を受ける権利が付与されるときの会計処理
③ 暗号資産建の電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理
④ 組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の保有の会計処理
Q9. 電子決済手段に関する取扱い
電子決済手段の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱いについて、その概要及び四半期における開示への影響について教えてください。
A9.
(1) 概要
2023年11月17日に、企業会計基準委員会(ASBJ)から、実務対応報告第45号が公表されており、公表日から適用されています。
(2) 公表の経緯
2022年6月に平成21年法律第59号「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)が改正されました。改正された資金決済法においては、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義され、また、これを取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入され、必要な規定の整備が行われました。
こうした状況を踏まえて、ASBJにおいて、資金決済法上の電子決済手段の発行及び保有等に係る会計上の取扱いの検討が行われ、実務対応報告第45号が公表されました。
また、実務対応報告第45号の公表にあわせて、企業会計基準第32号「「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正」及び会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)の改正が行われました。
(3) 範囲
資金決済法2条5項に規定される電子決済手段のうち、1号電子決済手段、2号電子決済手段及び3号電子決済手段を対象とすることとされています。ただし、1号電子決済手段、2号電子決済手段又は3号電子決済手段のうち外国電子決済手段については、電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られるとされています(実務対応報告第45号2項)。
また、実務対応報告第45号2項にかかわらず、3号電子決済手段の発行者側に係る会計処理及び開示に関しては、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」を適用するとされています(実務対応報告第45号3項)。
以下では「電子決済手段」とは、実務対応報告第45号の対象となる特定の電子決済手段をいいます。
(4) 電子決済手段に係る会計処理
① 電子決済手段の保有に係る会計処理(実務対応報告第45号5項から7項及びBC30項)
(i) 電子決済手段の取得時、移転時又は払戻時の会計処理
実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段に係るその取得時、移転時又は払戻時の会計処理は図表9のとおりとされています。
図表9 電子決済手段の取得時、移転時又は払戻時の会計処理
|
電子決済手段の取得時 |
電子決済手段の移転時又は払戻時 |
|
|---|---|---|
|
計上日 |
受渡日 |
受渡日 |
|
計上額 |
当該電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、当該電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理 |
電子決済手段を第三者に移転するときに金銭を受け取り、当該電子決済手段の帳簿価額と金銭の受取額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理 |
(ii) 電子決済手段の期末時の会計処理
実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段は、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とすることとされています。なお、実務対応報告第45号では電子決済手段の換金リスクに関する会計上の取扱いを定めないとされています。
② 電子決済手段の発行に係る会計処理(実務対応報告第45号8項から10項)
(i) 電子決済手段の発行時、払戻時の会計処理
実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段の発行時、払戻時の会計処理は図表10のとおりとされています。
図表10 電子決済手段の発行時、払戻時の会計処理
|
電子決済手段の発行時 |
電子決済手段の払戻時 |
|
|---|---|---|
|
計上日 |
受渡日 |
受渡日 |
|
計上額 |
当該電子決済手段に係る払戻義務について債務額(すなわち券面額に基づく価額)をもって負債として計上し、当該電子決済手段の発行価額の総額と当該債務額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理 |
払戻しに対応する債務額を取り崩す |
(ii) 電子決済手段の期末時の会計処理
実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段に係る払戻義務は、期末時において、債務額をもって貸借対照表価額とすることとされています。
③ 外貨建電子決済手段の期末時の円換算(実務対応報告第45号11項及び12項)
実務対応報告第45号の対象となる外貨建電子決済手段の期末時の円換算は図表11のとおりとされています。
図表11 外貨建電子決済手段の期末時の円換算
|
期末時の円換算 |
|
|---|---|
|
実務対応報告第45号の対象となる外貨建電子決済手段 |
企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」(以下「外貨建取引等会計処理基準」という。)一2 (1) ①の定めに準じて処理を行う。すなわち、決算時の為替相場による円換算額を付する。 |
|
実務対応報告第45号の対象となる外貨建電子決済手段に係る払戻義務 |
外貨建取引等会計処理基準一2 (1) ②の定めに従って処理を行う。すなわち、決算時の為替相場による円換算額を付する。 |
④ 預託電子決済手段に係る取扱い(実務対応報告第45号13項)
電子決済手段等取引業者又はその発行する電子決済手段について電子決済手段等取引業を行う電子決済手段の発行者は、電子決済手段の利用者との合意に基づいて当該利用者から預かった実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段を資産として計上せず、また、当該電子決済手段の利用者に対する返還義務を負債として計上しないこととされています。
(5) 開示(実務対応報告第45号14項及びBC45項)
実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段及び実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段に係る払戻義務に関して、金融商品会計基準40-2項に定める金融商品の状況に関する及び金融商品の時価等に関する事項について注記を行うこととすることとされています。
なお、金融商品の時価等に関する事項を注記するにあたり、実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段については、預金に関する取扱いに準ずることが考えられるとされています。また、実務対応報告第45号の対象となる電子決済手段に係る払戻義務は、金銭債務に関する取扱いに従うことになると考えられるとされています。
(6) キャッシュ・フロー作成基準一部改正及びキャッシュ・フロー実務指針の改正の概要
資金の範囲について、キャッシュ・フロー作成基準一部改正においては、特定の電子決済手段、すなわち、資金決済法2条5項1号から3号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段については、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る。)を現金に含めることとされています(キャッシュ・フロー作成基準一部改正2項及び3項)。また、キャッシュ・フロー実務指針においては、キャッシュ・フロー作成基準一部改正の定めと整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」が追加され、キャッシュ・フロー作成基準一部改正の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告第45号の適用対象となる1号電子決済手段、2号電子決済手段及び3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られるとされています(キャッシュ・フロー実務指針2項(1))。
なお、電子決済手段の貸借対照表上の取り扱いについては、令和6年2月19日 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方において、電子決済手段は、「実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」BC18項において、「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるものの「現金又は預金そのものではない」とされていることから、財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれないこととなります。したがって、電子決済手段については、財務諸表等規則第17条第1項第12号に規定する「その他」に区分されることとなります。なお、財務諸表等規則第19条に基づき、重要性が認められる場合には、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記する必要があります。」との金融庁の考え方が示されています。
また、電子決済手段はキャッシュ・フロー計算書及び貸借対照表において上述のように取り扱われることとなるため、電子決済手段を保有している場合には連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲の注記、貸借対照表との科目の関係の注記についても留意してください。
パーシャルスピンオフ編
Q10. いわゆるパーシャルスピンオフ税制の概要
いわゆるパーシャルスピンオフ税制の概要について教えてください。
A10.
(1) いわゆるパーシャルスピンオフ税制の概要
令和5年度税制改正において、完全子会社株式に関して一部の持分を残す株式分配のうち、当該一部の持分が当該完全子会社の株式の発行済株式総数の20%未満となる株式分配((図表12)参照)について、一定の要件を満たす場合には、課税の対象外とされる特例措置が設けられました。これが、いわゆるパーシャルスピンオフ税制と呼ばれています。
図表12 イメージ図
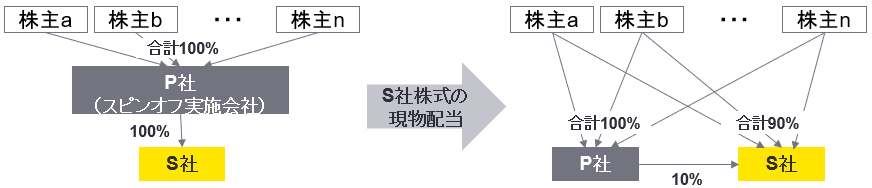
(出典:経済産業省 産業組織課「『スピンオフ』の活用に関する手引(令和4年9月)」www.meti.go.jp/press/2022/09/20220916005/20220916005-1.pdf〈2024年2月20日アクセス〉)
(2) 設定の経緯
令和5年度税制改正以前のスピンオフ(企業が特定事業を切り出して独立会社とする組織再編行為)に関する税制においては、スピンオフ実施会社に持分の一部を残す場合には、適格組織再編に該当しないこととされていました。しかしながら、内閣官房より公表された「スタートアップ育成5か年計画」では、大企業が有する経営資源(人材、技術等)の潜在能力の発揮や大企業発のスタートアップ創出の観点から、スピンオフの促進が重要であることが示され、このために、スピンオフを行う企業に持分を一部残す場合についても課税の対象外とすることが示されました。これを受けて、令和5年度税制改正により、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が設けられました。
(3) 適用要件
完全子会社株式に関して一部の持分を残す株式分配について、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が適用されるためには、基本的に、(図表13)に示す要件を満たす必要があります。
図表13 適格組織再編に該当するための要件(概要)
|
要件 |
内容 |
|
|---|---|---|
|
① |
非支配要件 |
現物分配法人が株式分配の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ、株式分配に係る完全子法人が株式分配後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと |
|
② |
株式のみ 按分交付要件 |
産業競争力強化法に基づく認定を受けた事業再編計画に従って行われる、同法に基づく特定剰余金の配当であって、完全子法人株式の100分の80超が移転し、かつ、現物分配法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみが交付されること |
|
③ |
従業者継続要件 |
おおむね100分の90以上の従業者が完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれること |
|
④ |
事業継続要件 |
完全子法人の主要な事業が完全子法人において、株式分配後も引き続き行われることが見込まれること |
|
⑤ |
役員継続要件 |
完全子法人の特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと |
|
⑥ |
事業再編計画 認定要件 (令和6年度税制改正大綱により要件の追加が提案されています) |
2023年4月1日から2024年3月31日までの間(令和6年度税制改正大綱により延長が提案されています)に、特定剰余金配当に係る関係事業者等(完全子法人)が、経済産業大臣の定める以下の要件を満たし、事業の成長発展が見込まれるものとして、事業再編計画の認定を受けていること。 (上記期間内に認定を受ければスピンオフ実施が期間後であっても課税の特例は適用される) <経済産業大臣が定める要件>
<事業再編の実施に関する指針四へ> 以下イ~ハのいずれかの要件を満たしていることが確認できること イ:インセンティブ構造
ロ:新規事業性
ハ:事業の成長可能性
|
出典:経済産業省 産業組織課「『スピンオフ』の活用に関する手引(令和4年9月)」www.meti.go.jp/press/2022/09/20220916005/20220916005-1.pdf〈2024年2月20日アクセス〉)
なお、令和5年度税制改正では、いわゆるパーシャルスピンオフ税制を適用するためには2023年4月1日から2024年3月31日までの間に認定を受ける必要がありましたが、2024年3月28日に国会で成立した令和6年度税制改正法において、当該認定を受ける期間を2028年3月31日までとすること、つまり適用期限を4年延長することとされています。また、令和6年度税制改正の大綱では、以下の見直しも提案されています。
① 認定事業再編計画の公表時期について、現行では認定の日とされているところを、認定の日から認定事業再編計画に記載された事業再編の実施時期の開始の日までとすること
② 認定株式分配に係る完全子法人が主要な事業として新たな事業活動を行っていることを要件として追加すること
Q11. 完全子会社株式に関して一部の持分を残す株式の現物配当の会計処理
完全子会社株式に関して一部の持分を残す株式の現物配当の会計処理について教えてください。
A11.
(1) いわゆるパーシャルスピンオフ税制に対応した会計基準等の改正
いわゆるパーシャルスピンオフ税制に対応して、ASBJにより、自己株式等会計適用指針及び税効果会計適用指針が改正されました。また、日本公認会計士協会(以下「JICPA」という。)により、資本連結実務指針が改正されました。
これらの会計基準等の改正は、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が時限的なものであり、早期に基準開発を完了すべきとの理由から、発生する可能性の高い取引((図表14)の「対象」)に対象が限定されています。
図表14 会計基準等の改正に係る対象取引 |
|
分配後において子会社株式に該当するか |
分配後において子会社株式に該当するか |
||
|
該当しない(*1) |
該当する |
||
|
分配対象株式は完全子会社株式であるか |
完全子会社株式 |
対象 |
|
|
分配対象株式は完全子会社株式であるか |
上記以外の子会社株式 |
対象外 |
対象外 |
(*1) いわゆるパーシャルスピンオフ税制において税制適格となるかどうかには関わらない。また、支配を喪失して関連会社になった場合も含まれる
(2) 個別財務諸表上の会計処理
スピンオフ実施会社の個別財務諸表上、保有する完全子会社株式の一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社株式に該当しなくなった場合、配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもってその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額します(自己株式等会計適用指針10項)。
【設例:前提条件】
① 期末において、100%子会社であるS社の株式(帳簿価額1,000、時価1,400)のうち90%をその他資本剰余金から配当した結果、S社株式はその他有価証券となった。
(株式の現物配当の処理)
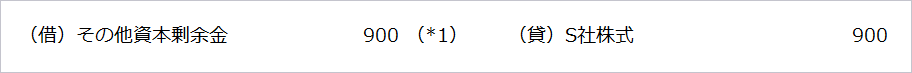
(*1) 配当の効力発生日における配当されるS社株式の適正な帳簿価額
(S社株式の振り替え)
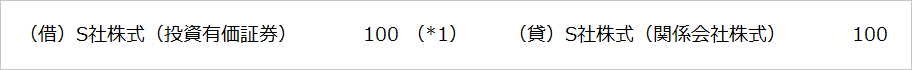
(*1) 配当後のS社株式の適正な帳簿価額
(3) 連結財務諸表上の会計処理
保有する完全子会社株式のすべて又は一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社に該当しなくなった場合について、連結財務諸表上も、個別財務諸表と同様に、配当財産の時価で配当したとはせず、現物配当に係る損益は計上しないように会計処理することになります。
具体的には、連結財務諸表に計上した取得後利益剰余金及びその他の包括利益累計額並びにのれん償却累計額の合計額等(以下「投資の修正額」という。)について、個別財務諸表の取得価額に含まれている付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金とこれ以外の部分とに分けて(図表15)のように処理します(資本連結実務指針第46-3項、第46-4項)。
図表15 投資の修正額の処理
|
個別財務諸表の取得価額に含まれている付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金 |
左記以外の部分 |
|---|---|
|
配当前の投資の修正額とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額について、配当により個別財務諸表で計上したその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の減額を修正する。 |
配当前の投資の修正額とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額について、連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に子会社株式の配当に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上する(*1) |
(*1) この処理により減少するその他の包括利益累計額は当期純利益を構成するものではないため、組替調整の対象とはならない。
なお、配当後の残存投資は、子会社株式の一部売却の処理に準じて処理します(資本連結実務指針第46-3項また書き、第46-4項また書き)。
【設例:前提条件】
① 期末において、100%子会社であるS社の株式(帳簿価額1,000、時価1,400)のうち90%をその他資本剰余金から配当した結果、S社株式はその他有価証券となった。
② 連結財務諸表上、配当前の投資の修正額は300であり、その内訳は以下のとおりである。
ⅰ追加投資時の投資差額(連結財務諸表上は資本剰余金):210
ⅱ取得関連費用(連結財務諸表上は利益剰余金):△70
ⅲ取得後利益剰余金:160(うち、当期純利益は30)
③ 連結財務諸表上、配当後の投資の修正額は30である。
(配当前持分の評価)
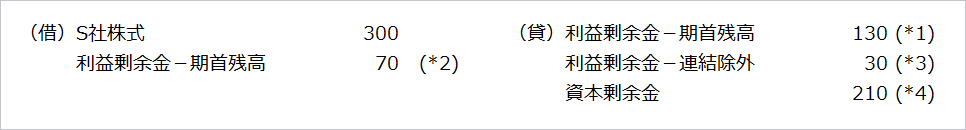
(*1) 取得後利益剰余金のうち前期末までの額(【設例:前提条件】②ⅲ)
(*2) 個別財務諸表上は取得価額に含まれているが連結財務諸表上は費用処理されている取得関連費用(【設例:前提条件】②ⅱ)
(*3) 取得後利益剰余金のうち当期純利益の額(【設例:前提条件】②ⅲ)
(*4) 追加投資時の投資差額(【設例:前提条件】②ⅰ)
(配当の修正及び株式配当による利益剰余金の減額)
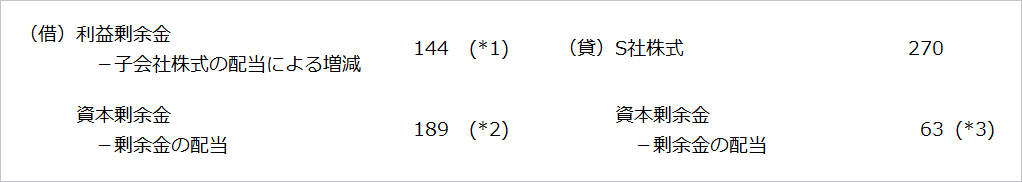
(*1) 取得後利益剰余金160-160×残存持分比率10%
(*2) 追加投資時の投資差額210-210×残存持分比率10%
(*3) 連結財務諸表上費用処理されている取得関連費用△70-△70×残存持分比率10%
(帳簿価額への修正)
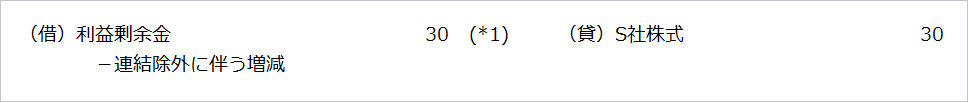
(*1) 配当後の投資の修正額30(【設例:前提条件】③)
(4) 連結財務諸表上の税効果会計
投資の修正額などの連結財務諸表固有の一時差異のうち、パーシャルスピンオフにより解消する部分については、パーシャルスピンオフでは個別財務諸表及び連結財務諸表のいずれにおいても現物配当に係る損益は計上されないことから、税効果適用指針における連結財務諸表固有の一時差異に直接的には該当しない((図表16)の定義に当てはまらない)と考えられると指摘されていました(税効果会計適用指針第124-2項)。
図表16 連結財務諸表固有の一時差異の定義
|
連結財務諸表固有の将来減算一時差異 |
連結財務諸表固有の将来加算一時差異 |
|---|---|
|
連結決算手続の結果として連結貸借対照表上の資産の金額(又は負債の金額)が、連結会社の個別貸借対照表上の資産の金額(又は負債の金額)を・・・ |
連結決算手続の結果として連結貸借対照表上の資産の金額(又は負債の金額)が、連結会社の個別貸借対照表上の資産の金額(又は負債の金額)を・・・ |
|
下回る(又は上回る)場合に、当該連結貸借対照表上の資産(又は負債)が回収(又は決済)される等により、当該一時差異が解消する時に、連結財務諸表における利益が減額されることによって当該減額後の利益の額が当該連結会社の個別財務諸表における利益の額と一致する関係を持つもの |
上回る(又は下回る)場合に、当該連結貸借対照表上の資産(又は負債)が回収(又は決済)される等により、当該一時差異が解消する時に、連結財務諸表における利益が増額されることによって当該増額後の利益の額が当該連結会社の個別財務諸表における利益の額と一致する関係を持つもの |
しかしながら、パーシャルスピンオフにより解消する一時差異についても税効果適用指針の定めを適用することが適切と考えられるため、連結財務諸表固有の将来減算一時差異又は将来加算一時差異に準ずるものとして取り扱うこととされました(税効果会計適用指針第4項(5)なお書き)。
具体的には、上記【設例:前提条件】②において、配当前の投資の修正額300は、パーシャルスピンオフにより解消する際に損益が計上されないため、上表の定義には直接的には該当しないことになりますが、連結財務諸表固有の将来加算一時差異に準ずるものとして取り扱われます。したがって、子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来加算一時差異に係る認識要件を満たす場合には、当該一時差異について繰延税金負債を計上します。
改正法人税等会計基準編
Q12. 改正法人税等会計基準の概要及び適用時期【再掲】
法人税等会計基準等の改正について、その概要と適用時期を教えてください。
A12.
(1) 概要
2022年10月28日に、企業会計基準委員会(ASBJ)から(図表17)記載の会計基準等の改正が公表され、また、同日に日本公認会計士協会(JICPA)から同表記載の実務指針等の改正が公表されています。
図表17 改正された会計基準・実務指針等
|
公表主体 |
改正会計基準等の名称 |
|---|---|
|
ASBJ |
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」 |
|
ASBJ |
企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」 |
|
ASBJ |
企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 |
|
JICPA |
会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 |
|
JICPA |
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 |
|
JICPA |
会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」 |
|
JICPA |
会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」 |
|
JICPA |
「金融商品会計に関するQ&A」 |
(2) 公表の経緯
ASBJより、2018年2月に企業会計基準第28号等を公表し、JICPAにおける税効果会計に関する実務指針のASBJへの移管を完了しましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととしていました。
① 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
② グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
ASBJでは、移管の完了後、まず上記①について審議を開始しましたが、2020年度の税制改正においてグループ通算制度が創設されたことに伴い、グループ通算制度を適用する場合の取扱いについての検討を優先していました。その後、2021年8月に実務対応報告第42号を公表した後に、審議が再開され、公表に至ったものです。
(3) 主な改正点
主な改正点は以下の2点です。詳細な内容はそれぞれのQ&Aをご確認ください。
① 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税) (Q13参照)
② グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果 (Q14参照)
(4) 適用時期
適用時期については、(図表18)のとおり、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となります。なお、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用が可能ですが、早期適用する場合には、上記2つの改正点のいずれも同時に適用しなければならないと考えられます。
図表18 適用時期 |
|
原則適用 |
2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から |
|
早期適用 |
2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から |
Q13. 税金費用の計上区分【再掲】
今回の改正によって、税金費用の計上区分がどのように変わるのか、教えてください。
A13.
(1) 現行の会計処理の問題点
当事業年度の所得等に対する税金費用について、現行の会計処理では以下のとおりとなっていました。
現行の会計処理
当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)については、法令に従い算定した額を損益に計上する(改正前法人税等会計基準5項)
上記現行の会計処理によれば、課税所得の発生原因となった取引がどのようなものであろうと、課税所得に対して発生した法人税等は全て損益計算書において損益として計上されることになります。
ここで、その他の包括利益に計上された取引又は事象(以下「取引等」という。)が課税所得計算上の益金又は損金に算入され、法人税等が課せられるケースがあります。この場合には、対象となる取引等についてはその他の包括利益に計上されることになりますが、一方で、当該取引等に対して課せられる法人税等は損益に計上されることとなります。
このような場合には、「税引前当期純利益」と「税金費用」の対応関係が図られないことになり、この点が問題視されていました。
この点について、以下の設例を用いて説明します。
【設例:前提条件】
① A社(3月決算)は、取得原価が10,000の「その他有価証券」を保有しており、X1年3月期の期末において、その他有価証券の時価は、12,000であった。
② X1年4月1日にA社はグループ通算制度に加入することが決定しており、X1年3月期の期末において、当該「その他有価証券」に対して、税務上、時価評価が行われる。このため、「その他有価証券評価差額金」2,000は、X1年3月期において課税所得に含まれ課税される。
③ A社は、当該「その他有価証券評価差額金」を除いても課税所得が4,000生じている。
④ X1年3月期の期末における法定実効税率は30%であった。
⑤ その他の将来減算一時差異及び将来加算一時差異は存在しない。
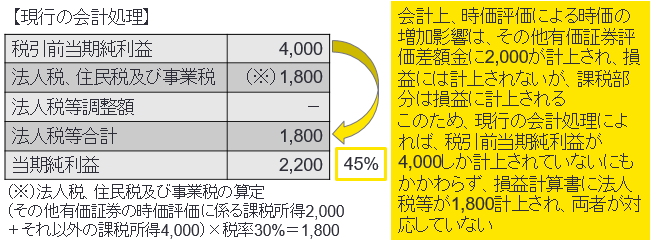
(仕訳)

(2) 改正後の会計処理
改正後の会計処理の概要は以下のとおりです。
① 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、「損益」、「株主資本」及び「その他の包括利益」(又は「評価・換算差額等」)に区分して計上する(法人税等会計基準5項、5-2項)
② 株主資本又はその他の包括利益に計上した金額に、課税の対象となる企業の対象期間における法定実効税率を乗じて算定する(法人税等会計基準5-4項)
まず1点目の発生源泉となる取引等に応じて3つの区分に分けて計上することとした理由は、この考え方を採用した場合、税引前当期純利益と所得に対する法人税等の間の税負担の対応関係が図られる点、また、税効果額については、税効果適用指針において、この考え方と同様に取り扱っている点、加えて、国際的な会計基準においても、この考え方と同様に処理されている点を踏まえたものです。
また、2点目の法定実効税率を乗じて算定するとした理由は、複雑な計算を伴う場合の実務への配慮です。なお、課税所得が生じていないことなどから法令に従い算定した額がゼロとなる場合に、株主資本又はその他の包括利益の区分に計上する法人税等についてもゼロとするなど、他の合理的な計算方法により算定することができるとされています(法人税等会計基準5-4項ただし書き)。
改正後の会計処理について、上記(1)の設例と同様の前提である場合には以下のとおりとなります。
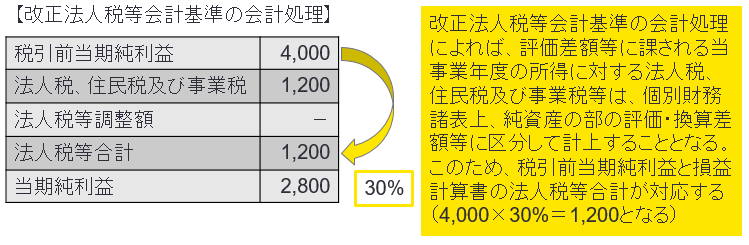
(仕訳)

(3) 株主資本等又はその他の包括利益に計上される取引等の例示
株主資本等又はその他の包括利益に計上される取引等の例示は(図表19)のとおりです。
なお、その他の包括利益の欄の1番下の「退職給付会計における未認識項目」に関して、以下の点にご留意ください。
連結財務諸表においては、「退職給付会計における未認識項目」については、その他の包括利益を通してその他の包括利益累計額に計上されることになります。ここで、税務上は年金制度であれば掛金拠出額が損金算入されます。一方、会計上は、退職給付引当金は損益を通して計上された部分と、その他の包括利益を通して計上された未認識項目部分とで構成されているため、掛金拠出額に係る当期税金費用も、損益とその他の包括利益とで区分する必要があります。しかし、損益及びその他の包括利益と税金費用との対応関係が一概に決定できず、区分して算定することは困難であると考えられます。したがって、損益とその他の包括利益に区分して算定することが困難な場合に該当するため、損益に計上することが認められています(法人税等会計基準5-3項(2)、29-6項、29-7項)。
図表19 株主資本等又はその他の包括利益に計上される取引等の例示
|
区分 |
分類 |
内容 |
|
|---|---|---|---|
|
株主資本 |
|
子会社等が保有する親会社株式等を企業集団外部の第三者に売却した場合の連結財務諸表における法人税等に関する取扱い |
|
|
株主資本 |
親会社株式等の売却 |
子会社等が保有する親会社株式等を当該親会社等に売却した場合の連結財務諸表における法人税等に関する取扱い |
|
|
株主資本 |
子会社に対する投資の売却 |
子会社に対する投資を一部売却した後も親会社と子会社の支配関係が継続しており、連結財務諸表上、当該売却に伴い生じた親会社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する場合の当該資本剰余金部分に対応する法人税等相当額についての取扱い |
|
|
株主資本 |
子会社に対する投資の売却 |
子会社に対する投資について追加取得に伴い生じた親会社の追加取得持分と追加投資額との差額を資本剰余金として計上し、その後に子会社に対する投資を売却した場合における当該資本剰余金に対応する法人税等相当額についての取扱い |
|
|
その他の包括利益 |
グループ通算制度(又は連結納税制度)の加入時の時価評価 |
グループ通算制度(又は連結納税制度)の開始時又は加入時に、会計上、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額が計上されている資産又は負債(例えば、その他有価証券)に対して、税務上、時価評価が行われ、課税所得計算に含まれる場合 |
|
|
その他の包括利益 |
非適格組織再編成における時価評価 |
非適格組織再編成において、会計上、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額が計上されている資産又は負債(例えば、その他有価証券)に対して、税務上、時価評価が行われ、課税所得計算に含まれる場合 |
|
|
その他の包括利益 |
在外子会社持分へのヘッジ会計 |
投資をしている在外子会社の持分に対してヘッジ会計を適用している場合などにおいて、税務上は当該ヘッジ会計が認められず、課税される場合 |
|
|
その他の包括利益 |
退職給付会計における未認識項目 |
確定給付制度を採用しており、連結財務諸表上、未認識数理計算上の差異等をその他の包括利益累計額として計上している場合において、確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金等の額が、税務上、支出の時点で損金の額に算入される場合 |
|
Q14. グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果【再掲】
今回の改正によって、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の会計処理がどのように変わるのか、教えてください。
A14.
(1) 税務上の取扱い
内国法人が有する譲渡損益調整資産を他の完全支配関係がある内国法人に譲渡した場合には、グループ法人税制が適用され、課税所得計算上、譲渡時点において売却損益を計上せず、繰り延べられることとされています。
当該繰り延べられた売却損益については、譲受法人において、当該資産の譲渡等の事由が生じたとき(完全支配関係がある他の法人に対する譲渡も含まれる。)に、譲渡法人の課税所得計算上、売却損益を益金の額又は損金の額に算入することとされています(法人税法61条の11)。
(2) 現行の会計処理の問題点
子会社株式等を連結会社間で売却し、グループ法人税制が適用され、税務上売却損益が繰り延べられる場合について、改正前の税効果の取扱いは以下のようになっていました。
① 個別財務諸表上の取扱い
連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合、当該子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表における当該売却損益に係る一時差異について、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する(改正前税効果適用指針17項)
② 連結財務諸表上の取扱い(改正前税効果適用指針39項)
(i) 売却元企業の個別財務諸表において子会社株式等の売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額は修正しない。
(ii) 連結会社間における子会社株式等の売却の意思決定等に伴い、既に子会社等に対する投資に関連する連結財務諸表固有の一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上している場合は、当該繰延税金資産又は繰延税金負債のうち、当該売却により解消される一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を売却時に取り崩す。
(iii) 当該子会社株式等の売却に伴い、追加的に又は新たに生じる一時差異については、子会社等に対する投資に係る一時差異として、税効果適用指針22項又は23項に従って処理する。
上記の会計処理によれば、グループ法人税制が適用される連結会社間の子会社株式等の売却について、内部取引であることから連結財務諸表上は売却損益が消去され、税務上も売却損益が繰り延べられるため課税されていないにもかかわらず、連結損益計算書上、税金費用(法人税等調整額)が計上される結果となります。このため、現行の取扱いは、連結決算手続上、消去される取引に対して税金費用を計上するものであり、税引前当期純利益と税金費用が必ずしも適切に対応していないとの声が聞かれていました。
この点について、以下の設例を用いて説明します。
【設例:前提条件】
① P社は、S1社及びS2社の株式の100%を保有し子会社としている。なお、3社はいずれも3月決算の内国法人である。なお、P社連結グループは、グループ通算制度は適用していない。
② X1年3月末時点のS2社株式の税務上の簿価及び個別財務諸表上の簿価は、2,000である。また、S2社に対する投資の連結財務諸表上の簿価は2,500である。
③ P社はS1社に対して、S2社株式を時価3,500で売却する意思決定をX1年3月末に行った。なお、P社は連結財務諸表上、従前、配当による課税関係が生じないこと及び売却する意思がなかったことから、X1年3月末以前においては、子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来加算一時差異に対して繰延税金負債を計上していなかった。
④ X1年4月にS2社株式の売却に係る取引が実行された。なお、S1社はS2社株式を売却する意思はない。
⑤ 法定実効税率は30%とする。
⑥ X2年3月期において、P社連結上、税金等調整前当期純利益が10,000生じており、当該利益に対応する法人税、住民税及び事業税が3,000生じている。また、上記前提条件に関連するものを除いて、将来減算一時差異及び将来加算一時差異は存在しない。
※ 以降の図中にある用語はそれぞれ以下の意味で使用している。
税務簿価:S2社株式の税務上の帳簿価額
会計簿価:S2社株式の個別財務諸表上の帳簿価額
連結簿価:S2社に対する投資の連結貸借対照表上の価額
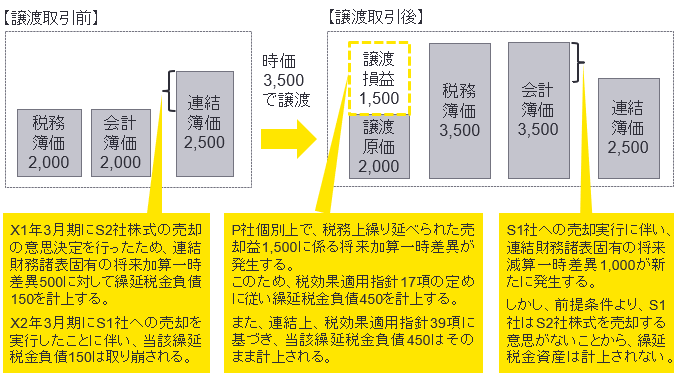
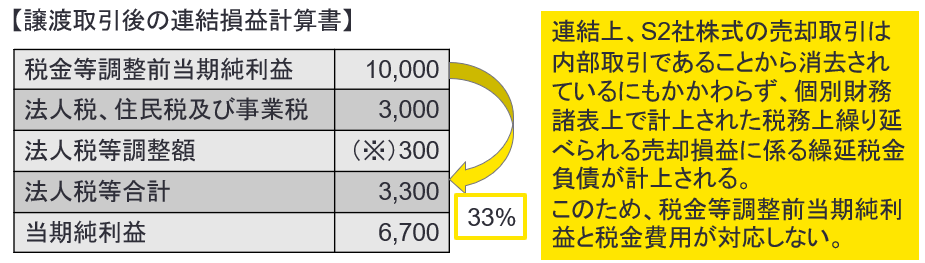
(※)法人税等調整額の算定
① 税務上繰り延べられた売却損益に係る将来加算一時差異に対する繰延税金負債の計上
⇒税務上繰り延べられた売却益1,500×税率30%=450
② X1年3月期の売却の意思決定時に計上されたS2社への投資に係る連結財務諸表固有の将来加算一時差異に対する繰延税金負債の取崩し
⇒連結財務諸表固有の将来加算一時差異500×税率30%=150
①-②=300
(3) 改正後の会計処理
改正後の税効果の取扱いは以下のようになっています。
① 個別財務諸表上の取扱い
改正前と同様(注2)に、当該子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表における当該売却損益に係る一時差異について、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する(税効果適用指針17項)
② 連結財務諸表上の取扱い(税効果適用指針22項(1)①、23項(2)②、39項、持分法実務指針27項、29項、30項)
(i) 子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す。
(ii) 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等、法人税法61条の11に規定されている、課税所得計算上、繰り延べられた損益を計上することとなる事由についての意思決定がなされた時点において、当該取崩額を戻し入れる。
(iii) 子会社等に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式等の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない。
注2 今回の改正において、個別財務諸表上の会計処理は、以下の理由から見直されていない。
- 子会社株式等の売却により将来加算一時差異が生じているにもかかわらず繰延税金負債を計上しない取扱いは、一部の場合を除き、一律に繰延税金負債を計上する税効果適用指針の取扱いに対する例外的な取扱いとなるため、その適用範囲は限定することが考えられる
- 個別財務諸表においては、連結財務諸表とは異なり、売却損益が消去されないことから、税金費用を計上しないこととした場合には、税引前当期純利益と税金費用との対応関係が図られないこととなると考えられる
上記(2)の設例の前提条件に基づき、改正後の税効果の取扱いがどのようになるか、以下に示します。
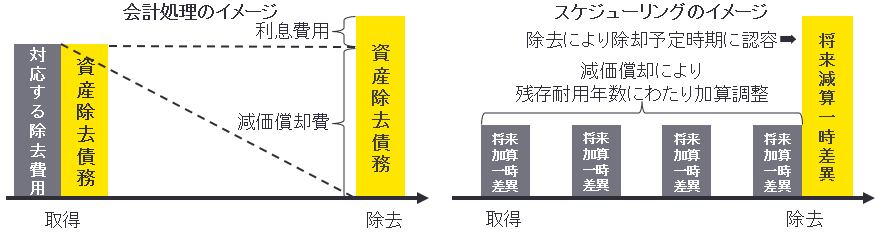
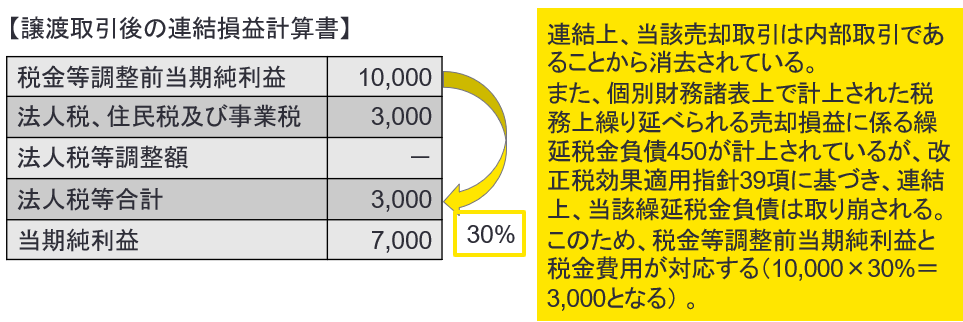
Q15. 経過措置【再掲】
法人税等会計基準等の改正における経過措置を教えてください。
A15.
(1) 経過措置
① 税金費用の計上区分
税金費用の計上区分に関しては、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができるとする経過措置が定められています(法人税等会計基準20-3項ただし書き、税効果適用指針65-2項(2)ただし書き)。
② グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果に関しては、経過措置は定められていません(すなわち、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。)。これは、対象となる取引は、売却元企業の税務申告書に譲渡損益調整勘定等として記載されているため、過去の期間における対象取引の把握は可能と考えられること、また、会計処理については、購入側の企業における再売却等についての意思の有無により判断することになるが、この点も、過去の連結財務諸表における子会社等に対する投資に係る一時差異への税効果会計の適用において一定の判断がなされていたと考えられることから、遡及適用が困難となる可能性は低いと考えられたためです(税効果適用指針163項(2))。
インボイス制度編
Q16. インボイス制度の概要【再掲】
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の概要を教えてください。
A16.
2019年の消費税法改正によって、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となって以降は、軽減税率の対象品目の売上・仕入を区分して請求書を発行したり帳簿に記帳したりする「区分経理」が求められるようになり、仕入税額控除の適用を受けるためには区分経理に対応した帳簿や区分記載請求書等の保存が必須となっていました(区分記載請求書等保存方式)。
2023年10月1日より、「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度の下では、仕入税額控除の要件として、原則、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要になります。(図表20)のとおり、適格請求書には、現行の区分記載請求書の記載事項を基として、赤字の項目を追加することが義務づけられています。
図表20 区分記載請求書及び適格請求書の記載事項
|
区分記載請求書の記載事項 |
適格請求書の記載事項 |
|
|---|---|---|
|
① 請求書発行者の氏名又は名称 |
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
|
|
② 取引年月日 |
|
|
|
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
|
|
④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額 |
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 |
|
|
⑤ 請求書受領者の氏名又は名称 |
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 |
|
|
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
||
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」に基づき筆者が作成)
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入については、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができないことになります。
ただし、インボイス制度導入から6年間(2023年10月1日から2029年9月30日まで)は、一定の要件の下で、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(最初の3年間は80%、次の3年間は50%)を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられています。
Q17. インボイス制度において仕入税額控除を行うことができない消費税相当額の会計処理【再掲】
インボイス制度において仕入税額控除を行うことができない適格請求書発行事業者以外の者からの仕入の場合でも、会計上、支払対価の額に110分の10を乗じて算出した金額を「仮払消費税等」として区分して計上すべきかどうか教えてください。
A17.
(1) 税務上の取扱い
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入については、仕入税額控除の適用を受けることができないため、税務上は仮払消費税等の額がない(すなわち、取引の対価の額に含める。)こととなります(国税庁「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)」(以下「国税庁Q&A」という。)問1参照)。
なお、国税庁Q&Aの「Ⅲ 会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上した場合の法人税の取扱い」では、「法人の会計においては、消費税等の影響を損益計算から排除する目的(中略)などの理由で、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについてインボイス制度導入前と同様に(中略)仮払消費税等の額として経理することも考えられます。」とした上で、会計上で仮払消費税等の額として経理した場合の具体的な税務調整の例が示されています。
(2) 会計上の取扱い
消費税中間報告では、控除対象外消費税等に関する会計処理が定められています。しかし、控除対象外消費税等と「インボイス制度において仕入税額控除を行うことができない適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税等」(以下「インボイス制度下の控除不可消費税相当額」という。)では、税務上の位置付けが異なるため、インボイス制度下の控除不可消費税相当額に関する会計処理については、現行の会計基準等において明示されていないと考えられます。
このため、以下のとおり、インボイス制度下の控除不可消費税相当額について、「仮払消費税等」として区分して計上する処理(パターン1)と、「仮払消費税等」として区分せずに取引の対価の額に含める(資産の取得原価とする又は発生した経費等に含める)処理(パターン2)の、いずれの処理も認められると考えられます。
なお、インボイス制度下の控除不可消費税相当額に関する会計処理方法については、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に該当するため、重要性に応じて会計方針として開示することが考えられます。
<仮払消費税等」として区分して計上する処理(パターン1)の仕訳例>
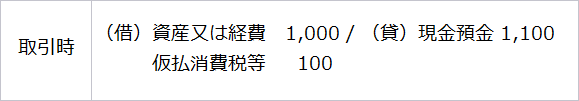
<「仮払消費税等」として区分せずに取引の対価の額に含める(資産の取得原価とする又は発生した経費等に含める)処理(パターン2)の仕訳例>
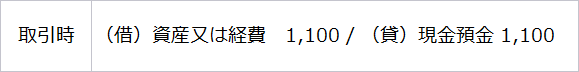
Q18. インボイス制度下の控除不可消費税相当額を仮払消費税として区分して計上する場合の会計処理【再掲】
Q17においてパターン1の会計処理(「仮払消費税等」として区分して計上する処理)を採用した場合、区分計上された仮払消費税等をどのように会計処理すべきか教えてください。
A18.
インボイス制度下の控除不可消費税相当額について、Q17のパターン1の会計処理(「仮払消費税等」として区分して計上する処理)を採用した場合に、区分計上された仮払消費税等をどのように会計処理すべきかに関しては、以下のとおり、複数の考え方があり得ると考えられます。
(考え方1)消費税中間報告で示されている会計処理(「資産の取得原価に算入する処理」又は「発生事業年度の期間費用とする処理」)のいずれかを選択適用する考え方
(考え方2)控除対象外消費税等について採用している会計方針をインボイス制度下の控除不可消費税相当額にも適用する考え方
(考え方3)インボイス制度下の控除不可消費税相当額は発生事業年度の期間費用として処理する考え方
<「資産の取得原価に算入する処理」の仕訳例>
・棚卸資産の取得の場合
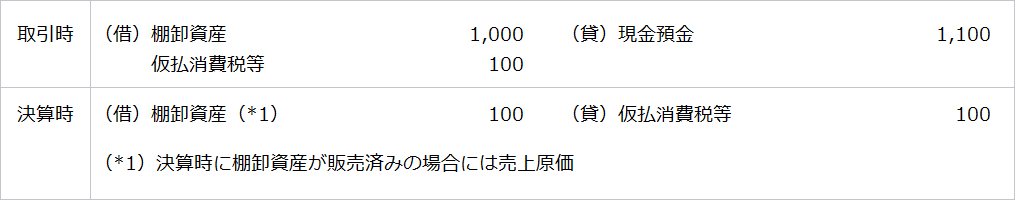
・固定資産の取得の場合
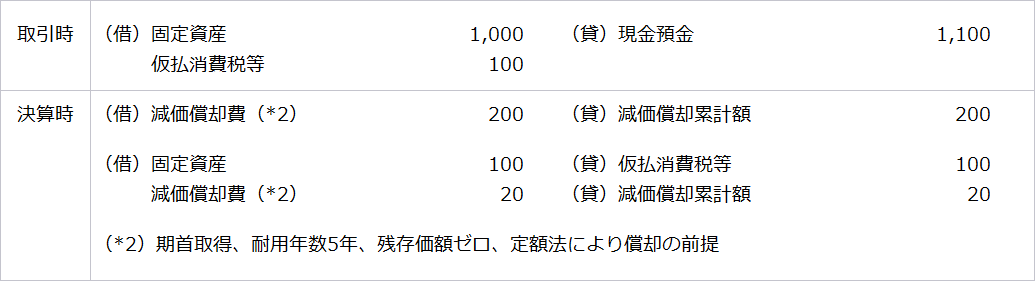
<「発生事業年度の期間費用とする処理」の仕訳例>
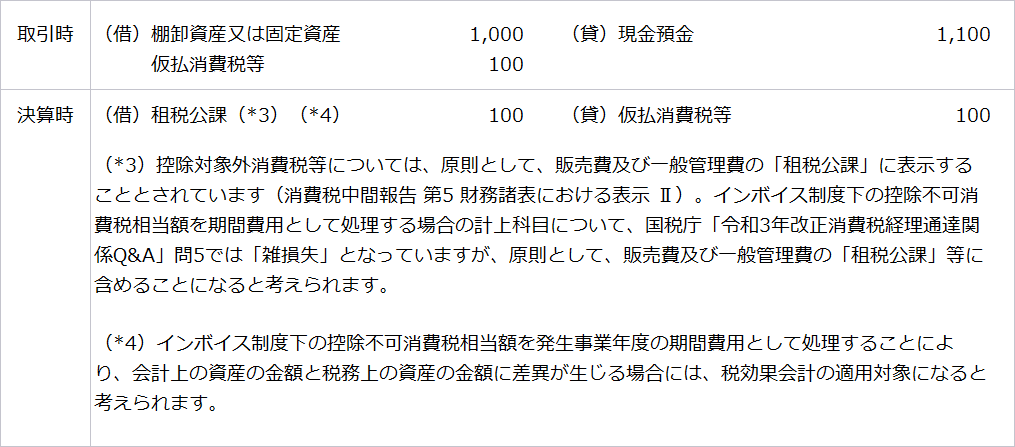
Q19. グローバル・ミニマム課税制度の概要【再掲・一部更新】
グローバル・ミニマム課税制度の概要を教えてください。
A19.
経済協力開発機構(OECD)は、かねてより、近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化により生じた多国籍企業の活動実態と各国の税制や国際課税ルールとの間のずれを利用することで、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS)への対処に取り組んでいましたが、2021年になり、OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」における国際的合意のうち、グローバル・ミニマム課税(第2の柱)における所得合算ルール(Income Inclusion Rule、IIR)が、我が国において導入されることとなりました。
グローバル・ミニマム課税における所得合算ルールとは、国際的に最低限の実効税率(15%)を定めた上で、それを下回る国(=軽課税国)における最低税率での課税を確保するべく、親会社所在地国が、親会社に対して、子会社の最低税率に至るまで課税(トップアップ課税)するルールです(図表21参照)。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた改正法人税法が2023年3月28日に成立しています。当該改正法人税法では、基本的に、年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の多国籍企業を対象として、一定の適用除外を除く所得について最低税率15%の課税が確保されるように制度化をすることとされています。
図表21 グローバル・ミニマム課税における所得合算ルールの概要
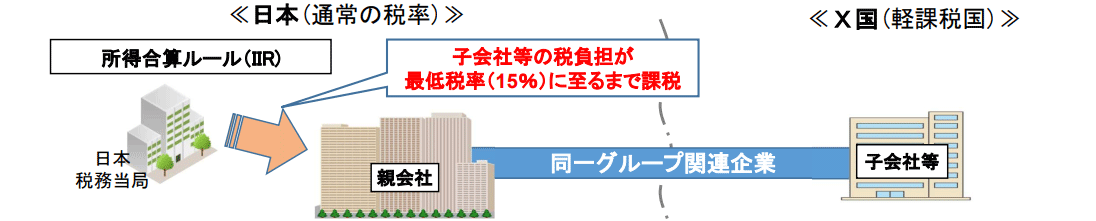
(出典:内閣府第21回税制調査会「財務省説明資料〔国際課税〕」、 www.cao.go.jp/zei-cho/content/4zen21kai1.pdf 〈2024年2月14日アクセス〉)
Q20. グローバル・ミニマム課税制度の税効果会計への影響【再掲・一部更新】
グローバル・ミニマム課税制度の導入による税効果会計への影響を教えてください。
A20.
(1) 税効果適用指針の定め
繰延税金資産及び繰延税金負債の額は、決算日において国会で成立している税法に規定されている方法に基づいて将来の会計期間における減額税金又は増額税金の見積額を計算することとされています(税効果適用指針44項)。
このため、グローバル・ミニマム課税制度を含む改正法人税法が成立した2023年3月28日以後、グローバル・ミニマム課税制度の適用(2024年4月1日以後開始する事業年度から適用)が見込まれる3月決算企業は、年度末決算においてグローバル・ミニマム課税制度を前提として、本来は、当該制度が税効果会計へ与える影響を検討する必要があります。
(2) 2023年実務対応報告第44号の公表
税効果会計は利益に関連する金額を課税標準とする税金を対象として認識するものですが、グローバル・ミニマム課税制度に基づいた基準税率(15%)までの上乗せ税額(以下「上乗せ税額」という。)は、親会社等がその所在地国の税務当局に支払うものであるため、課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業とが相違することとなり、税効果会計を適用すべきかが明らかではないと考えられます。また、仮に税効果会計を適用するとした場合、グローバル・ミニマム課税制度に基づく税効果会計の会計処理に関して、以下の点が明らかではないと考えられます。
① グローバル・ミニマム課税制度の適用によって、企業が、既存の税法の下で認識した繰延税金資産又は繰延税金負債を見直す必要があるかどうか
② 上乗せ税額を加味すると、税効果会計に使用する税率がどのような影響を受けるか
③ グローバル・ミニマム課税制度に基づき、追加的な一時差異を認識すべきかどうか
これらに加えて、実務上の負担も想定されます。
以上より、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)において、改正法人税法の適用を前提とした税効果会計を適用することは困難と考えられます。このため、当面の間、必要と考えられる取扱いを示すために、ASBJより実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下「2023年実務対応報告第44号」という。)が公表されました。
(3) 2023年実務対応報告第44号の内容
2023年実務対応報告第44号では、グローバル・ミニマム課税制度の適用を前提とした税効果会計を適用することは困難であることから、当面の間、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針にかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととされています。
また、(2)に記載のとおり、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計については、現行の枠組みにおいて適用すべきか否かが明らかではないと考えられることを踏まえて、企業間の比較可能性等の観点から、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するといった原則的な取扱いの適用を認めず、当該特例的な取扱いを一律に適用するとされています。
なお、当該特例的な取扱いは、グローバル・ミニマム課税制度の具体的な内容やグローバル・ミニマム課税制度の適用を前提として税効果会計を適用すべきかどうかが今後明らかになるまでの当面の取扱いであるため、特例的な取扱いを適用する期間は、ASBJが本実務対応報告の適用を終了するまでの間とされています。
(4) 2024年改正実務対応報告第44号の公表
2024年3月22日に、企業会計基準委員会(ASBJ)から、改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「2024年改正実務対応報告第44号」という。)が公表されています。2024年改正実務対応報告第44号では、令和5年度税制改正で導入された所得合算ルール(IIR)のみならず、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする取扱いを継続することとされています。
Q21. グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)の会計処理及び開示
実務対応報告第46号について、概要を教えてください。
A21.
(1) 実務対応報告第46号の概要
グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計について2023年3月に実務対応報告第44号が公表された後、法人税等(当期税金)の会計処理及び開示に関する取扱いについてもASBJにおいて検討が行われ、2024年3月22日に実務対応報告第46号が公表されています。
実務対応報告第46号の概要は以下のとおりです。
① 連結財務諸表及び個別財務諸表における会計処理
グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、計上時期を対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度として、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上することとされています。
また、財務諸表の作成時点において一部の情報の入手が困難な場合の見積りに関して、次の考え方が結論の背景において示されています。
- 対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度において適時に情報を入手することが困難な場合においては、財務諸表の作成時点で入手可能な対象会計年度に関する情報に基づきグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を見積ることとなる(初年度における見積りについては後述の(2)補足文書の概要を参照)
- 適用初年度の翌年度以降は、入手可能となる情報が増加し、さらに申告が行われた年度以降は情報を入手する体制の整備や実績値の把握等によって、より精緻な見積りが可能となると考えられる
- 企業が当事業年度の財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき見積った金額と翌事業年度の見積金額又は確定額との間に差額が生じたとしても、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積っている場合には、当該差額は誤謬にはあたらず、当期の損益として処理することになると考えられる。また、会計上の見積りの変更にあたって、当該差額に重要性がある場合には、会計上の見積りの変更に関する注記を行うこととなると考えられる
② 四半期財務諸表及び中間財務諸表における取扱い
四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下「四半期財務諸表」という。)においては、四半期財務諸表の作成にあたって入手している情報は年度に比して限定的な情報であると考えられる等の理由から、上記①の定めにかかわらず、当面の間、当四半期連結会計期間及び当四半期会計期間を含む対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができるとされています。また、従前より特定事業会社及び非上場会社が中間作成基準等を適用して作成する中間連結財務諸表及び中間個別財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)においても(Q24(3)参照)、適時に情報を入手し、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を合理的に見積ることが可能であるかどうかについては追加的な検討が必要であると考えられることから、中間財務諸表においても、当面の間、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができるとされています。
この「当面の間」について、その具体的な期間は、ASBJが追加的な検討を行い、当該取扱いを改正するまでの間であることを想定しているとされています。
また、この当面の取扱いを適用するときは、適用している旨を注記することとされています。
なお、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の成立により、金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止され、これまで四半期財務諸表を作成していた企業は中間財務諸表を作成することになります。その際に適用する会計基準についてASBJは検討を行い、2024年3月22日に企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「中間会計基準」という。)等を公表しています。この中間会計基準において、これまでに公表された会計基準等で使用されている「四半期財務諸表」等の用語は「中間財務諸表」等と読み替えるものとされています。このため、この中間会計基準を適用して作成する中間財務諸表に対しても、上記の四半期財務諸表における当面の取扱いは適用できることになります。
③ 貸借対照表における表示
連結貸借対照表及び個別貸借対照表において、グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものは、固定負債の区分に長期未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示することとされています。
④ 連結損益計算書及び個別損益計算書における表示
連結損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、対応関係の観点から、税金等調整前当期純利益の次に、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示することとされています。また、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が重要な場合は、当該金額を注記することとされています。この際、重要であるか否かは企業のキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解するために有用であるかどうかを踏まえて判断することになると考えられるとされています。
また、個別損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、連結損益計算書における表示区分との整合性の観点と親会社等の所得(利益)に対する税には直接的には該当しないものであるという観点から、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を次のいずれかの方法により表示することとされています。
- 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次にその内容を示す科目をもって区分して表示する
- 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示し、当該金額を注記する
ただし、個別損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の金額の重要性が乏しい場合には、上記の定めにかかわらず、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することができるとされています(この場合は当該金額の注記を要しない。)。
⑤ 適用時期等
実務対応報告第46号の定めは、グローバル・ミニマム課税制度の適用時期に合わせて、2024年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。
ただし、上記②の四半期財務諸表及び中間財務諸表において当面の取扱いを適用した場合の注記の定めに関しては、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。
(2) 補足文書
① 補足文書の概要
ASBJは、補足文書「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りについて」(以下「補足文書」という。)を実務対応報告第46号と同時に公表しています。その背景として、ASBJは、特に適用初年度におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の見積りについて、その困難さから具体的な指針を求める意見が聞かれたとされています。検討の結果、企業の状況により入手可能な情報とそれに基づく見積りは異なると考えられるため、見積りに関する具体的な指針を示さず、適用初年度において情報の入手が困難な場合に考えられる見積りの一例を補足文書として示されています。
なお、本補足文書は、実務対応報告第46号の定めを適用する場合において、実務に資するための情報を提供することを目的として公表するものとされており、企業会計基準、企業会計基準適用指針及び実務対応報告(以下「企業会計基準等」という。)を追加又は変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書であるとされています。
② 適用初年度における見積りの例
補足文書に示されている適用初年度における見積りの一例は次のとおりです。
- 対象範囲の判定を行うに際しては、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手していない国別報告事項に関する情報や恒久的施設等及び特殊な会社等に関する情報を適時に入手することができない場合には、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手している子会社等の情報のみに基づき国別実効税率を算定する等の方法により対象範囲の判定を行う。
- 子会社等におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の算定に際して、個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額並びに給与適用除外額及び有形資産適用除外額の算定において必要な情報について、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手しておらず対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度の決算時において適時に入手することができない場合には、従来の連結財務諸表の作成にあたって入手している子会社等の会計数値に基づき当該金額を見積る。
Q22. 令和6年度税制改正の概要
2024年3月28日に令和6年度税制改正法が国会で成立していますが、税制改正項目のうち当期の税効果会計に影響を与える可能性があると考えられる項目はあるでしょうか。
A22.
2024年3月28日に国会で成立した令和6年度税制改正法において、資本蓄積の推進や生産性の向上により供給力を強化するため、イノベーションボックス税制や戦略分野国内生産促進税制が創設されています。また、外形標準課税の適用対象法人の見直しも行われています。
これらの税制改正項目の概要及び税効果会計への影響は以下のとおりですが、このうち、イノベーションボックス税制の創設及び外形標準課税制度の見直しは当期の税効果会計に影響を与える可能性があると考えられます。
(1) イノベーションボックス税制
① 税制の概要
本税制は、企業が国内で自ら研究開発を行った特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、2025年から2032年までの間に開始する各事業年度において、当該知的財産の国内への譲渡所得又は国内外からのライセンス所得の30%の所得控除を認める制度です(図表22参照)。本税制は、所得全体から、知的財産から生じる所得のみを切り出して税制優遇を行うという、我が国で初の税制であるとされています 。(注3)
図表22 イノベーションボックス税制のイメージ
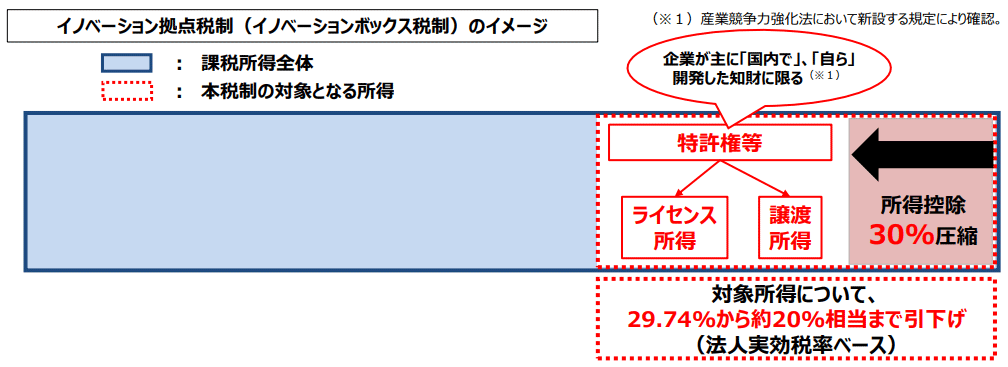
出典:経済産業省「令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について」(www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/pdf/03.pdf〈2024年1月26日アクセス〉)
注3 与党「税制改正大綱」(2023年12月14日)
② 税効果会計への影響
本税制の適用により、対象期間に当該知的財産に係る所得が生じた時に所得控除が認められ、税負担額が軽減されます。このため、本税制を含む改正法の成立日(2024年3月28日)以後、企業が本税制の適用を見込む場合、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りにおいて本税制を適用した場合の所得控除の影響を反映することになると考えられます。
ここで、本税制の適用対象となる知的財産に係る所得が生じるまでの期間において、本税制の適用対象となる知的財産を企業が資産計上している場合、当該資産から将来生じる所得により税負担額が軽減されることから、税効果会計上の一時差異等(税効果適用指針4項(3))が生じているかが問題となります。この点、知的財産を企業が資産計上しているとしても、将来の知的財産の譲渡等の取引により当該資産等から生じる原価(損金算入額)を上回る収入(益金算入額)が生じるまでは、当該取引に係る所得は生じず所得控除が認められません。このため、決算日時点において知財財産を資産計上しているだけでは将来の税負担額が軽減されるものではないことから、当該取引に係る一時差異等は生じていないものと考えられます。
(2) 戦略分野国内生産促進税制
① 税制の概要
本税制は、産業競争力強化法の改正を前提に、同法の改正法の施行の日から2027年3月 31 日までの間にされた同法の事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者であるものが、当該認定の日以後10年間、国として戦略的な長期投資が不可欠となる対象物資(図表23参照)を生産するための設備を取得した場合に、対象物資の生産・販売量に応じた金額とその設備の取得価額を基礎とした金額のうちいずれか少ない金額の税額控除を認める制度です。
各年度の控除上限は当期の法人税額の40%(半導体については20%)とされていますが、4年間(半導体は3年間)の税額控除の繰越期間を設けるものとされています。
図表23 戦略分野国内生産促進税制における対象物資ごとの単位当たり控除額
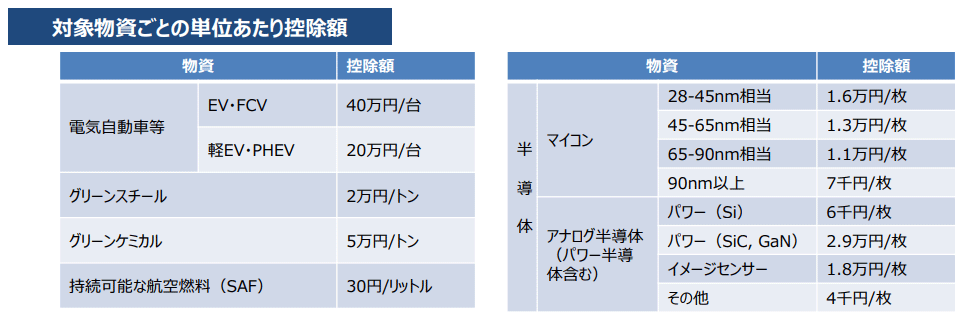
出典:経済産業省「令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について」(www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2024/pdf/03.pdf〈2024年1月26日アクセス〉)
② 税効果会計への影響
各年度において控除限度超過額が生じた場合、繰り越した控除限度超過額は翌期以降の繰越可能な期間の控除余裕額を限度として税額を控除することが認められ、将来の税負担額が軽減されることになります。このため、本税制が適用された後に生産・販売する対象物資から控除限度超過額が生じた際には税効果会計上の一時差異等に該当し、将来の対象物資の生産・販売量の見込み等を踏まえて繰延税金資産の計上要否を検討することになると考えられます。
(3) 外形標準課税制度の見直し
① 見直しの概要
外形標準課税制度は、資本金が1億円超の大法人を対象に2004年に導入されていますが、資本金の額を減少することで外形標準課税の適用対象法人から外れる事例が生じているとして、その対応として外形標準課税の適用対象法人の範囲の見直しが図られています。今回の見直し後においてもこれまでの資本金1億円超の法人が適用対象となるという基準は維持されますが、資本金が1億円以下となる場合であっても適用対象とする基準が追加されます。
具体的には、前事業年度に資本金が1億円超であることから外形標準課税の対象であった法人が、当事業年度に資本金が1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には、今回の見直しにより外形標準課税の対象となります。この見直しは、2025年4月1日以後開始する事業年度からとされています。
また、親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応として、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(改正法の公布日後に、当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算した金額)が2億円を超える法人についても、今回の見直しにより外形標準課税の対象となります。この見直しは、2026年4月1日以後開始する事業年度からとされています。
② 税効果会計への影響
繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとされています(税効果会計基準 第二 二 2)。ここで、法定実効税率の算定基礎となる事業税の税率は、外形標準課税対象法人に該当するかどうかにより異なります。この点、3月末の決算日までに上記①の見直しを反映した法律が国会で成立(2024年3月28日成立)していることから、決算日時点において、今回の見直し後の外形標準課税対象法人の要件を満たし、施行日以後開始する事業年度に外形標準課税対象法人になることが見込まれているのであれば、施行日以後開始する事業年度以降に解消する一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について外形標準課税対象法人に該当することを前提とする税率により計算することが考えられます。
今回の税制改正における見直しにより、決算日時点で見直し後の外形標準課税対象法人の要件を満たしているかどうかという状況を踏まえて、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を計算することにご留意ください。
改正四半期開示制度編
Q23. 改正四半期開示制度の概要
四半期開示制度の見直し(金融商品取引法の改正、財務諸表等規則等の改正、取引所の四半期決算短信)の概要を教えてください。
A23.
(1) 概要
2023年11月20日の臨時国会において、四半期開示制度の廃止を含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年度法律第79号)(以下「改正金商法」という。)が可決成立しています。
この改正金商法の成立によって、企業開示制度の見直しが行われ、四半期報告制度が廃止されることになりました。具体的には、この改正により、2024年4月1日以降に開始する四半期から四半期報告書制度は廃止され、上場会社には半期報告書の提出が義務付けられます。そして、第1・第3四半期開示については、四半期決算短信に一本化することになります(図表24参照)。
なお、2024年4月1日より前に開始した四半期会計期間については、従来通り、四半期報告書の提出が求められます。
図表24 四半期開示制度の見直しの全体像
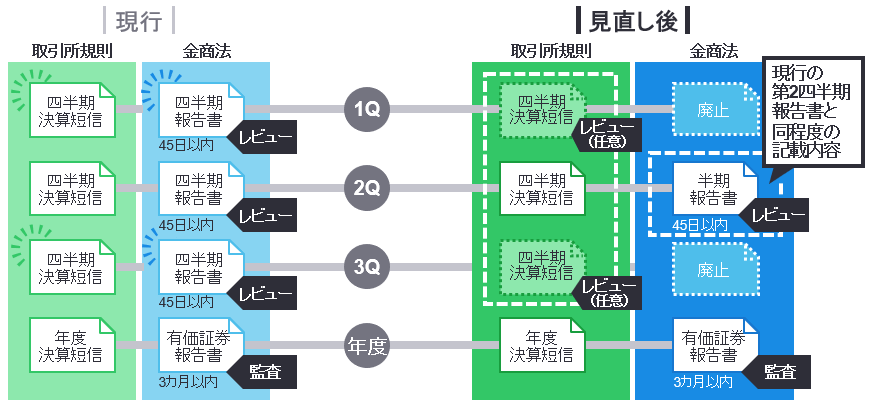
(2) 改正の目的
法改正にあたっては、デジタル化の進展等の環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を目的とするものであることが明示されています。改正の背景にある課題の1つとして、企業経営や投資家の投資判断においてサステナビリティを重視する動きがみられ、企業開示においても中長期的な企業価値に関連する非財務情報の重要性が高まっていますが、一方で、金融商品取引法に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信ではその内容に重複がみられ、コスト削減や効率化の観点から見直すべきとの指摘があったとされています。
このような状況を背景に、報告の頻度を見直すことにより企業の負担を軽減し、より長期的な視点での投資家とのコミュニケーションを促進することが改正の主要な目的とされています。
(3) 適用範囲
改正法により影響を受ける会社は以下のとおりです。
- 金融商品取引法24条の5第1項の表の1号に掲げる上場会社等
- 金融商品取引法24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する3号に掲げる非上場会社(※)
(※)3月期決算会社の2024年4月以後開始する事業年度から、非上場企業の半期報告書においても、新半期報告書の選択適用が可能(改正法24条の5第1項及び附則3条1項)。なお、銀行等(特定事業会社)の半期報告書の制度(中間監査)は変更はない
(4) 主要な改正点
今回の四半期開示制度の主要な改正ポイントの概略は以下のとおりです。
① 四半期報告書制度の廃止
金商法24条の4の7及び24条の4の8の削除により、上場会社が四半期ごとに四半期報告書を提出する義務が廃止されます。これにより、第1・第3四半期については、四半期ごとの詳細な財務情報の公開が義務ではなくなり、第2四半期に係る四半期報告書は、半期報告書としての報告に変更されることになります。
② 四半期決算短信の拡充
第1・第3四半期については、四半期報告書及び四半期決算短信の開示が一本化されます。これを受け、セグメント情報、キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項など、開示内容の追加が取引所規則により義務付けられることになります。
③ 四半期に係る会計監査人のレビュー
従来の四半期報告書においては、財務諸表について会計監査人のレビューが義務化されていましたが、第1・第3四半期の四半期報告書が廃止されることにより、法定のレビューは半期報告書のみとなります。
第1・第3四半期の決算短信に対する監査人のレビューは原則任意とされていますが、会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合には、監査人のレビューが義務となります。
(5) 改正法の適用時期
改正法の適用は、2024年4月1日以降に開始する四半期からとなります(改正法附則2条1項)。ただし、2024年4月1日より前に開始した四半期会計期間については、従来どおり、四半期報告書の提出が求められます。したがって、決算期によって四半期報告書が廃止され四半期決算短信に統一される時期、及び新たに定められた半期報告書の提出が求められる時期が異なるため、留意が必要です((図表25)参照)。
図表25 決算期別の改正法の適用時期
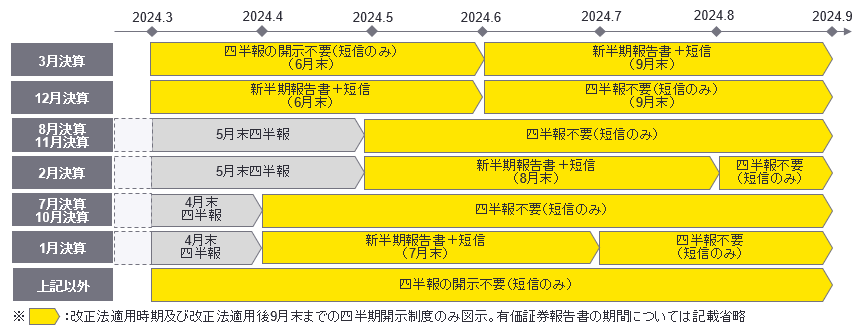
(6) 開示制度と適用される会計基準及び開示規則
制度見直し後の半期報告書は、ASBJ所管の中間会計基準及び金融庁所管の開示に関する法令(財務諸表等規則関係)に基づき作成することになります。一方で、四半期決算短信については、取引所規則に基づき作成されますが、その詳細については、現行の四半期会計基準を参照する形となりました((図表26)参照)。
図表26 四半期開示制度見直し後に適用となる会計基準
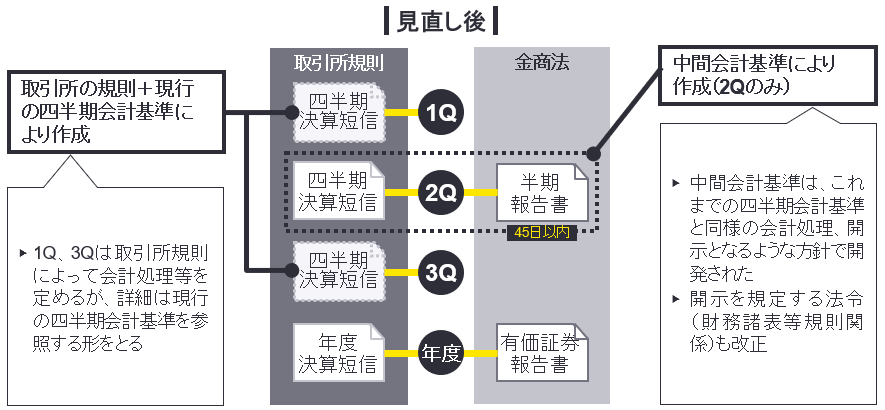
① 金融庁(開示府令、財務諸表等規則等)
金融庁は、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定を整備するため、2024年3月27日に「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令」等を公布しています。
これにより、従前の四半期(連結)財務諸表は、第1種中間(連結)財務諸表に改正され、従前の中間(連結)財務諸表は、第2種中間(連結)財務諸表に改正されました。第1種中間(連結)財務諸表が含まれる半期報告書は、改正前の第2四半期(連結)財務諸表が含まれる第2四半期報告書と同程度の記載内容となっています。
また、今回の改正においては、財務諸表等規則、四半期財務諸表等規則及び中間財務諸表等規則の一体化が行われており、(図表27)のような再編を行われています。これは、連結財務諸表規則、四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則についても同様となります。
図表27 財務諸表等規則等の再編
【財務諸表等規則】
|
現行 |
改正 |
|---|---|
|
財務諸表等規則 |
第1編 総則 |
|
四半期財務諸表等規則 |
第1編 総則 |
|
中間財務諸表等規則 |
第1編 総則 |
【連結財務諸表規則】
|
現行 |
改正 |
|---|---|
|
連結財務諸表規則 |
第1編 総則 |
|
四半期連結財務諸表等規則 |
第1編 総則 |
|
中間連結財務諸表等規則 |
第1編 総則 |
② ASBJ(中間会計基準)
ASBJにおいて、改正後の金融商品取引法上の半期報告書制度に対応する会計基準等について検討が行われ、2024年3月22日に、中間会計基準及び中間適用指針が公表されています。
この中間会計基準の詳細は(Q24)をご参照ください。
③ 東京証券取引所(四半期決算短信)
東京証券取引所では、2023年11月22日に、「四半期開示の見直しに関する実務検討会」における検討を踏まえ、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」をとりまとめ、公表しています。また、2023年12月18日には、「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」を公表し、2024年3月28日に有価証券上場規程等の改正が行われました。
第1・第3四半期に係る決算短信の開示内容については、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告で示されていた方向性を踏まえ、四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家の要望が特に強い事項を四半期決算短信に追加し、開示を義務付けるとされました。開示を義務付ける事項は、(図表28)のとおりですが、現行の四半期決算短信から、サマリー情報に「レビューの有無」の記載を追加するとともに、添付資料の四半期財務諸表等において、「セグメント情報等の注記」及び「キャッシュ・フローに関する注記(任意に四半期キャッシュ・フロー計算書を開示する場合を除く。)」を追加しています。
また、開示が義務付けられる事項以外についても、原則として、上場会社が投資者ニーズを適切に把握し、投資者ニーズのある事項に関して積極的に開示することが重要とされています。このため、会社情報適時開示ガイドブックにおいて投資判断に有用と考えられる情報を例示し、投資者ニーズに応じた自発的な開示を促すこととされました。この投資判断に有用と考えられる情報の具体例は(図表28)をご参照ください。
図表28 第1・第3四半期決算短信の開示内容
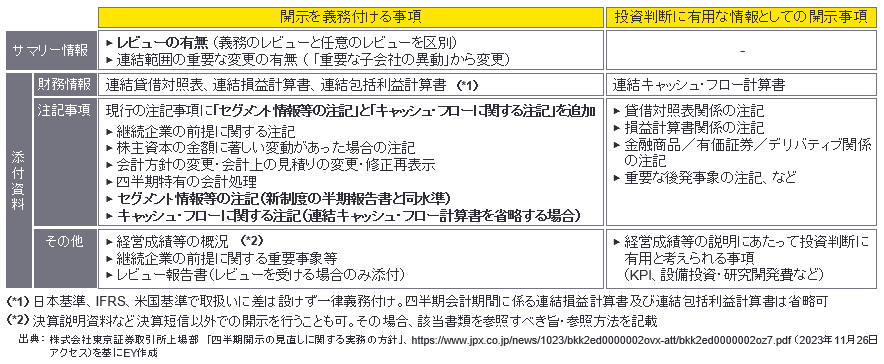
Q24. 中間財務諸表に関する会計基準
四半期開示制度の見直し後の中間財務諸表の会計処理及び開示はどのようになるのか、中間会計基準の概要を教えてください。
A24.
(1) 概要
ASBJにおいて、金融商品取引法上の四半期報告書制度の見直しへの対応として、改正後の金融商品取引法上の半期報告書制度に対応する会計基準等について検討が行われ、2024年3月22日に、中間会計基準及び中間適用指針(以下、合わせて「中間会計基準等」という。)が公表されました。
(2) 公表理由
(Q23)の通り、2023 年 11 月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和 5 年法律第 79 号)が成立し、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止され、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとされます。これにより改正後の金融商品取引法上は半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表(以下合わせて「中間財務諸表」という。)が開示されることになるため、当該中間財務諸表に係る会計処理及び開示に関する取扱いを定めたものです。
(3) 適用範囲
中間会計基準等は、次の会社が半期報告書制度に基づき作成する中間財務諸表に適用されます。
- 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号に掲げる上場会社等
- 金融商品取引法第24条の5第1項ただし書きにより、同項の表の第1号に掲げる上場会社等と同様の半期報告書を提出する第3号に掲げる非上場会社
(※)なお、従前より特定事業会社及び四半期財務諸表を提出していない非上場会社においては中間財務諸表の作成が義務付けられ、当該中間財務諸表には、中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解(以下合わせて「中間作成基準等」という。)が適用されています。これらの会社が作成する中間財務諸表については、引き続き中間作成基準等が適用されることになります(中間会計基準BC10項)。
(4) 開発にあたっての基本的な方針
中間会計基準等の開発にあたっての基本的な方針として、中間財務諸表の記載内容が従前の第 2 四半期報告書と同程度の記載内容となるように、基本的に四半期会計基準及び四半期適用指針(以下合わせて「四半期会計基準等」という。)の会計処理及び開示を引き継ぐこととしています。
また、期首から 6 か月間を 1 つの会計期間(中間会計期間)とした場合と、四半期会計基準等に従った第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性がある項目((6)参照)については、改正後の金融商品取引法の成立日から施行日までの期間が短期間であることから、会計処理の見直しにより企業の実務負担が生じないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めています。
(5) 中間財務諸表の範囲
中間財務諸表の範囲は、中間財務諸表が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容を基本とすることを踏まえ、(図表29)のとおりとされています。
図表29 中間財務諸表の範囲 |
|
中間連結財務諸表 |
中間連結貸借対照表 中間連結損益及び包括利益計算書(※1) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 |
|
中間個別財務諸表(※2) |
中間個別貸借対照表 中間個別損益計算書 中間個別キャッシュ・フロー計算書 |
(※1)2計算書方式による場合は、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(※2)中間連結財務諸表を開示する場合、中間個別財務諸表の開示は不要
(6) 中間会計基準等で個別に検討した項目
中間財務諸表において期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とすることに伴い差異が生じる可能性がある項目については、個別に検討が行われており、そのうち一部の項目については経過措置を定めています((図表30)参照)。
なお、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法について、公開草案では、経過措置を設けた経緯から四半期適用指針に基づいて四半期適用指針に基づいて四半期切放し法を適用していた場合という条件を記載されていましたが、中間会計基準等の適用初年度において従前の四半期財務諸表において採用していた会計方針(年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針を除く。)との継続性は求められないため、当該記載は削除されています(中間適用指針BC2項)。
図表30 中間財務諸表に係る取扱いと四半期会計基準等の取扱いに差異が生じる可能性がある項目とその対応
|
項目 |
内容 |
経過措置 |
|---|---|---|
|
原価差異の繰延処理 |
原価差異の繰延処理を認める |
- |
|
子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日 |
みなし取得日の決算日等には、期首、中間会計期間の末日又はその他の適切に決算が行われた日を含む(四半期決算日を引き続きみなし取得日として適用可能とすることを意図したもの。その他の適切に決算が行われたとは、子会社において中間会計基準に準じた決算が行われたことを想定している(中間会計基準BC18項)) |
- |
|
有価証券の減損処理に係る中間切放し法 |
中間会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れに関しては、中間切放し法と中間洗替え法の2つがある。中間切放し法と中間洗替え法のいずれかの方法を選択適用することができる |
中間会計期間末における有価証券の減損処理について、第1四半期の末日において切放し法を適用したものとして中間会計期間末において切放し法を適用することができる |
|
棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法 |
年度決算において切放し法を適用している場合は、中間会計期間末において、洗替え法と切放し法のいずれかを選択適用することができる |
棚卸資産の簿価切下げについて、第1四半期の末日において切放し法を適用したものとして中間会計期間末において切放し法を適用することができる |
|
一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理 |
著しく変動していないと考えられる場合には、前年度末の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用することができる |
第1四半期の貸倒実績率等と著しく変動していないと考えられる場合には、第1四半期の貸倒実績率等の合理的な基準を使用して中間会計期間末における一般債権に対する貸倒見積高を算定することができる |
|
未実現損益の消去における簡便的な会計処理 |
前年度から取引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前年度の損益率や合理的な予算制度に基づいて算定された損益率を使用して計算することができる |
第1四半期から取引状況に大きな変化がないと認められる場合には、中間会計期間末における未実現損益の消去について、第1四半期における損益率を使用して計算することができる |
(7) 適用時期
中間会計基準等は、改正後の金融商品取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用されます(中間会計基準37項)。
なお、適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について中間会計基準等を遡及適用することとされています(中間会計基準38項)。
(8) 今後の基準開発の方向性
中間会計基準等では、改正後の金融商品取引法の成立日から施行日までの準備期間が非常に短い中で、短期的な対応として、改正後の金融商品取引法に従って新たに中間財務諸表を作成する場合の会計処理及び開示について定めています。
一方、今般の法改正により、金融商品取引法上は中間財務諸表のみを作成することになりますが、上場会社においては四半期決算短信が提出されるため、引き続き3か月ごとに決算が行われることになります。四半期決算短信については取引所規則に従うこととされていますが、上場会社の観点からは四半期決算短信と中間財務諸表は連続したものとして作成することから、同じ会計基準等に基づいて中間決算と四半期決算を行うべきであるとの意見が聞かれていました。
これらを踏まえ、ASBJは本会計基準等の公開草案の公表時に、今後の基準開発の方向性についてコメントを募集しました。
コメントでは、本会計基準等と四半期会計基準等を統合した期中財務諸表に関する会計基準等を開発し、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用するという提案に賛成する意見と、提案に反対し中間財務諸表にも現行の四半期会計基準等をそのまま適用できるように改正するという代替案を提案する意見等が聞かれています。
いずれの意見も本会計基準等と四半期会計基準等を統合することには反対していないものの、統一の方法に関しては様々な意見があるため、ASBJではこれらの意見を踏まえて、今後検討を行う予定としています。
なお、金融商品取引法上は四半期報告書制度が廃止されますが、上場会社においては引き続き取引所規則に基づき第1・第3四半期決算短信の報告が行われるため、今後、期中財務諸表に関する会計基準等の開発が行われるまでの間、四半期会計基準等は適用を終了しないことが予定されています。
非財務情報編
Q25. 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報等の開示
2023年3月期の有価証券報告書から、2023年1月31日改正の開示府令等に基づく開示をしていますが、2024年3月期の開示の検討にあたり留意すべき点や参考にすべき情報を教えてください。
A25.
2023年1月に公布・施行された改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)等に基づく有価証券報告書のサステナビリティ情報等の開示は、2023年3月期から行われています。2024年3月期では2年目の開示として、開示府令で要求される内容を明瞭に記載することに加え、各企業の取組みの進展も踏まえ、より一層充実した内容の開示を積極的に行うことが期待されます。
開示の検討にあたっては開示府令等で求められる開示内容を再度ご確認いただくとともに(2023年3月期 決算上の留意事項参照)、金融庁から2024年3月29日に公表された「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)」における「令和5年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等」の内容をご確認ください。サステナビリティに関する開示及びコーポレートガバナンスの状況等の開示が2024年3月期の有価証券報告書のレビュー対象とされたことも踏まえ、前期の審査結果を踏まえた課題として挙げられた以下の項目について、特に留意が必要です。
- サステナビリティに関する考え方及び取組
- サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭
- サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価及び管理するための過程の記載がない又は不明瞭
- 戦略並びに指標及び目標のうち、重要なものについて記載がない
- サステナビリティ関連のリスク及び機会の記載がない又は不明瞭なため、サステナビリティに関する戦略並びに指標及び目標に関する記載が不明瞭
- 人的資本に関する方針、指標、目標及び実績のいずれかの記載がない又は不明瞭
- サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭
- 従業員の状況
- 女性管理職比率を女性活躍推進法の管理職の定義に従って算定・開示していない
- 女性管理職比率を女性活躍推進法の管理職の定義に従って算定・開示していない
- コーポレート・ガバナンスの状況等
- 取締役会、会社が任意に設置する指名・報酬委員会、監査役会等の開催頻度、具体的な検討内容、出席状況等の記載がない
- 内部監査が取締役会に直接報告を行う仕組みの有無に関する記載がない
- 政策保有株式縮減の方針を示しつつ、売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的の株式に変更を行っており、又は、発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したものの、実際には長期間売却に取り組む予定はなく、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態にある
- 取締役会、会社が任意に設置する指名・報酬委員会、監査役会等の開催頻度、具体的な検討内容、出席状況等の記載がない
また、2023年12月27日に金融庁から公表され、2024年3月8日に更新された「記述情報の開示の好事例集2023」の更新」が参考になると考えられます。
この好事例集では、有価証券報告書の記載項目である「サステナビリティに関する考え方及び取組等」、「コーポレート・ガバナンスの状況等」(「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況」、「株式の保有状況」)及び「経営上の重要な契約等」に関し、今後の開示の参考となる好事例が掲載されているとともに、「投資家、アナリスト、有識者が期待する主な開示のポイント」が開示項目別に記載されており、財務諸表利用者の期待を踏まえた開示を検討する際に有用になるものと考えられます。
以下の表に「投資家、アナリスト、有識者が期待する主な開示のポイント」の一部を記載していますが、詳細は全文をご参照ください。また、「好事例として採り上げた企業の主な取組み」も紹介されており、開示面のみならず、企業のサステナビリティを高める取組み自体を検討する際にも参考になるものと考えられます。
「投資家、アナリスト、有識者が期待する主な開示のポイント」(一部を抜粋、要約)
- サステナビリティ情報全般
- 比較可能性、透明性、独自性の3つの観点が重要
- ESGやサステナビリティに関するKPIの選定理由や算定方法等についての説明が有用
- 比較可能性、透明性、独自性の3つの観点が重要
- サステナビリティ情報 全般的要求事項
- 企業の全体戦略とサステナビリティの関わりについての開示が有用
- 企業の全体戦略とサステナビリティの関わりについての開示が有用
- 気候変動
- Scope3についての開示も期待
- シナリオ分析において自社に関係ある情報を反映するとともに、データソースの開示が有用
- Scope3についての開示も期待
- 人的資本、多様性等
- 経営戦略と人材戦略の関係性の開示が有用
- 人的資本のうちコンプライアンス色が強い部分は比較可能性が期待され、戦略的な部分は経営戦略と関連した独自性の高い開示が期待
- 経営戦略と人材戦略の関係性の開示が有用
- 人権
- 想定される具体的なリスクと回避方法の開示が有用
- 想定される具体的なリスクと回避方法の開示が有用
- <コーポレートガバナンスの状況等ほかの開示>
- コーポレート・ガバナンスの概要
- ガバナンスの実効性は取締役会及び委員会の具体的な内容の開示やスキルマトリクスなどにより読み取ることが可能と考えられ、実効性を表す開示として取締役会で否決又は反対票が投じられた議案の数や比率の開示が有用
- 取締役会議長等の視点からのガバナンス活動の開示は、どのような活動や取組が行われているかに加え、その取組等の意味や意義、ガバナンスの実効性がわかるため有用
- ガバナンスの実効性は取締役会及び委員会の具体的な内容の開示やスキルマトリクスなどにより読み取ることが可能と考えられ、実効性を表す開示として取締役会で否決又は反対票が投じられた議案の数や比率の開示が有用
- 監査の概要
- 監査役・監査委員会等の委員長の視点による監査の状況の認識や、監査役会等の活動状況等の説明内容の開示が有用
- 重点監査項目の選定理由、具体的な活動内容をストーリーで開示することが有用
- KAMについての監査役等の具体的な検討内容の開示が有用
- 監査役・監査委員会等の委員長の視点による監査の状況の認識や、監査役会等の活動状況等の説明内容の開示が有用
- 株式の保有状況
- 政策保有株式の削減実績は、簿価ベースだけでなく時価ベースでも開示することが有用
- 政策保有株主から政策保有株式の売却等の意思表示が示された際に、売却を妨げることはない旨を記載することが有用
- 政策保有目的から純投資目的への区分変更の場合は、その理由や区分変更後の議決権行使基準、売却までの想定期間等の開示が有用
- 政策保有株式の削減実績は、簿価ベースだけでなく時価ベースでも開示することが有用
- 経営上の重要な契約等
- 開示の法令は契約上の守秘義務に優先することから、秘匿性の高いものや実質的な秘密等を除き、契約上の守秘義務を理由として開示対象から外すことについての合理的な説明を行うことは難しいため、積極的な開示が有用
- 財務制限条項に抵触した場合、債権者からの期限の利益喪失請求等の有無の開示に加えて、債権者から請求等がない場合にその理由の開示が有用
- 経営上の重要な契約等と事業等のリスクや株式の保有状況等の開示との連動が有用
- 開示の法令は契約上の守秘義務に優先することから、秘匿性の高いものや実質的な秘密等を除き、契約上の守秘義務を理由として開示対象から外すことについての合理的な説明を行うことは難しいため、積極的な開示が有用





