EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

本稿では、日本の製造業をめぐる従来の競争環境と付加価値の源泉を再整理した上で、デジタル化によるビジネスモデルへの影響と戦略の再構築のための方向性について考察します。
本稿の執筆者
EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) EYパルテノン 末永 宣之
プライベートエクイティファンド・商社・製造・ハイテク業界のクライアントに対して、成長戦略、M&A、新規事業創発支援、事業統合、企業変革支援のコンサルティング業務に従事。特に、デジタル・テクノロジー企業の事業や製品、サービスの評価をはじめ、ソフトウエア戦略、事業投資後の価値向上に関する助言を数多く提供している。EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) パートナー。
EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) EYパルテノン 井上 陽介
プライベートエクイティファンド・金融・製造・商社のクライアントに対して、M&A、知的財産の戦略的活用、成長戦略のコンサルティング業務に従事。知的財産を経営戦略の一部に組み入れるためのサービス開発や提案活動を行っている。EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) ビジネスアナリスト。
要点
- コーポレートガバナンス・コード改訂における知財ガバナンス強化を単なる制度対応ではなく企業変革につなげるにはどうすればよいか。
- 新興国メーカーの戦略的強みは、本当に人件費などのコスト優位性だけか。
- 先進国メーカー/IT企業の戦略的強みは、本当にマーケティングの巧拙のような発想力の豊かさだけか。
Ⅰ はじめに
2021年と2022年は、経営者にとって知的財産への関心が高まる年となりました。2021年6月、改訂コーポレートガバナンス・コードが公表され、補充原則3-1③の中で「知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべき」と明記されました。さらに、原則に沿った開示を行うためのガイドラインとして、2022年1月には内閣府より「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」が策定され、企業は対応を求められています。
重要なのは、コーポレートガバナンス・コードでは「自社の経営戦略・経営課題との整合性」の開示が求められており、ガイドラインでは知財・無形資産の「投資・活用戦略の開示・発信」の前に「現状の姿の把握」から「投資や資源配分の戦略の構築」までをすべきとされている点です。
本稿では、なぜ研究開発と知財の保有状況の開示だけではなく、自社の事業を見直し戦略を再構築する必要があるのかについて考察します。
Ⅱ 各国の研究開発費および特許取得数と、日本企業の時価総額ランキングからの退出
経済協力開発機構(OECD)によると、日本企業が研究開発にかける費用は主要国の中で特に大きく、GDP比の研究開発費の割合は1990年代から2009年まで主要国1位であり、韓国に追い抜かれた2010年以降も世界上位を保っています※1(<図1>参照)。
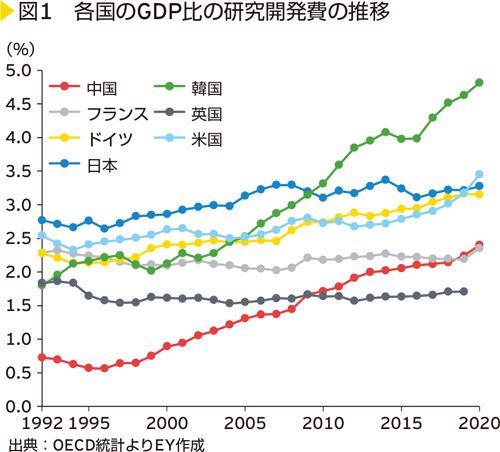
また、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization:WIPO)によると、日本企業はパテントファミリー数においても、2010年まで主要国1位を維持していました※2(<図2>参照)。
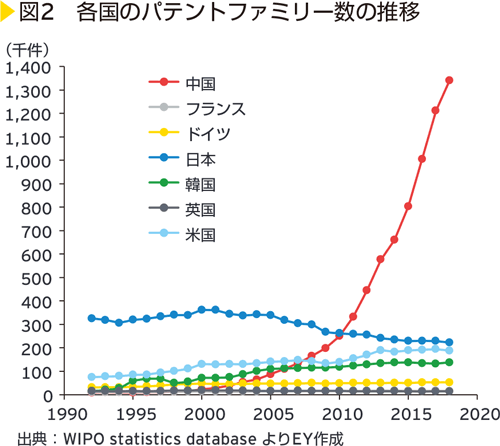
特に、電気機械器具・エネルギーと輸送機器の分野では、日本が世界で1位の特許出願数のシェアを保持しています(<図3>参照)。
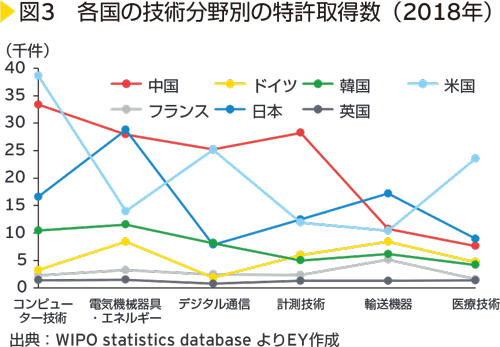
このように、近年は韓国にGDP比研究開発費で、中国に特許取得数で後塵(こうじん)を拝しているとはいえ、日本は現在も研究開発・特許大国であると言えます。
しかし、日本の製造業は世界で市場シェアや企業価値を失いつつあります。例えば、世界の時価総額トップ50社に占める製造業の企業数は1989年から2022年までに19社から26社に増加した一方、その中の日本企業の数は11社から1社にまで数を減らしています※3。
旺盛な研究開発を行い、特許も多く取得している日本の製造業が過去30年で世界の時価総額トップ企業群からほとんど姿を消してしまった理由の1つに、製造バリューチェーン上の付加価値の源泉が変化してきたことが考えられます。
Ⅲ 製造バリューチェーンにおける付加価値源泉の変化
1. ハードウエアのすり合わせ技術
かつての日本企業の強みとして『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件』の著者である小川紘一氏が指摘しているのが、先端技術の開発と工場中心のものづくりを支えるハードウエアのすり合わせ技術です。
例えば、ブラウン管テレビを作るためには、開発者・部品製造・画像職人・現場技術者の連係プレーが必須となっていました。開発担当者と部品製造担当者が調整を繰り返して生み出した部品を、画像職人がさらに微調整しながら組み合わせて画像を映し出し、その職人の技を工場の大量生産ラインで再現できるようなライン設計が必要だったのです。この複雑な調整を実現するため、日本の電機メーカーは内製化やケイレツ化を進め、垂直統合的なサプライチェーンを構築して、世界で高いシェアを保持していました。
この時代には、特定の人材の引き抜きや、同じ部品の調達ができたとしても、企業間・人材間の調整の仕組みそのものを引き抜くことはできませんでした。また、日本企業は企業間でクロスライセンスを行う慣行があり、日本の企業群は厚い特許網で守られていました。
2. ICチップの導入によるモジュール化
1980年代、米国でパソコンの販売が本格化しました。パソコンが製造業の観点で革新的だったのは、部品間のすり合わせの必要が少なかったことです。パソコン以前の製造業では、ブラウン管テレビの例のように部品間の不整合を開発段階での調整によってなくしておく開発手法がとられていましたが、パソコンでは標準仕様を公開したことと部品の制御を担うICチップを導入したことで、開発段階での調整の必要を減らしたのです。この開発手法の変化はビジネスモデルにも変化をもたらしました。調整が少なく済むので、部品の組立工程を新興国のメーカーへ外注することが可能となり、組立工程においてバリューチェーン上のプロセスを積み木のように組み立てる、「モジュール化」が進んでいきました。
この「ICチップによる部品制御」は、液晶テレビやDVDなどさまざまな製品に応用されていきました。ICチップの普及に従い、日本の製造業におけるすり合わせ型の強みを支えた人材は人件費という足かせになっていきました。しかし、自社のビジネスの危機に気付いた頃には、すでに米国メーカーが業界標準仕様の基本ソフト(OS)を握っているため太刀打ちできず、ビジネスモデルを転換することはできませんでした。この流れが顕著になったのは1990年代中期以降ですが、この時代、日本企業の経営者はバブル崩壊後の国内市場低迷に対する対策や負債比率の増加に対する財務体質改善やコスト削減のために奔走しており、これらがバリューチェーンの変化への対応が遅れた原因ともなりました。
3. Industry 4.0の普及によるデジタル化、プラットフォーム化
さらに、2011年にドイツの「High-Tech Strategy 2020」の中でIndustry 4.0が採択され、製造業に新たな契機が訪れます。Industry 4.0はCPS(サイバー・フィジカル・システム)という、仮想空間上の工場(Cyber)と現実の工場(Physical)をIoTセンサーによってリンクさせ、仮想空間上でAIを用いて製造の最適化を行い、現実の工場に指示を出す技術によって「スマート工場」を実現する構想です。Industry 4.0の取組みは、2013年4月にドイツで官民連携のIndustry 4.0実現プロジェクトチームが組成され、2014年3月には米国でインダストリアル・インターネット・コンソーシアムが発足するなど、2010年代前半に急速に普及が進んでいきました。
Industry 4.0の普及によって、オペレーション効率の圧倒的な効率化が進むとともに、製造業のバリューチェーン全体のモジュール化が発展しました。ここではその代表例としてデジタルケイレツについて紹介します。
2000年代、Industry 4.0以前の時代には、ICチップが組立工程のモジュール化への転換を起こしたとはいえ、ケイレツ内の企業にリーダー企業が人材を派遣して現場改善を行うといった日本独自の強みは健在でした。しかし、Industry 4.0の普及により、欧州でもデジタルツールによってケイレツの手法を取り入れる取組みが生まれました。これを『製造業プラットフォーム戦略』の著者の小宮昌人氏は「デジタルケイレツ」と名付けています。デジタルケイレツは、ケイレツを代表する企業がプラットフォームを作り、製造ノウハウをアプリとして提供するモデルです。
欧州では日本と違い部品メーカーが複数の最終製品メーカーと取引をしていることが一般的です。そのため、デジタルケイレツを主導する企業は、部品メーカーに自社のケイレツに入ってもらえるよう、アプリの機能の拡充や参加企業の募集に余念がありません。例えば、ドイツの自動車産業では大手2社が互いのプラットフォームの拡大を競っています。
このデジタルケイレツの普及は、日本の製造業にとって、「ケイレツ文化が真似された」以上の脅威があります。なぜなら、デジタルケイレツは日本のように人材を派遣する負担がなく、ケイレツ企業の製造データを蓄積して活用できる追加メリットがあるなど、日本のケイレツ文化よりも利点が多いからです。
さらに、デジタルケイレツ以外にも、工作機械にセンサーを取り付けて製造ノウハウをデータとして販売する手法や、3Dモデリングを用いて新興国にマザー工場と同じラインを素早く組み立てる技術、製造ラインを立ち上げることを専門とするラインビルダーやその下請けの生産設備SIerと呼ばれる企業が現れており、例えば、新興国の企業が何もノウハウがない状態から自動車の量産ラインを21カ月で開始できるようになるなど、日本企業がそれまで強みとしてきた領域でデジタル技術を活用したさまざまな競合が現れ、低コストで類似の製品を世界中のどこでも製造できる時代が近づいています(<図4>参照)。
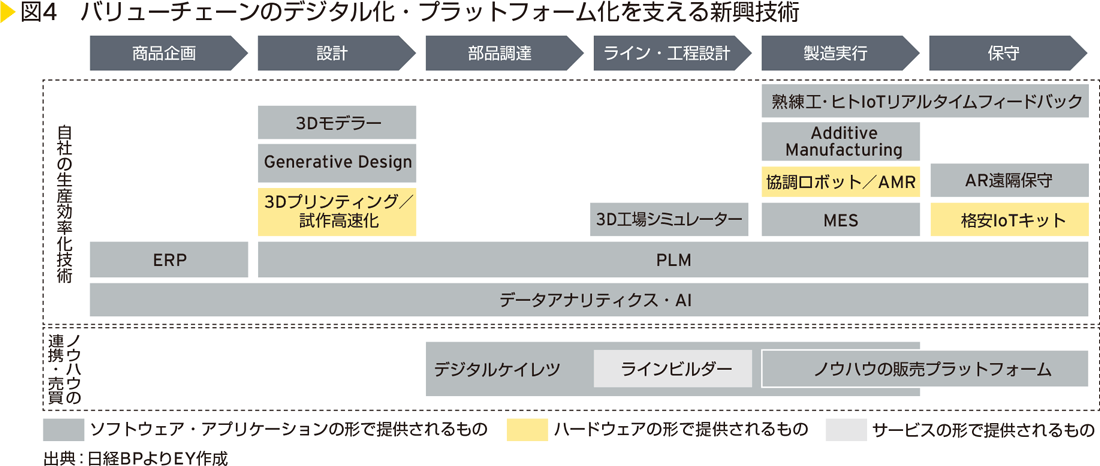
Ⅳ 製造バリューチェーンの変化への適応
1990年代以降、モジュール化されたプロセスに研究開発を行った日本企業は、多くの特許を持ちながらも市場シェアを失っていきました。例えば1993年から日本企業連合が開発したDVDは、世界標準を獲得し、必須特許の90%を持ちながらも撤退を余儀なくされました。また、日本企業が長年の研究の末に実用化した大型液晶テレビは、2001年には世界シェアを80%以上握り、2005年までに米国で出願された関連特許の88%を日本企業が握ったものの、2021年の世界シェアのほとんどは韓国企業と中国企業が握っている状況です。
デジタル化・プラットフォーム化が進んだバリューチェーンにおいては、たとえ高い技術力と厚い特許網があったとしても、必ずしも市場シェアを維持できるとは限りません。自社の強みとなる事業領域の環境変化を把握し、プラットフォームを構築する「キーストーン企業」や、複数のプラットフォームに独自の価値を提供する「エッジ企業」になれるよう、ビジネスモデルや事業戦略を柔軟に転換してはじめて、市場シェアを維持できるのです。
冒頭に触れた改訂コーポレートガバナンス・コードが「知的財産への投資の経営戦略との整合性」を開示することを求めているのは、このような背景があるためだと考えられます。コーポレートガバナンス・コードの改訂への対応を、単なる規制対応ではなく、自社の戦略を再構築する好機と捉え、<図5>のような論点を検討していくべきではないでしょうか。
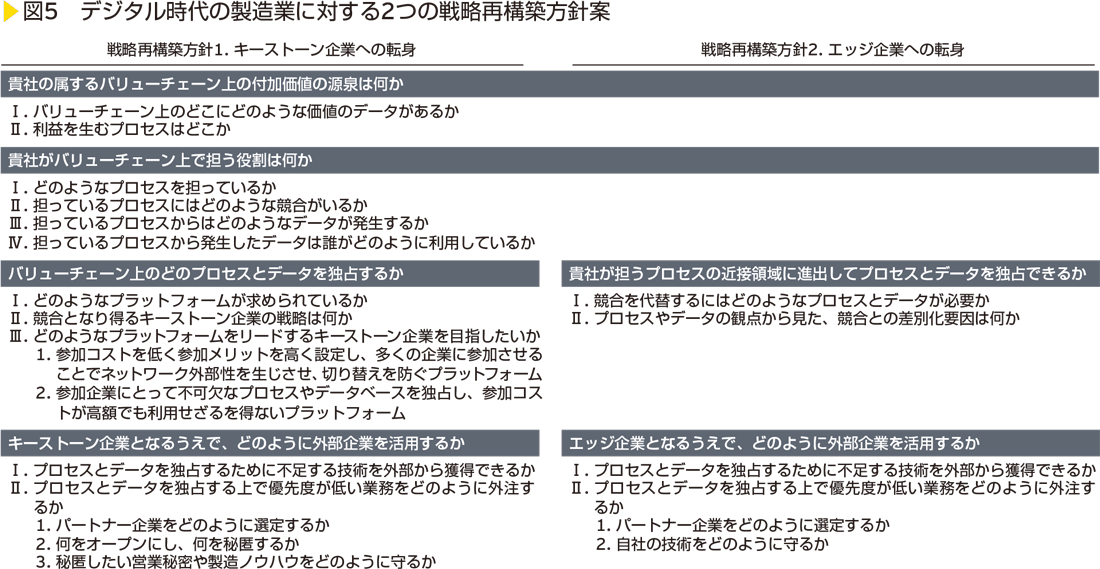
<参考文献>
- 日本取引所グループ「コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)』(株式会社東京証券取引所、2021年)
- 内閣府「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン Ver 1.0」(知的財産戦略推進事務局、2022年)
- 小川紘一『オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件』(翔泳社、2014年)
- 丸島儀一『知的財産戦略』(ダイヤモンド社、2011年)
- ジェームス・C・アベグレン(山岡洋一訳)『新・日本の経営』(日本経済新聞出版、2004年)
- 尾木蔵人『決定版 インダストリー4.0-第4次産業革命の全貌』(東洋経済新報社、2015年)
- 小宮昌人『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP、2021年)
- 西澤佑介「液晶テレビ産業における日本企業の革新と衰退」(経営史学会49巻2号、2014年)
※1 OECD(2022),“Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds”,“Economic Outlook No 111 - June 2022”, stats.oecd.org/(2022年7月9日アクセス)
※2 WIPO statistics database(last update 2021 November), www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent(2022年7月4日アクセス)
※3 CNET Japan「グラフで見る、2022年の「『世界時価総額ランキング』-- 50位以内の日本企業はトヨタのみ」、japan.cnet.com/article/35182623/(2022年7月9日アクセス)
「情報センサー2022年10月号 Trend watcher」をダウンロード
サマリー
本稿では、日本の製造業をめぐる従来の競争環境と付加価値の源泉を再整理した上で、デジタル化によるビジネスモデルへの影響と戦略の再構築のための方向性について考察します。
関連コンテンツのご紹介
戦略(EYパルテノン)、買収・合併(統合)・セパレーション、パフォーマンスの再構築、コーポレート・ファイナンスに関連した経営課題を独自のソリューションを活用し、企業成長を支援します。
EYパルテノンのデジタル戦略コンサルティングチームは、ビジネストランスフォーメーションを加速させる上で効果的かつ成長を促進するデジタルビジネス戦略を設計し、提供しています。



