EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2023年7月号 会計情報レポート
EY新日本有限責任監査法人 品質管理本部 会計監理部
公認会計士 平川 浩光
公認会計士 石川 仁
品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務に従事している。
Ⅰ はじめに
2024年3月期より、原則適用となる会計基準及び早期適用可能となる会計基準は<表1>のとおりです。
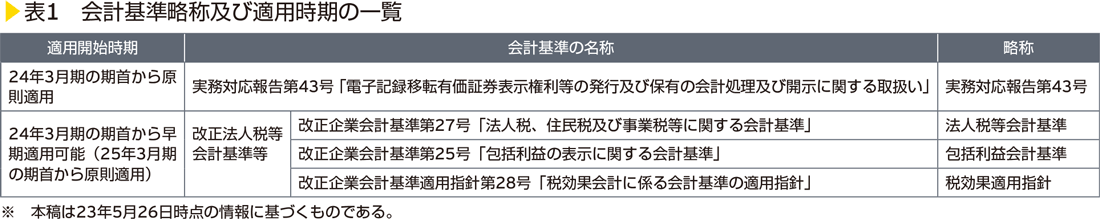
本稿ではこれらを中心に24年3月期第1四半期決算に影響する会計基準を解説するとともに、年度の最初に迎える第1四半期決算でよくある検討ポイントについても解説します。
また、本文中で使用する会計基準の略称及び適用開始時期は同じく<表1>のとおりです。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者らの私見であることをあらかじめお断りします。
Ⅱ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
1. 範囲
実務対応報告第43号は、株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の会計処理及び開示を対象としています。電子記録移転有価証券表示権利等とは、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令52号)1条4項17号に規定される権利をいい、金融商品取引法(昭和23年法律25号)2条2項に規定される有価証券とみなされるもの(以下、みなし有価証券)のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいいます。
なお、一部の論点については実務対応報告第43号では取り扱わず、22年3月15日に企業会計基準委員会(以下、ASBJ)より公表された「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」において今後の方向性に関する予備的な分析がされています。こちらについては、本誌22年6月号をご参照ください。
2. 発行及び保有の会計処理
電子記録移転有価証券表示権利等は、その発行及び保有がいわゆるブロックチェーン技術等を用いてなされる点を除けば、従来のみなし有価証券と権利の内容は同一であると考えられるため、電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理は、基本的に従来のみなし有価証券の発行及び保有の会計処理と同様に取り扱います。
ただし、発生及び消滅の認識の会計処理については、一部別途の定めが置かれており、会計処理の概要は<表2>をご参照ください。金融商品取引法に定義する有価証券に該当しても、信託受益権については、優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合などを除いて、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、金融商品会計基準)や会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、金融商品実務指針。また、金融商品会計基準及び金融商品実務指針を合わせて、以下、金融商品会計基準等)上の有価証券として取り扱わないものとされているため、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合と該当しない場合とに分けて会計処理が整理されています。
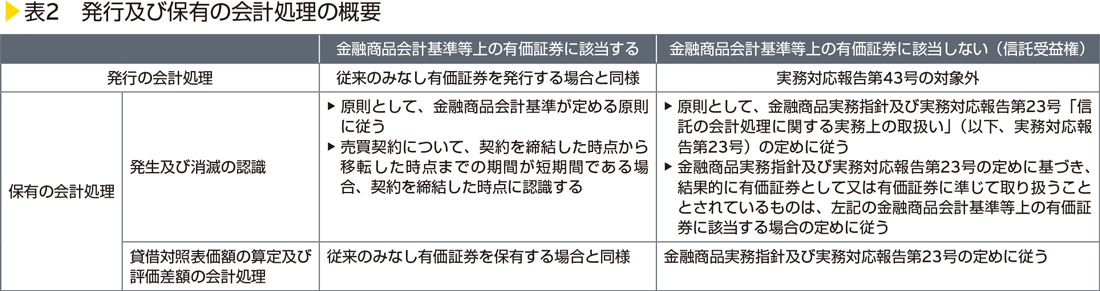
3. 四半期における開示
電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の表示方法及び注記事項は、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合に求められる表示方法及び注記事項と同様とされています。このため、電子記録移転有価証券表示権利等は、従来のみなし有価証券に含めて貸借対照表に表示し、四半期において金融商品に関する注記事項を開示する場合には、当該注記においても従来のみなし有価証券に含めて注記することになります。
また、この第1四半期決算から実務対応報告第43号を原則適用する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として注記することになります(企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬(びゅう)の訂正に関する会計基準」(以下、過年度遡(そ)及会計基準)10項)。なお、実務対応報告第43号においては、特定の経過的な取扱いが定められていないため、従前から電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合には、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになります(過年度遡及会計基準6項(1))。
Ⅲ 改正法人税等会計基準等
22年10月28日にASBJより法人税等会計基準、包括利益会計基準、税効果適用指針(これらを合わせて以下、改正法人税等会計基準等)の改正が公表されています(<表1>参照)。これらの適用時期は<表3>のとおりであり、24年3月期第1四半期決算から早期適用が可能となっています。
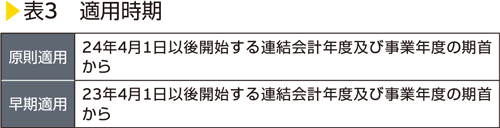
1. 主な改正内容
主な改正内容は<表4>のとおり2点あり、それぞれについて解説していきます。なお、改正内容の詳細については、設例も踏まえて解説している本誌22年8月・9月合併号も併せてご確認ください。
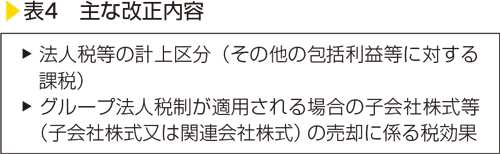
2. 法人税等の計上区分に関する改正
(1) 改正前の会計処理と問題点
例えば、その他有価証券の時価評価に伴う評価差額や、ヘッジ会計における繰延ヘッジ損益などその他の包括利益に計上された取引又は事象(以下、取引等)が課税所得計算上の益金又は損金に算入され、法人税、住民税及び事業税等(以下、法人税等)が課せられる場合があります。
改正前の法人税等会計基準では、当事業年度の所得等に対する法人税等は、法令に従い算定した額を損益に計上することとしていたため、このような取引等についてはその他の包括利益に計上される一方で、これに対して課せられる法人税等は損益に計上されていました。
したがって、税引前当期純利益と税金費用の対応関係が図られていないのではないかという問題点が指摘されていました。
(2) 改正後の会計処理
改正後の法人税等会計基準では、当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとされました。なお、株主資本又はその他の包括利益に計上される取引等の例示は<表5>の通りです。
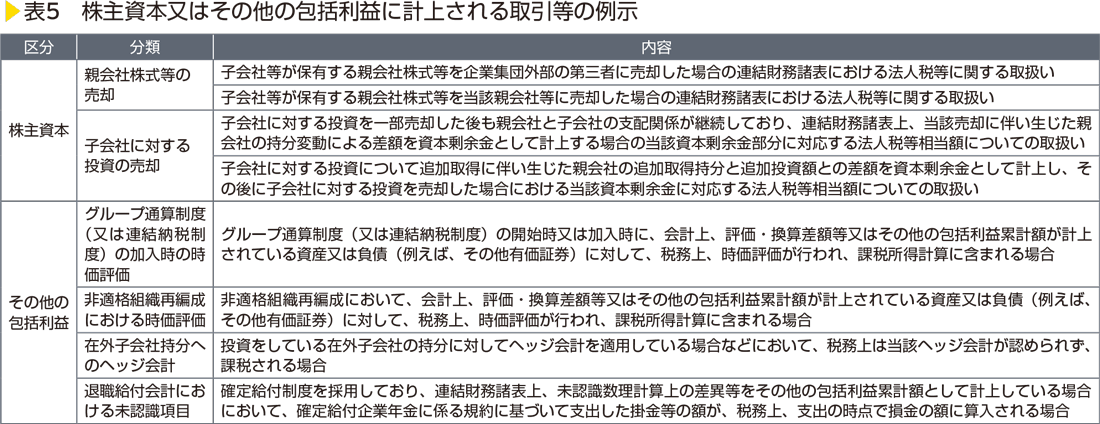
3. グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果に関する改正
(1) 税務上の取扱い
税務上、内国法人が有する譲渡損益調整資産(有価証券等)を他の完全支配関係がある内国法人に譲渡した場合には、グループ法人税制が適用され、課税所得計算上、譲渡時点において売却損益を計上せず、繰り延べられることとされています。そして、当該繰り延べられた売却損益については、譲受法人において、当該資産の譲渡等の事由が生じたときに、譲渡法人の課税所得計算上、売却損益を益金の額又は損金の額に算入することとされています。
(2) 改正前の会計処理
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、改正前の税効果適用指針39項では、当該子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表において、当該売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額は修正しないこととされていました。つまり、売却益が計上されることを前提とすると、個別財務諸表では売却益に対応して繰延税金負債が計上されますが、連結財務諸表上は内部取引であることから売却益が消去され、また、税務上も売却益が繰り延べられるため課税されていないにもかかわらず、連結財務諸表上は税金費用及び繰延税金負債が計上される結果となっていました。
(3) 改正後の会計処理
(連結財務諸表の取扱い)
連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合、当該売却に係る連結財務諸表上の税引前当期純利益と税金費用との対応関係の改善を図る観点から、連結財務諸表において<表6>の処理を行うこととされました。
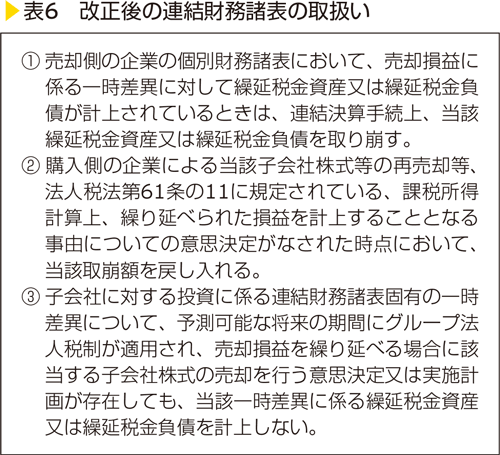
(個別財務諸表の取扱い)
個別財務諸表においては、連結財務諸表とは異なり、売却損益が消去されないことから、税金費用を計上しないこととした場合には税引前当期純利益と税金費用との対応関係が図られないこととなると考えられます。したがって、改正前の取扱いを見直さないこととされています。
4. 会計方針の変更の注記及び経過措置
この第1四半期決算から改正法人税等会計基準を早期適用する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として注記することになります(法人税等会計基準20-3項、税効果適用指針65-2項、過年度遡及会計基準10項)。
なお、改正法人税等会計基準の適用初年度においては、原則として、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用することとされています。ただし、法人税等の計上区分については、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができることとする経過的な取扱いが定められています(<表7>参照)。
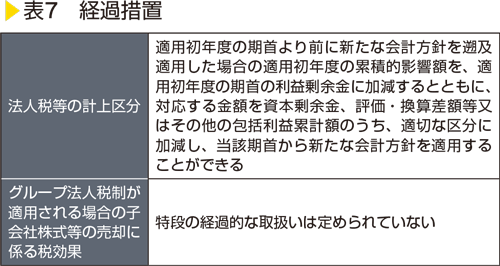
Ⅳ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い
1. グローバル・ミニマム課税制度の税効果会計への影響
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下、グローバル・ミニマム課税制度)を含めた改正法人税法が23年3月28日に成立しています。
グローバル・ミニマム課税制度の適用は24年4月1日以後開始する事業年度からとされていますが、その適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む)において、税効果適用指針の定めに基づき、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要があります。
しかしながら、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であるとの意見が聞かれたことから、ASBJより、23年3月31日に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(以下、実務対応報告第44号)が公表され、当該公表日以後適用されています。
なお、グローバル・ミニマム課税制度の具体的な内容については、EY税理士法人「令和5年度税制改正大綱(詳細版)」をご参照ください。
2. 実務対応報告第44号の概要
(1) 範囲
グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後その適用が見込まれるか否かの判断について、企業が適時にかつ適切に行えるか懸念があるとの意見が聞かれたことを踏まえ、実務対応報告第44号では、企業会計審議会が1998年10月に公表した「税効果会計に係る会計基準」が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表において、一律に適用するとされています(実務対応報告第44号2項)。
(2) 会計処理及び開示
ASBJが実務対応報告第44号の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む)における税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととされています(実務対応報告第44号3項)。
これは、税効果会計は利益に関連する金額を課税標準とする税金を対象として認識するものですが、グローバル・ミニマム課税制度に基づいた基準税率(15%)までの上乗せ税額は、親会社等がその所在地国の税務当局に支払うものであるため、課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業とが相違することとなり、税効果会計を適用すべきか否か等が明らかではないことや、実務上の負担も想定されることなどから特例的な取扱いが定められたものとなります。
このため、24年3月期第1四半期決算においても、23年3月期と同様に、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映せず、税効果会計を適用することになります。
なお、グローバル・ミニマム課税制度の影響が見込まれる企業において実務対応報告第44号を適用した旨を注記することも考えられますが、企業がグローバル・ミニマム課税制度の施行日以後その適用が見込まれるか否かの判断を適時にかつ適切に行うことについて懸念があるとの意見が聞かれたため、実務対応報告第44号の適用に関する開示は求めないこととされています。
(3) 適用期間
実務対応報告第44号の特例的な取扱いは、グローバル・ミニマム課税制度の具体的な内容やグローバル・ミニマム課税制度の適用を前提として税効果会計を適用すべきかどうかが今後明らかになるまでの当面の取扱いであるため、適用期間は、ASBJが実務対応報告第44号の適用を終了するまでの間とされています。
このため、ASBJより公表されている「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」では、法人税等会計基準及び税効果適用指針等の会計基準等の改正の要否について、今後、検討することを予定しているとされています。
Ⅴ 第1四半期決算でよくある検討ポイント
年度開始に合わせて企業内の組織変更や合併などの組織再編が行われることも多く、これらに関連するさまざまな論点について、第1四半期で検討が必要となることが多くあります。また、年度決算の観点でも、第1四半期のタイミングで検討しておくべき論点もあります。そこで、本章では、第1四半期決算において特に検討が必要と考えられる論点をいくつか取り上げて解説します(<表8>参照)。
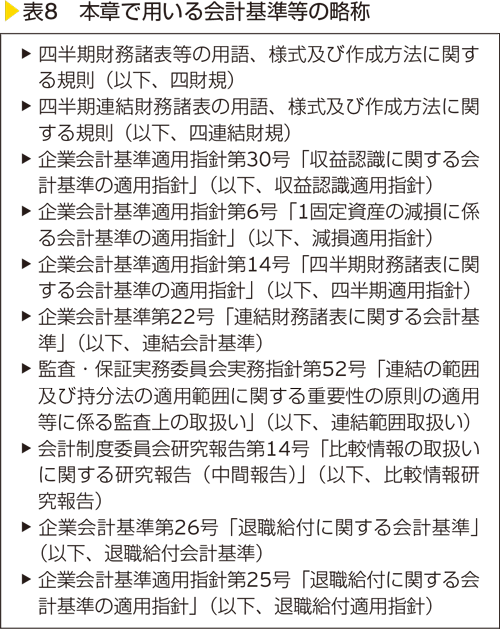
1. セグメント情報
企業の管理手法が変更されたことに伴い、報告セグメントの区分方法を変更する場合には、前年同四半期累計期間について、変更後の区分方法により作り直したセグメント情報の開示が求められており、当該開示が困難な場合には、前年度の区分方法により作成した当四半期累計期間の情報を開示することも認められています(四財規様式一号(記載上の注意)8(2)、四連結財規様式一号(記載上の注意)8(2))。年度開始に合わせて、企業内の組織変更等が行われることも多いですが、第1四半期においては、組織変更や管理手法の変更の有無及びその変更が報告セグメントの区分方法に影響するか否かを検討する必要があります。
また、収益の分解情報に関する注記(四財規22条の4第1項、四連結財規27条の3)の記載に際して、収益の分解に用いる区分は、最高経営意思決定機関が事業セグメントに関する業績評価を行うために定期的に検討している情報も考慮することとされています(収益認識適用指針106-4項(2))。このため、報告セグメントの区分方法を変更する場合に、事業セグメントの業績評価のために検討している情報にも変化があれば、収益の分解に用いる区分への影響についても留意する必要があると考えられます。
2. 四半期における固定資産の減損会計
(1) グルーピング
減損会計の資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされており、実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることとされています(減損適用指針7項)。この取扱いは、四半期も年度も同様です。
当期に行われた資産のグルーピングは、原則として、翌期以降の会計期間においても同様に行うとされていますが(減損適用指針9項)、グルーピングは経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行う必要があり(減損適用指針7項)、事業の再編成による管理会計上の区分の変更、主要な資産の処分、事業セグメントの区分方法の変更など、事実関係が変化した場合には、グルーピングの変更が行われるものとされています(減損適用指針74項)。ただし、例えば、管理会計上の区分を形式的に変更すれば、連動してグルーピングの見直しが行われるわけではなく、グルーピングの基礎となる事実関係の変化に伴って独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位が実態として変化している場合に、グルーピングの見直しが必要になると考えられます。
第1四半期において、組織変更等に伴いグルーピングの基礎となる事実関係が変化した場合には、グルーピングの見直しを検討するに際して、当該事実関係の変化に伴って独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位の実態が変化しているかどうかに留意する必要があります。
(2) 減損の兆候
① 減損の兆候に関する簡便的な取扱い
減損の兆候は、通常の企業活動において、実務的に入手可能なタイミングで利用可能な情報に基づき検討することとされています(減損適用指針11項)。この趣旨を踏まえ、前年度末等において所有する資産又は資産グループについて全体的に減損の兆候を把握している場合には、四半期における減損の兆候を把握するに際して、必ずしも四半期ごとに資産又は資産グループに関連する営業損益、営業キャッシュ・フローあるいはその市場価格を算定又は入手することまでは求められておらず、使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生したかどうかについて、留意することとされています(四半期適用指針14項、92項)(<表9参照>)。
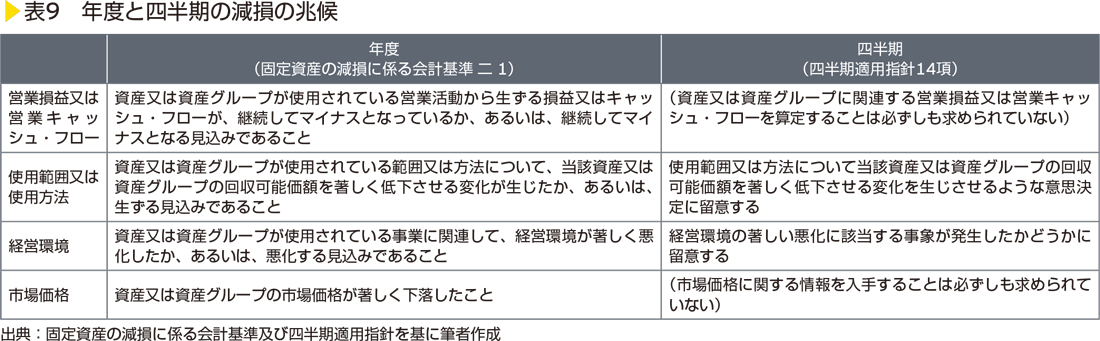
ただし、四半期においても、資産又は資産グループに関連する営業損益等の管理資料が利用可能である場合には、当該資料に基づき減損の兆候を検討する必要があると考えられます。また、市場価格に関しても、例えば、減損の兆候を把握するための市場価格として一定の指標を使用しており、期中に当該指標の改定が行われる場合には、指標が改定された四半期において、市場価格に基づく減損の兆候の検討を行うことが考えられます。
② 前期末に減損の兆候を識別したものの減損損失を計上しなかった場合の取扱い
前期末に減損の兆候を識別したものの、減損の認識の判定を行った結果、減損損失を計上しなかった場合には、減損の兆候があったという点で、減損の兆候がなかった他の資産又は資産グループよりも減損損失計上のリスクは高いことから、四半期においても慎重に検討すべきであると考えられます。特に、前期末において、減損の兆候はあるが減損を認識しなかった資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りに関する事項を、会計上の見積りに関する注記に記載している場合やKAM(監査上の主要な検討事項)の対象になっている場合には、四半期においても計画と実績とを比較し、前期末における将来キャッシュ・フローの見積りのベースとなる事業計画からの乖かい離が生じていないかどうかを確認し、乖離が生じている場合にはその原因を分析した上で、当四半期において減損の兆候を識別すべきか否かを慎重に検討する必要があると考えられます。
(3) 減損損失の認識・測定
減損の兆候の検討については、前述①のとおり、四半期適用指針において別段の定めが設けられていますが、減損損失の認識の判定や減損損失の測定については、別段の定めは設けられていません。このため、四半期において減損の兆候が識別された場合、減損損失の認識及び測定を簡便的に行うことは認められず、減損適用指針の定めに従い会計処理を行うことになると考えられますので、留意が必要です。
3. 連結の範囲
親会社は、原則として全ての子会社を連結の範囲に含めなければならないとされていますが、資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとされています(連結会計基準13項、注3)。
連結範囲の重要性の判断にあたっては、量的側面と質的側面の両面で判断されるべきであり、量的な重要性が乏しいという判断だけで連結の範囲から除外することができない子会社も存在する可能性があります(連結範囲取扱い3項)。例えば、<表10>にある子会社については、量的な重要性が乏しい場合であっても、原則として非連結子会社とすることはできません(連結範囲取扱い4-2項(2))
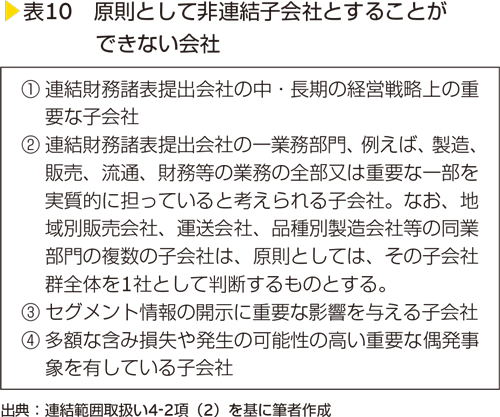
ここで、第1四半期には重要性がない子会社でも、年度末までに重要性が高まることが見込まれているような場合には、そのような質的側面に鑑みて、第1四半期から連結の範囲に含めることが考えられます。なお、比較情報研究報告Q4のAでは、非連結子会社として取り扱っていた子会社について、第2四半期連結累計期間から重要性が高まったため、連結子会社として取り扱うことになる場合でも、当該子会社の期首からの損益を取り込むこととされています。しかし、このようなケースは、第1四半期には予測できなかったような事態が第2四半期以降に発生し重要性が高まった場合(例えば、第2四半期において、連結子会社が災害等により損失を被った影響で、非連結子会社としていた会社の重要性が相対的に高まった場合)等の例外的なケースであると考えられます。
このため、第1四半期において連結の範囲を検討する際には、第1四半期末における状況だけでなく、年度末までに重要性が高まる可能性のある子会社がないかという点も考慮して、慎重に検討する必要があります。
4. 長期期待運用収益率の見直しの検討
当年度の退職給付費用の計算に用いられる長期期待運用収益率は、当期損益に重要な影響があると認められる場合のほかは、見直さないことができるとされています(退職給付適用指針31項)。見直しを行う時期は明記されていないものの、期待運用収益は、期首の年金資産の額に長期期待運用収益率を乗じて計算する(退職給付会計基準23項)こととされているため、原則的に期首に見直しを行うものと考えられます。したがって、第1四半期決算において、長期期待運用収益率の見直しの要否を検討する必要があると考えられます。
長期期待運用収益率は、年金資産が退職給付の支払に充てられるまでの時期、保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮して設定することとされています(退職給付適用指針25項)。長期期待運用収益率の見直しを検討するにあたっては、前年度の運用利回り実績も1つの考慮要素となりますが、直近の運用実績だけに基づき短期的に見直しを行うようなものではなく、長期的な観点で検討することが求められる点に留意が必要です。
なお、どのような場合であれば「当期損益に重要な影響がある」と認められるのかについては、退職給付会計基準等では示されていないことから、各社において重要性に関する合理的な基準を設定するものと考えられます。
- YouTubeで動画配信中
2024年3月期第1四半期の主な決算上の留意事項
「情報センサー2023年7月号 会計情報レポート」をダウンロード
関連コンテンツのご紹介
アシュアランスサービス
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
税務会計
EYの税務会計プロフェッショナルが、現代の税務環境で必要とされる複雑な要求事項の管理をサポートします。
企業会計ナビ
EY新日本有限責任監査法人より、会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。



