EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2018年12月号 押さえておきたい会計・税務・法律
公認会計士 太田 達也
当法人のフェローとして、法律・会計・税務などの幅広い分野で助言・指導を行っている。また、豊富な知識・経験および情報力を生かし、各種実務セミナー講師、講演等において活躍している。著書は多数あるが、代表的なものとして『会社法決算書作成ハンドブック』(商事法務)、『「純資産の部」完全解説』『「解散・清算の実務」完全解説』『「固定資産の税務・会計」完全解説』(以上、税務研究会出版局)、『例解 金融商品の会計・税務』(清文社)、『減損会計実務のすべて』(税務経理協会)などがある。
Ⅰ はじめに
100%子会社を解散・清算する場合、会計処理だけでなく、税務上の取扱いとの関連を考慮する必要があります。また、解散する前の段階で、親会社において子会社株式の減損をしているケースも少なくなく、その場合の処理についても、十分な理解・整理が必要です。
本稿では、100%子会社の解散・清算に係る会計処理、税務処理について、詳しく解説します。
Ⅱ 100%子会社を解散・清算したときの親会社の会計処理
親会社において子会社株式の減損をしていなかった場合は、子会社の清算結了に伴い、子会社株式の帳簿価額を消却損として損失に計上することが考えられます。
一方、業績の悪化に伴い解散する場合、親会社において子会社株式の減損を行っていることが考えられます。減損後の帳簿価額を消却損として計上することになりますが、ゼロ円まで減損している場合は、消却損は計上されません。
Ⅲ 子会社を解散・清算したときの親会社の税務処理
子会社に残余財産が残り、親会社に分配した場合は、税務上、「資本の払戻し」として取り扱われますので(法法24条1項4号)、資本金等の額の減少と、それを超えて分配がされたときはその超える額が利益積立金額の減少として取り扱われます。その利益積立金額の減少部分が、いわゆる「みなし配当」になります。
ただし、親会社と子会社との間に完全支配関係があるときは、みなし配当に係る親会社における受取配当金は全額益金不算入とされ(法法23条1項)、また、株式の譲渡損益は不計上とされますので(法法61条の2第17項)、親会社の所得には影響がありません。
また、残余財産の分配がない場合は、親会社の有する子会社株式の(税務上の)帳簿価額相当額を資本金等の額の減少として処理します(法令8条1項22号)。損金算入されない点に留意する必要があります。
以上の会計処理と税務処理との関係について、次の設例を参考としてください。
設例1 100%子会社の解散・清算に係る会計・税務処
- 前提条件
当社(甲社)の100%子会社乙社は、ここ数年業績が悪化していました。X1期に、乙社の資産状態が著しく悪化しているため、乙社株式(帳簿価額1,000万円)をゼロ円まで減損しましたが、税務上は損金算入要件を満たしていないと判断し、自己否認しました。
X2期に、業績の改善の見通しも立たないことから、乙社を解散・清算することを決定しましたが、当社としては乙社株式を売却する計画はなく、清算結了まで保有し続ける方針です。X3期に、乙社の残余財産の分配がないことが確定し、清算結了に至りました。
X1期からX3期までのそれぞれの事業年度における当社の会計処理、税務処理および別表の記載を示してください。当社と乙社との間には、完全支配関係があります。なお、当社は税効果会計を適用しており、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」における分類1の会社です。法定実効税率を30%とします。
X1期の会計・税務処理
1. 会計処理
税務上は損金不算入ですので、将来減算一時差異が1,000発生します。法定実効税率30%を乗じた額を繰延税金資産として計上します。
2. 税務処理
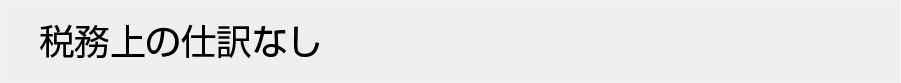
税務上は、子会社株式評価損は損金不算入と判断され、自己否認していますので、仕訳なしです。
3. 別表の記載
別表四で1,000万円を加算(留保)し、別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」の増加欄に同額を記載します。別表五(一)の調整は、子会社株式に係る会計上の帳簿価額(ゼロ円)と税務上の帳簿価額(1,000万円)との差異を表しています。この差異は、税効果会計における将来減算一時差異に該当します。繰延税金資産および法人税等調整額に係る申告調整も、併せて別表四および別表五(一)に記載しています。
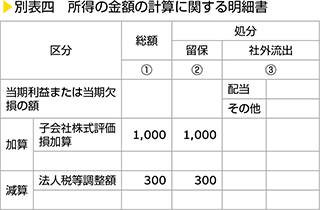

X2期の会計・税務処理
1. 会計処理
平成30年2月16日付で、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の一部改正が公表されました。完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される可能性が低い場合には、分類1であっても、当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することが適切であるとの考え方を明らかにする改正が行われました。
本事例は、完全支配関係がある子会社の解散・清算であって、かつ、清算結了まで子会社株式を保有し続ける方針ですので、繰延税金資産の回収可能性はないと判断されます。繰延税金資産を取り崩します。
2. 税務処理
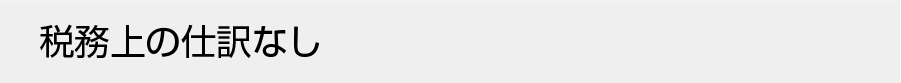
3. 別表の記載
繰延税金資産の取崩しに対応する別表の調整を示します。


X3期の会計・税務処理
1. 会計処理
会計上は、X1期に子会社株式を帳簿価額ゼロまで減損していますので、子会社が清算結了となったX3期に仕訳は発生しません。
2. 税務処理
税務上は、子会社株式の消却損は損金不算入とされ(法法61条の2第17項)、子会社株式の帳簿価額相当額について、資本金等の額の減算として処理します(法令8条1項22号)。
3. 別表の記載
会計上の損益および税務上の所得に影響はありませんので、別表四の記載は必要なく、別表五(一)に次のように記載します。

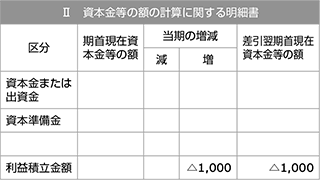
会計上は、X1期に減損しており利益剰余金が減少しましたが、税務上はX3期の子会社の残余財産の確定に伴い資本等取引として資本金等の額の減少として処理する違いが生じます。要するに、会計上は損益取引として処理したのに対して、税務上は資本等取引として処理したことになります。結果として、「利益積立金額の計算に関する明細書」と「資本金等の額の計算に関する明細書」にプラス・マイナス1,000万円の振替調整を入れることになりますが、この調整は残ります。この差異は、会計と税務のルールの差異に基づくものであり、永久に解消されない差異ですので、税効果会計の対象にはなりません。
Ⅳ その他の税務上の論点
1. 繰越欠損金の引継ぎ
完全支配関係がある子会社の残余財産が確定した場合、その子会社の繰越欠損金のうち未使用のものが、原則として、その親会社に引き継がれます(法法57条2項)。異なる会社間で繰越欠損金の引継ぎが行われるのは、①適格合併とこの②完全支配関係がある子会社の残余財産の確定の二つのケースになります。
平成22年度税制改正のときに、グループ法人税制が導入されましたが、完全支配関係がある法人を一体であると捉える考え方から、子会社株式の消却損は損金不算入とされる一方において、この取扱いが定められたものです。
なお、親会社が子会社から繰越欠損金を引き継ぐ場合は、別表七(一)付表1を記載することになりますが、その添付書類として、子会社の最後事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度)の確定申告書に添付された別表七(一)の写しを添付する必要があります。また、地方税の申告においても第6号様式の別表九に併せて別表十二「適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書」および子会社の最後事業年度の確定申告書に添付された第6号様式の別表九の写しを添付する必要があります。
2. 適格現物分配
(1) 適格現物分配の定義
残余財産の分配は、みなし配当事由(法法24条1項4号)であるため、現物資産により残余財産の分配をしたときは、税務上の現物分配に該当します。適格要件を満たした現物分配である場合に、税務上の適格現物分配に該当します。
適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人または協同組合等に限る)のみであるものをいいます(法法2条12号の15)。この規定から、現物分配を受ける株主の中に個人株主が1名または外国法人が1社でも存在するときは、適格現物分配に該当しないことになる点に留意する必要があります。
また、適格要件を満たすかどうかは、「現物分配の直前において現物分配法人との間に完全支配関係がある法人のみである」のかどうかで判定されるため、適格合併や適格分割のように、再編後において完全支配関係または支配関係の継続が見込まれることという要件は付されていない点に留意が必要です。従って、完全支配関係がある法人間における残余財産の現物分配のように、現物分配後において清算結了により現物分配法人が消滅することが予定されている(完全支配関係が解消することが見込まれている)場合にも、適格性には影響がありません。
(2) 適格現物分配の処理
適格現物分配により、現物分配法人から被現物分配法人に対して現物資産が移転する場合、現物分配法人は帳簿価額により資産を譲渡したものとして処理します(法法62条の5第3項)。従って、譲渡損益は計上されません。現物分配は、合併、分割等の他の組織再編行為と異なり、譲渡法人側に課税の繰延べポジションが残らない取引、いわば手仕舞い型の取引であるため、含み損益に係る繰延処理等の申告調整等は不要です。
一方、被現物分配法人においては、その現物分配法人における現物分配直前の帳簿価額で当該資産を受け入れることになります(法令123条の6第1項)。残余財産の分配は、税務上、「資本の払戻し」ですので、現物分配法人において資本金等の額の減少と、それを現物資産の帳簿価額がそれを超えた額について利益積立金額の減少を認識しますが、利益積立金額の減少部分が、いわゆる「みなし配当」になります。被現物分配法人において利益積立金額の増加を認識します(法令9条1項4号)。この場合、受取配当等の益金不算入の規定(法法23条1項)の適用を受けず、適格現物分配に係る益金不算入規定の適用を受ける(法法62条の5第4項)ことにより、全額益金不算入となります。従って、別表八(一)の記載は不要です。
なお、具体的な設例については、紙面の関係もあるため、拙著『「解散・清算の実務」完全解説』(税務研究会出版局)を参照してください。
(注) 文中、法令条文等は、以下のとおり略して記載しています。
法法:法人税法
法令:法人税法施行令情



