EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2016年12月号 会計情報レポート
第5事業部 公認会計士 浅井哲史
監査事業部所属。現在は、主に旅客運輸業、情報サービス業等の国内事業会社の監査業務や米国基準に準拠した財務諸表の監査業務に従事する一方、研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務にも従事。主な著書(共著)に『こんなときどうする?減損会計の実務詳解Q&A』『会社法決算書の読み方・作り方(第10版)』(いずれも中央経済社)などがある。
Ⅰ はじめに
固定資産の減損会計に関する実務上の論点を分かりやすく解説する本シリーズの第2回である今号では、減損損失の認識及び回収可能価額の算定に関する実務論点を取り上げます。なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りします。
Ⅱ 減損損失の認識に関する実務論点
1. 減損損失の認識の判定の基本的考え方
固定資産の減損に係る会計基準(以下、減損基準)は、資産又は資産グループごとに減損の兆候を把握し、減損の兆候がある場合には減損損失の認識の有無を判定することを求めています。減損損失の認識の判定において、帳簿価額と毎年の割引前将来キャッシュ・フローの合計を比較し、帳簿価額の方が大きければ減損損失を認識し、回収可能価額まで帳簿価額を減額する(減損損失の測定を行う)ことになります。そのため、減損損失の認識の判定(及び測定)は、将来キャッシュ・フローの見積り結果に大きく依存します。
2. 将来キャッシュ・フローの見積り
将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、まず主要な資産の特定を行う必要があります。以下、主要な資産の特定等に関する論点を説明し、その後に将来キャッシュ・フローの算定に当たっての実務上の留意事項について解説します。
(1) 主要な資産の決定
一般的には、製造業を営み工場設備を保有している企業では、固定資産全体に占める機械装置の金額的重要性が高くなり、不動産業などの業種では土地、建物等の金額的重要性が高いと想定されます。主要な資産とは、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産(減損基準注解(注3))とされていますが、固定資産の構成比率が大きい資産が必ずしも主要な資産に該当するわけではありません。土地、建物、機械装置等でどれが主要な資産に該当するかは、企業の置かれている経営環境によって異なると考えられます。
例えば、労働集約的な工場のようなケースでは、安価で安定的な労働力を確保するために、ヒトや設備を集約できる土地等の取得が優先される場合があります。そのような場合には、機械装置よりも土地等が資産グループの将来キャッシュ・フローの生成能力にとって、より重要な資産と判断されるケースがあります。一方、高度に自動化された工場では、製品の生産にとって機械装置の性能が重要な要素であり、かつ、容易に代替ができない場合があります。また、どの資産も事業運営にとっては重要であるとして、主要な資産を決定すること自体が困難な場合が考えられます。
減損基準や固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(以下、減損指針)には、主要な資産の判定に際し、具体的な数値基準が存在するわけではないため、実務上は、企業の実情に応じて合理的と考えられる資産を決定することになりますが、事業運営にとって不可欠であるかどうかといった点や、物理的及び経済的に容易に取り替えできるかどうかといった点(減損指針23項)に加え、キャッシュ・フロー生成への貢献の状況等を踏まえて総合的に判断することが求められると考えられます。なお、共用資産やのれんは、原則として主要な資産には該当しません(減損指針24項)。
(2) 主要な資産の経済的残存使用年数の把握
将来キャッシュ・フローの総額の見積期間は、主要な資産の経済的残存使用年数によって決定されます。将来キャッシュ・フローは、主要な資産の経済的残存使用年数経過時点までに獲得するキャッシュ・フローですが、経済的残存使用年数が20年を超える場合には、21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに基づいて、20年経過時点の回収可能価額(20年経過時点の正味売却価額または使用価値)を算定し、20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算します(減損基準二 2(2)、減損基準注解(注4))。
なお、主要な資産が土地と判定された場合は、土地は使用期限が無限であるため、20年を上限として将来キャッシュ・フローを見積ることになります(減損指針96項)。
(3) 将来キャッシュ・フローの見積りに当たっての実務上の留意事項
① 現在の使用状況や合理的な使用計画の考慮
計画されていない将来における設備投資や事業再編等により生ずる将来キャッシュ・フローを見積りに含めることはできません(減損基準注解(注5))。設備の増強は見込まれていないものの、資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮した結果、現在の資産グループの価値を維持するための支出については、見積りに含めることが求められます。例えば、主要な資産が土地であり、20年の将来キャッシュ・フローを見積る場合に、他の構成資産の経済的残存使用年数が15年であれば、15年経過時点で現在の価値を維持するための合理的な設備投資を織り込む必要があります。
一方、将来の設備投資や事業再編が計画されている場合には、当該計画を将来キャッシュ・フローの見積りに反映することになります。例えば、新たなビジネスを開始した会社で、現状は広告宣伝や開発コスト等の負担が大きく営業損益及びキャッシュ・フローがマイナスとなっているものの、市場成長率の裏付けや保有する技術力を背景に、新たに販売拡大のための戦略的かつ積極的な設備投資を行う具体的な計画がある場合、将来の設備投資に係るキャッシュ・アウト・フロー及び業況拡大に伴う追加キャッシュ・イン・フローを見積りに織り込むことになります。
② 複数の見積方法(単一の見積りと複数の見積り)
将来キャッシュ・フローの見積方法には、生起する可能性が最も高い単一の金額(最頻値)を見積る方法と、生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額(期待値)を見積る方法があります。将来計画等に基づき、単一の金額を見積る方法をとることが実務上は多いと考えられますが、固定資産の使用ないし処分に関して複数の選択肢を検討している状況では、将来生じ得る複数のキャッシュ・フローの幅を考慮した期待値による方が有用である場合も考えられます。そのため、複数の選択肢を生起する確率で加重平均した結果を見積ることも認められます(減損基準二 4(3))。
なお、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離(かいり)するリスクを将来キャッシュ・フローの見積り結果に反映させることは必ずしも求められてはいません。しかし、乖離するリスクを将来キャッシュ・フローの見積りに織り込んでいない場合には、減損損失の測定の際に用いる使用価値の算定における割引率に当該リスクを反映させる必要があり、実務上は割引率に反映させる方法を用いる場合が多いと考えられます(減損指針39項参照)。
③ 合理的で説明可能な仮定及び予測の実施
実務では、将来数値の根拠を中長期の経営計画等に求めることが考えられますが、一般的に長期の経営計画を策定している会社は少ないと考えられます。そのため、中期経営計画に基づき、長期の予測を行うケースが多いと考えられます。
なお、見積将来キャッシュ・フローが将来の買収等の期待を含めた内容になっている場合には、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいていることの要件が備わっていないと考えられます。さらに、将来高い成長率が期待されるとして、かなり右肩上がりの将来キャッシュ・フローとなっている場合には、過去及び現在の経済環境からみて予測が妥当なものかを説明できない場合が多いのではないかと考えられます。合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいていることの要件の検討に当たっては、営業活動から生じている損益等が継続してマイナスであるかなど、減損の兆候の判定で把握された事象に基づく判断が加味される必要があると考えます(減損指針36項参照)。
減損の兆候があると判定した要因と、それに基づく減損損失の認識の判定における考慮要素を示すと、<表1>のようになります。
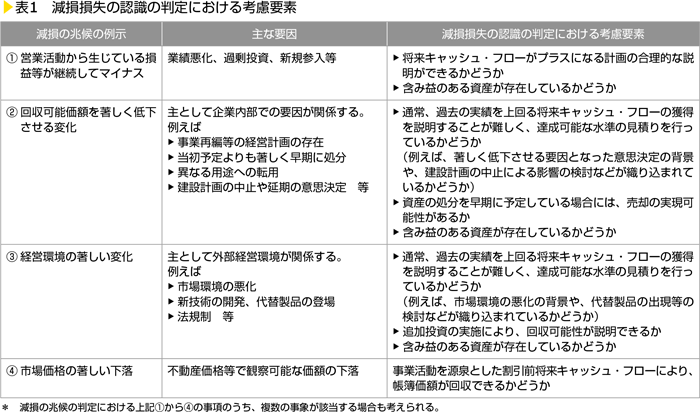
Ⅲ 回収可能価額の算定に関する実務論点
1. 回収可能価額の算定の基本的考え方
減損の兆候がある資産または資産グループが、減損損失の認識の判定の結果、減損損失を認識すべきと判定された場合は、減損損失の測定を行います。減損損失は、資産または資産グループの帳簿価額と回収可能価額の差額となります(減損基準二 3)。
(1) 回収可能価額の算定
回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方とされています。
ここで、正味売却価額は、資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除した金額と減損基準で定義されており、また、使用価値は資産または資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値と定義されています(減損基準注解(注1))。使用価値は、減損損失の認識段階で利用する将来キャッシュ・フローの割引計算の結果となります。
通常は使用価値が正味売却価額を上回る状況が多いと想定されるため、必ずしも現在の正味売却価額の算定は求められないと考えられますが(減損指針28項)、使用価値の算定に当たって、将来時点における正味売却価額を算定することが求められる場合もあります。その場合には現在の正味売却価額を算定し、それに基づき将来時点における金額を算定することが考えられます。
また減損指針では実務手続の煩雑性等を考慮し、重要性が乏しい資産の正味売却価額についての具体的な取扱いが示されています(減損指針28項、29項、90項等参照)。
(2) 割引率の決定
使用価値は将来キャッシュ・フローの割引計算によって求められるため、割引率の決定が重要な考慮要素となります。実務上多く見られる、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクを割引率に反映させるケースでは、減損指針126項で示されている割引率の例が参考になります(<表2>参照)。
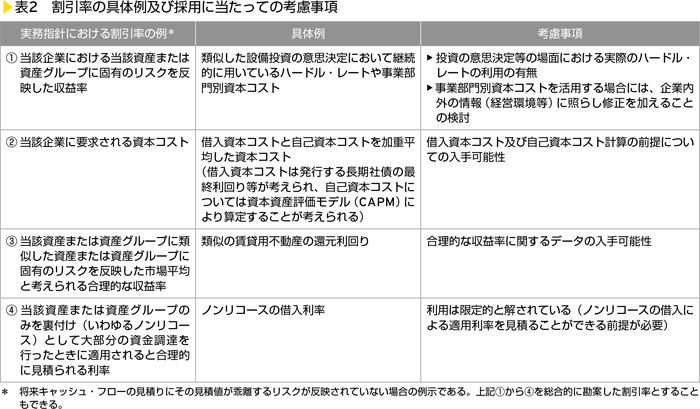
また、割引率の決定に関しては下記の点に留意する必要があります(減損指針43、44)。
- 現在時点(減損損失の測定時点)の割引率を利用
- 通常は単一の割引率を利用
- 税引前の割引率を利用
Ⅳ その他実務上の論点
1. 減損損失の認識と測定段階のそれぞれにおいて、異なる将来キャッシュ・フローを使い分けることができるか
将来キャッシュ・フローは最頻値による方法または期待値による方法で見積ることになり、将来キャッシュ・フローの見積りを認識と測定で使い分けることはできないと考えられます。将来キャッシュ・フローの見積りは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づき最善の見積りを行う必要がありますが、合理的な仮定及び予測の数値化方法が認識段階と測定段階で異なることは、当該仮定か予測の数値化方法のいずれかが最善でないこととなり、認められないと考えられます。
2. 減損損失の認識の判定を経ずに減損損失の測定を行うことができるか
わが国の減損基準の考え方では、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って、減損損失を認識する蓋然(がいぜん)性(確実性)規準として、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回ることを認識要件としていることから、減損損失の認識の要件に該当しない場合には、減損損失を計上することはできないと考えられます。
この点、減損の兆候が存在する場合には、回収可能価額を算定し、資産の帳簿価額がその回収可能価額を上回る場合に、差額を減損損失として認識・測定するという国際財務報告基準(IFRS)と差異が生じており、IFRSを採用したほうが早期に減損損失が計上される場合が多いと考えられます。



