EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2023年7月号 企業会計ナビダイジェスト
EY新日本有限責任監査法人 企業会計ナビチーム 公認会計士 中村 崇
監査部門に所属し、陸運業、建設業などの会計監査に携わる傍ら、書籍執筆、法人ウェブサイト(企業会計ナビ)に掲載する会計情報コンテンツの企画・執筆等に従事している。
今回は「解説シリーズ『持分法』第2回:「持分法の適用範囲」の一部を編集し、紹介します。
Ⅰ 持分法の適用範囲
連結財務諸表上、関連会社及び非連結子会社に対する投資については、原則として持分法を適用します(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下、会計基準)第6項)。
ここでまず関連会社及び非連結子会社とは何か、の定義から確認していきますが、<表1>の企業のことをいいます。なお、「企業」とは、会社及び会社に準ずる事業体をいい、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む)も含まれます(会計基準第4-2項)。
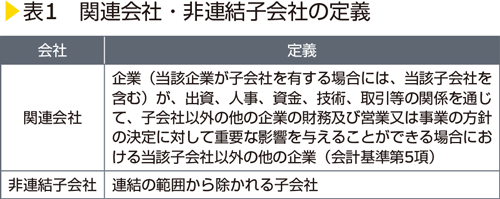
ただし、持分法適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法適用会社としないことができます(会計基準第6項)。
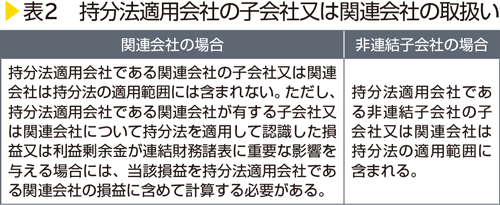
また、持分法適用会社の子会社又は関連会社が持分法適用範囲に含まれるかどうかについては、関連会社であるか非連結子会社かで異なり、<表2>のとおり定められています(会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」(以下、実務指針)第3項)。
Ⅱ 関連会社の判定
Ⅰ.で関連会社の定義を確認しましたが、関連会社の判定は、対象企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して「重要な影響を与える」ことができるかどうかがポイントとなり、実態を踏まえた実質的な判断が求められます。<表3>の場合には、他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して「重要な影響を与える」ことができると判定され、当該他の企業は関連会社に該当します。なお、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除きます(会計基準第5-2項)。
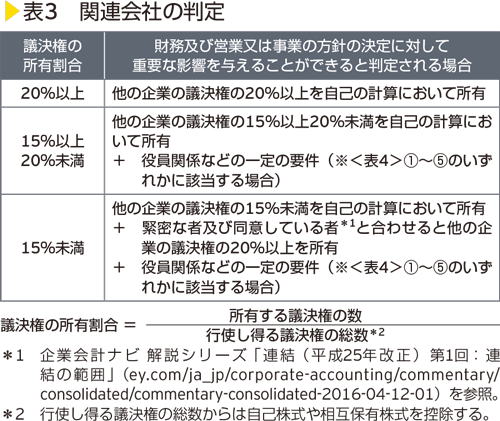
また、<表3>内の※に記載した、役員関係などの一定の要件とは、<表4>の①~⑤をいいます(会計基準第5-2項、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(以下、連結範囲適用指針)第21項~第23項)。議決権の所有割合と<表4>の要件を加味して、「重要な影響を与える」ことができるかどうかを検討します。
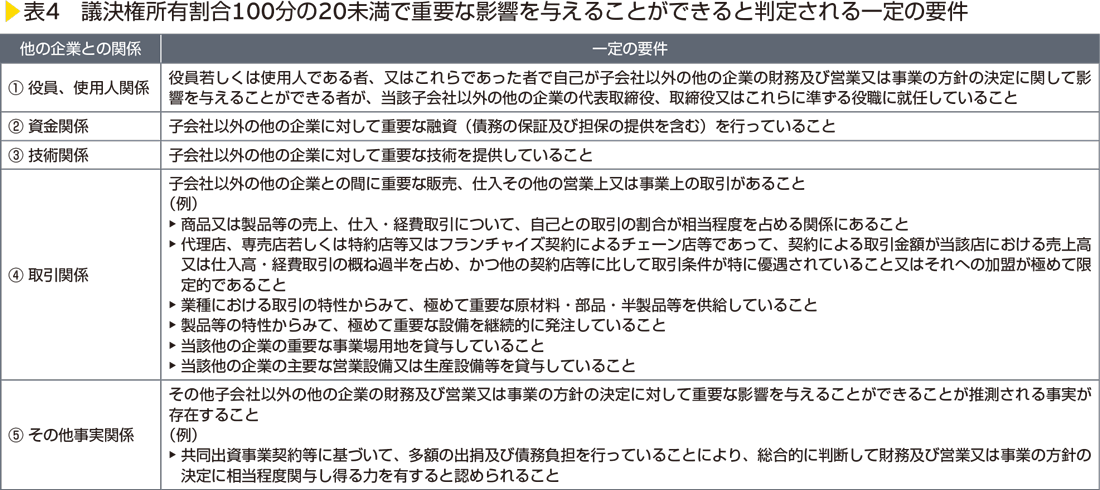
持分法の適用範囲から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えない関連会社及び非連結子会社(以下、関連会社等)の判定は、企業集団における個々の関連会社等の特性(質的重要性)とともに、少なくとも利益及び利益剰余金の2項目に与える影響(量的重要性)をもって判断すべきものと考えられます(監査・保証実務委員会実務指針第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」第5項、第5-2項)。
① 利益基準
持分法非適用の関連会社等の当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計
連結財務諸表提出会社の当期純損益の額、連結子会社の当期純損益の額のうち持分に見合う額並びに持分法適用の関連会社等の当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額
② 利益剰余金基準
持分法非適用の関連会社等の利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額
連結財務諸表提出会社の利益剰余金の額、連結子会社の利益剰余金の額のうち持分に見合う額並びに持分法適用の関連会社等の利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額
当該算式を適用する際は、次の事項に留意します。
① 影響が一時的であるため持分法を適用しない関連会社及び利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため持分法を適用しない関連会社については当該算式には含めません。
② 利益や剰余金の額の小さなものから機械的に順次選定するのではなく、個々の関連会社等の特性や当該算式で計量できない要件も考慮します。例えば、次のような関連会社等は原則として持分法を適用することになります。
- 連結財務諸表提出会社の中・長期の経営戦略上の重要な関連会社等
- 連結財務諸表提出会社の一業務部門、例えば、製造、販売、流通、財務等の業務の全部又は重要な一部を実質的に担っていると考えられる関連会社等
- セグメント情報の開示に重要な影響を与える関連会社等
- 多額な含み損失や発生の可能性の高い重要な偶発事象を有している関連会社等
③ 会社間の取引による資産に含まれる未実現損益を消去後の金額によります。
④ 関連会社等の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合においてその差異が3カ月を超えないときには、連結決算日の最近の事業年度に係る金額によることができます。
⑤ 当期純損益の額が事業の性質等から事業年度ごとに著しく変動する場合には最近5年間の平均を用いる等適宜な方法で差し支えありません。
「情報センサー2023年7月号 企業会計ナビダイジェスト」をダウンロード
関連コンテンツのご紹介
企業会計ナビ
EY新日本有限責任監査法人より、会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。
アシュアランスサービス
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。




