EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

「HRDXの教科書」出版記念セミナー
第1回「HRDXと人間中心社会の実現(2022年1月11日開催)
要点
- 人類は、あくなき欲求、競争原理で生活や経済の成長を実現してきたが、今後は競争だけなく、その先にある共存や自然と融合した社会への対応にも考慮しなければならない。
- 新技術を受容する体制が整う前に物事が進展してしまう現在、「人」を中核とした価値観と、グローバルな視点で共にデザインして創造する参加型の体験共有が求められている。
- 先端科学技術には、倫理的な問題が多分に含まれており、関係者は「責任ある科学技術イノベーション」をコアに、人間中心の考え方で未来世代への責任をつなぐ必要がある。
先ごろ開催した「HRDXの教科書」出版記念セミナー(第1回)では、スイス・ジュネーブ大学や経済協力開発機構(OECD)などでグローバルに活躍してきた原山優子氏(現・国立研究開発法人理化学研究所 理事)をゲストに迎え、「人と技術:古くて新しい関係を世界の潮流から紐解く」と題した基調講演を行っていただきました。
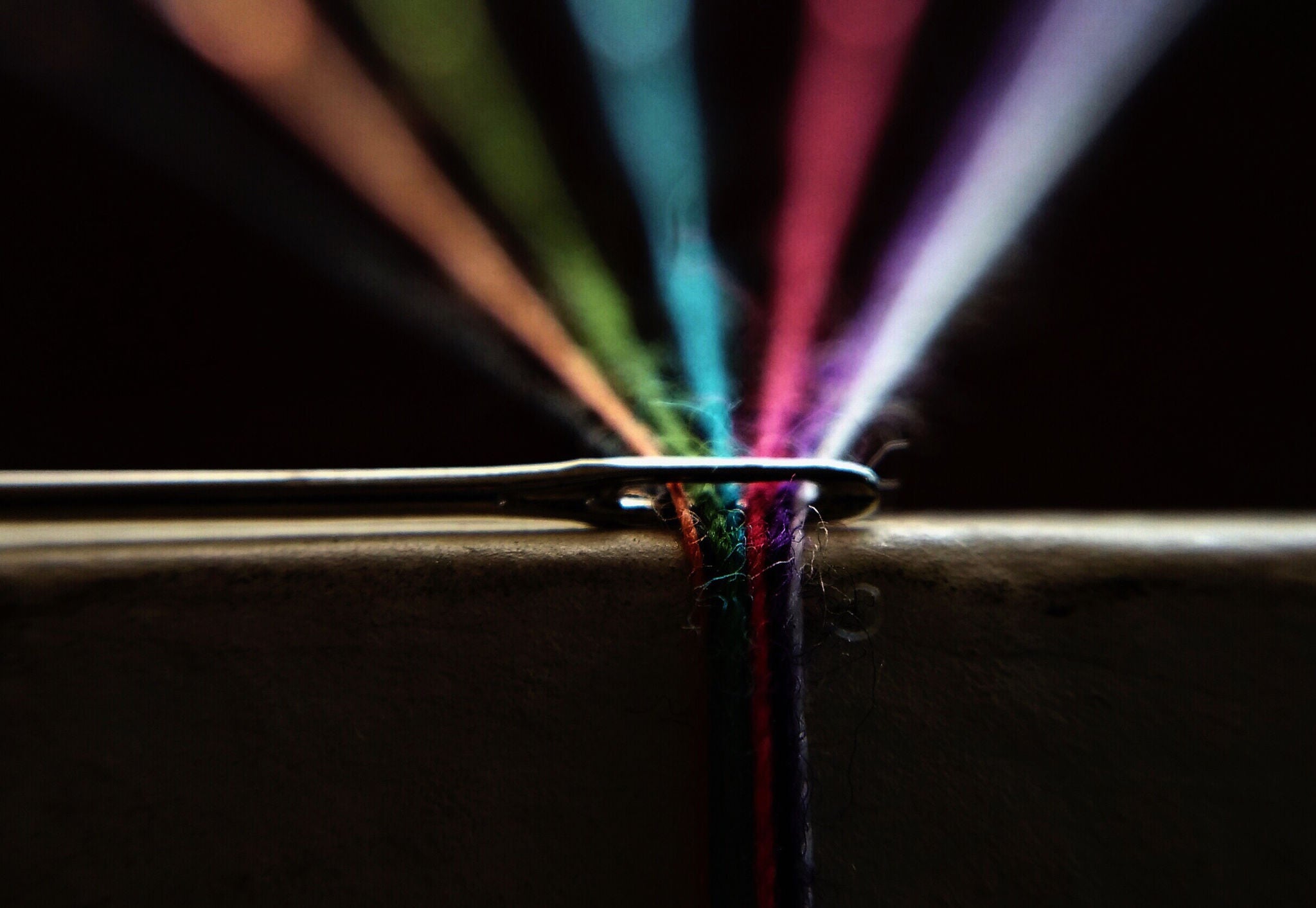
Section 1
「ヒト」が中核となり、新たなテクノロジーと共生していく世界で求められるものとは?
日々の生活を改善すべく生み出された技術は、時として想定外の効果をもたらし、社会構造さえも変革させてきました。しかし、どんなにテクノロジーが進化したとしても、それを操るコアとしての人間力は欠かせません。

国立研究開発法人理化学研究所 理事 原山 優子 氏
この2年間のコロナ禍により、世界はニューノーマルへと移行し、従来の「当たり前」が当然ではなかったことを思い知らされました。同様に、これまで私たちに刷り込まれてきた「人と技術」の関係性もまた、再認識が求められているのです。
「いま人々は人工物(Artifact)に囲まれて生活しています。しかし働くという行為を振り返ったとき、果たして人工物を創るために働いてきたのでしょうか?」 こう問いかけて講演を始めた原山氏は、「これまで私たちは世の中を変えるために発展を目指してきました。しかし発展の意味も、この2年間で再考する必要が出てきたようです」と語り、人類の長い歴史のコンテキストから、人と技術の関係性を紐解いて説明しました。
人類が登場した頃は、生きていくために自然と共生し、狩猟や採集をしていました。いま風にいえば、サステナブルなSociety 1.0の世界です。次に農耕を手段として自然に働きかけ、組織や国家が誕生するSociety 2.0になりました。ここまで人類は「パワー」を自身や家畜の力に頼っていましたが、やがて技術進化により動力を活用し、多くのモノを大量生産できるSociety 3.0の時代が到来しました。
現在のSociety 4.0の世界は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というキーワードで象徴されるように、動力源が「知」となり、デジタルとデータで社会自体を変えていく時代です。従来の有形資産から、情報という無形資産に比重を移し、付加価値が作り出されていくようになりました。そして次のSociety 5.0では人が中核となり、人工知能(AI)などの技術と共生していく世界になっていくでしょう。
人類は、このように長い歴史の中で道具を作り込み、技術を生み出して、そのメカニズムや自然現象を理解する科学を並進させてきました。生活に豊かさを与え、イノベーションを生み出してきたわけです。
「この背景には、発展や経済成長へのあくなき欲求や競争原理などの要因がありました。一方で、現在は(競争に)勝つことだけでなく、その先にある共存や、自然と融合した社会への対応も求められるようになっています。例えば、地球規模でカーボンゼロ(温暖化ガス排出が実質ゼロ)への取り組みも叫ばれています」(原山氏)
ここまで振り返ってきた「人」と技術の関係性に対し、「個人」と技術の関わりを細かく分析すると、研究者やエンジニアだけでなく、それらを支える多様なプロフェッショナルからも成立していることが分かります。また新技術を生み出すだけでなく、それらを社会に供給し、実装させる浸透力も必要です。
ところが昨今では、こういった新技術の浸透は以前のように緩やかでなく、スピードアップし、技術自体も非連続に飛躍し、そのインパクトが量・質ともに広がっています。そのため、社会が新技術を受容できる体制が整う前に、物事がどんどん進展してしまうというギャップが生まれています。
「そのような状況で、人と技術の関係性も進化させていく必要があるでしょう。もちろん技術は役立つことが前提ですが、単純に便利になるという理由だけでなく、人の感性に響いたり、社会的な倫理観や多様性、共感の形成といった、人を中核とした価値観の共有も重要です。ここにはグローバルな視点で共にデザインして創造する、参加型の体験共有が求められます」(原山氏)
もう1つ、人と技術の関係性で再考すべき点は、人自身も技術を適用する対象になってきたことです。先端科学技術、特にライフサイエンスの分野では、ゲノム編集や生殖補助医療、ニューロサイエンスなどが進み、生命体としてのヒトを理解する、補助することと同時に人をコントロールすることすら可能になるという社会的な問題も内包しています。また人工知能、ナノテクノロジー、センシング、ロボティクスなどのエンジニアリングの分野においても、技術の使い方次第では倫理的な問題が生じる恐れもあります。
原山氏は「新たな技術によって、人が人である本質的な機能を理解できると同時に、コントロールも可能になってしまうことや、人の意識や感性、人々の行動まで監視できるようになる恐れがあります。こういう社会に突入して、予期せぬことが起きたときの準備も大事になるでしょう」と警鐘を鳴らします。
特に、これらを推進する人々は「責任ある科学技術イノベーション」をコアに、未来の世代への責任も考えなければなりません。最近では「ELSI」(Ethical, Legal and Social Issues:倫理的・法的・社会的課題)や、「RRI」(Responsible Research & Innovation:責任ある研究・イノベーション)が叫ばれています。
現在のように科学技術の進展が著しい時代には、政府に委ねていた課題に、研究開発者やエンジニア、民間企業、一般市民も、自分事として積極的に関わり、議論していかねばなりません。原山氏は「ここで、まさにキーとなるのが、人間中心の考え方なのです」と力説します。
実は、こういった活動は、すでに責任ある研究主体としても進められています。例えば、遺伝子組み換え技術の安全性指針や、倫理的側面からヒト生殖系の臨床研究への提言、AIに関する原則などが議論されてきました。
AIに関しては、日本でも2016年から政府を中心に議論してきました。Society 5.0やDXを推進するために、アルゴリズムや人工知能をツールとして使う際に、倫理・法律・経済・教育・社会面などの論点をリストアップした「人工知能と人間社会に関する懇談会」や、AI開発ガイドライン案を策定した「AIネットワーク社会推進会議」が開かれました。
さらに2018年からの「人間中心のAI社会原則検討会議」により、政府の方針として人間中心のAI社会原則が練られ、国内のみならずOECDやG7(先進7カ国首脳会議)などのグローバルなフレームワークの中で議論にも貢献しました。
近年、OECDは経済問題だけでなく、より良い社会をつくるための「Going Digital」と呼ばれる横断的なプロジェクトを進めてきました。人間の豊かさや社会変革のための政策を議論し、その派生としてAIに関する「OECD AI原則」も2019年に策定されました。この原則を各国で実装すべく、その対応をウォッチするオブザーバートリー「OECD.AI」(OECD AI Policy Observatory)や専門家のネットワーク「ONE AI」(OECD Network of Experts on AI)もあります。
この流れをくみ、2020年にはフランスとカナダ主導による、G7を中心としたAIに関する国際的なグループ「GPAI」(Global Partnership on AI)も作られました。OECD AI原則をベースに、AIの社会実装や社会変革を促す母体として、「責任あるAI」「データガバナンス」「仕事の未来」「イノベーションと商業化」といった作業部会で、社会や企業の現場で起きていることや、起こり得る課題などが議論されています。
原山氏は「例えばDXやビジネスチャンスを生み出すツールとしてのAIは、使い方次第で兵器に搭載されたり、SNSやディープフェイク(動画や画像の人物などを加工した合成メディア)のアプリに利用されたりと、もろ刃の剣にもなります。エビデンスと呼ばれるものもAIにより生成された可能性が出てくると、何を証拠として判断したら良いのかわからなくなる。またバイアスが拡張されるリスクも大きい」と指摘し、「デジタルスキル以上に、AIと賢く付き合える人間力が必要」と強調します。
さらに「本質的には、人間社会は技術とともに作り込まれ、歴史の中で人権や民主主義の概念が社会に埋め込まれてきました。しかし次の社会では、当然と思っていたことがAIの活用で覆される可能性もあります。こういった困難な問題には『Collective intelligence』(集団的知性)としての議論が求められます」と提案し、講演を締めくくりました。

Section 2
グローバル時代と米中冷戦のはざまで、果たすべき日本の責任と国際協調の在り方とは?
続いて、基調講演に関する質問を受ける形で、原山氏とのトークセッションが開かれました。モデレーターは、EY アジアパシフィック ピープル・アドバイザリー・サービス 日本地域代表 パートナーの鵜澤 慎一郎が務めました。

まず、先端技術における情報管理に関わるコンプライアンスの問題と、ソリューションをテーマに議論が展開され、鵜澤が次のように問いかけました。
「米中冷戦構造が深刻化する以前は、サプライチェーンがグローバルで最適化されていました。情報管理も緩やかでしたが、EUの個人データ保護規制(GDPR)や、米中間のサイバー戦争による情報窃取が起き、各国での情報管理が厳しくなりました。システム自体もグローバルワンで作りづらくなる中、今後の科学技術は一体どのように展開されていくのでしょうか?」(鵜澤)

EY アジアパシフィック ピープル・アドバイザリー・サービス 日本地域代表 パートナー 鵜澤 慎一郎
原山氏は「米中の関係性は両国だけでなく、他国や第三者を引き込む、ホットでデリケートなテーマです。技術競争に加え、地政学的な要因が混ざり、どんな視点から国や企業の立ち位置を決めればよいのか読めないのが実情です。本来、サイエンスには国境がなく、グローバルに構築していくことが当たり前の世界でした。しかし、いまは共同研究やテーマ設定でも、軍事や競争力などの観点から中国との関係性を配慮し、場合によっては相手の「身体検査」をしながら、プロジェクトを組むようなフェーズに入ってしまいました」と嘆きました。
このような厳しい状況で、同氏は「私たちが守るべき価値観を声高に叫ばなければなりません。サイエンスのために一人の研究者として行動する方もいらっしゃいます。国籍によって排除することが本当に正しいことなのかも考える必要があるかもしれません。情報のサイロ化が起きたとき、さらに望ましくない状況が加速される可能性もあります。どこを潮時にすべきか、政治家だけでなく、多くのステークホルダーからプレッシャーをかけたり、表明を行うことも大事です。その中でバランス感のある落とし所を模索する必要があると思います」と慎重に答えました。
鵜澤も「こういった正解のない問題に対しては、Collective intelligenceで状況を判断しながら、最適解を判断していくしかないでしょう。しかし大きな流れとして、世界が保護主義に向かうことは理解していたほうがよいかもしれません」と補足しました。
原山氏は「EUでは政策的にデータ主権を打ち出していますが、ならば日本もやるということになると、さらにサイロ化が進むかもしれません。そこでカウンターバランスの流れを作る必要があります。それは米国というよりか、多くのステークホルダーによる行動となるでしょう。日本も先進国の一員として、国際社会の責任を果たすことが求められます」と強調しました。
2つ目の論点は「日本企業がDXをグローバルに進めるための効果的なアプローチについて」でした。
国際舞台で活躍してきた原山氏にとって、海外での長い暮らしは、日本人のアイデンティティや、刷り込まれた文化を見直す契機になったそうです。その上で同氏は「グローバル化とは、スタンダードに準じることだと思い込んでいる人がいらっしゃいますが、その標準とは一体誰がつくったものなのでしょう?」と疑問を投げかけ、次のようなアドバイスを送りました。
「自社を標準に寄せるのではなく、多くのアプローチの中で、実情に合わせて変えていく視点が大切です。単に同業種と同じアプローチを導入するだけでは意味がありません。物まねではなく、自己変革としての解を見つけるドライバーとして使う必要があります。海外に情報を求めたり、逆に日本文化にどっぷり浸かっていない外国人を採用したりして、改善点をリストアップする方法もあるでしょう」(原山氏)
鵜澤も「米国標準に合わせることがグローバルスタンダードではないと、私も常々思うところです。われわれとは違うモノの見方や行動特性を取る国があり、現状ではどれが良いのかを選び、さらに融合したものをつくることがダイバーシティであり、インクルージョンであると感じました」と、この意見に大いに賛同しました。
また、DXの進展によって「製造業の監査面で新たに留意すべき点があるか?」という質問に対し、原山氏は「お目付け役である監査役は、これまでは財務・会計などのチェックポイントを押さえていました。しかしモノ作りだけでなく、サービスを売ることも製造業に入ってくると、従来とは異なる投資や、付加価値を生み出すコア人材の組織も必要になります。DXに限らず、経営組織やビジネスモデルの変革が前提となれば、収益母体のシフトやコンプライアンスなどにも踏み込んで全体像を見渡すことが、監査役に要求されるようになるでしょう」と予測しました。
さらに原山氏は、HR(人事)の観点から新しい監査項目が加わる可能性も示唆しました。「例えば自社の社員をコントロールするために、今後はAIを導入することになるかもしれません。個人のプライバシーや尊厳を守りながら、果たして居心地の良い職場環境をつくるためにAIが使われているのか、その倫理観を企業が持ち合わせているのか、監査役がチェックするようになるかもしれません」
これを受けて、鵜澤は「今後DXが進展し、従来以上に非財務パフォーマンスとしての人的資本価値が重視されていく中で、企業が本当に人を大切に扱っているのかどうか、さらにAI活用も健全なのかが問われるような時代になっていくでしょう」と総括しました。
サマリー
企業変革の推進となるDXの成功には、デジタルテクノロジーの力だけに依存することなく、人間中心の考え方を基本とした組織・人材の変革が必要不可欠です。昨今の厳しい国際情勢に加え、AIなどの先端技術が各ビジネス現場やHR機能の中に導入され、そこに内包される倫理面やコンプライアンスなども含めて、自分事として捉えなければならない時代になってきたともいえるでしょう。



