EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

「HRDXの教科書」出版記念セミナー
第5回「HRDXと企業文化」(2022年5月12日開催)
要点
- 経営マネジメントの大家であるピーター・ドラッカーはCulture eats strategy for breakfast(企業文化は戦略に勝る)と有名な言葉を残しているが、DXやイノベーションを実現するにはカルチャー(企業文化)の側面を軽視してはいけない。
- 売上とコストで指標分解する従来経営発想から脱却し、顧客価値を起点に企業経営のバリューチェーンを再構築する。先行指標となるEX(Employee Experience)の価値を向上させて、好循環サイクルを回す。
- カルチャー変革とは、現状のカルチャーの棚卸し、MVV(Mission Vision Value)の設定、カルチャーの方向性の決定、カルチャーの言語化、カルチャーの浸透という手順で進める。
「HRDXの教科書」出版記念セミナー(第5回)では、Almoha LLC 共同創業者COO/デジタル庁人事・組織開発の唐澤俊輔 氏をゲストに迎え、「HRDXと企業文化」をテーマに解説していただきました。同氏は日本マクドナルド株式会社、メルカリ、SHOWROOM株式会社、デジタル庁など多種多様な業態でカルチャーの変革に関わり、独自の「カルチャーモデル」を提唱している。
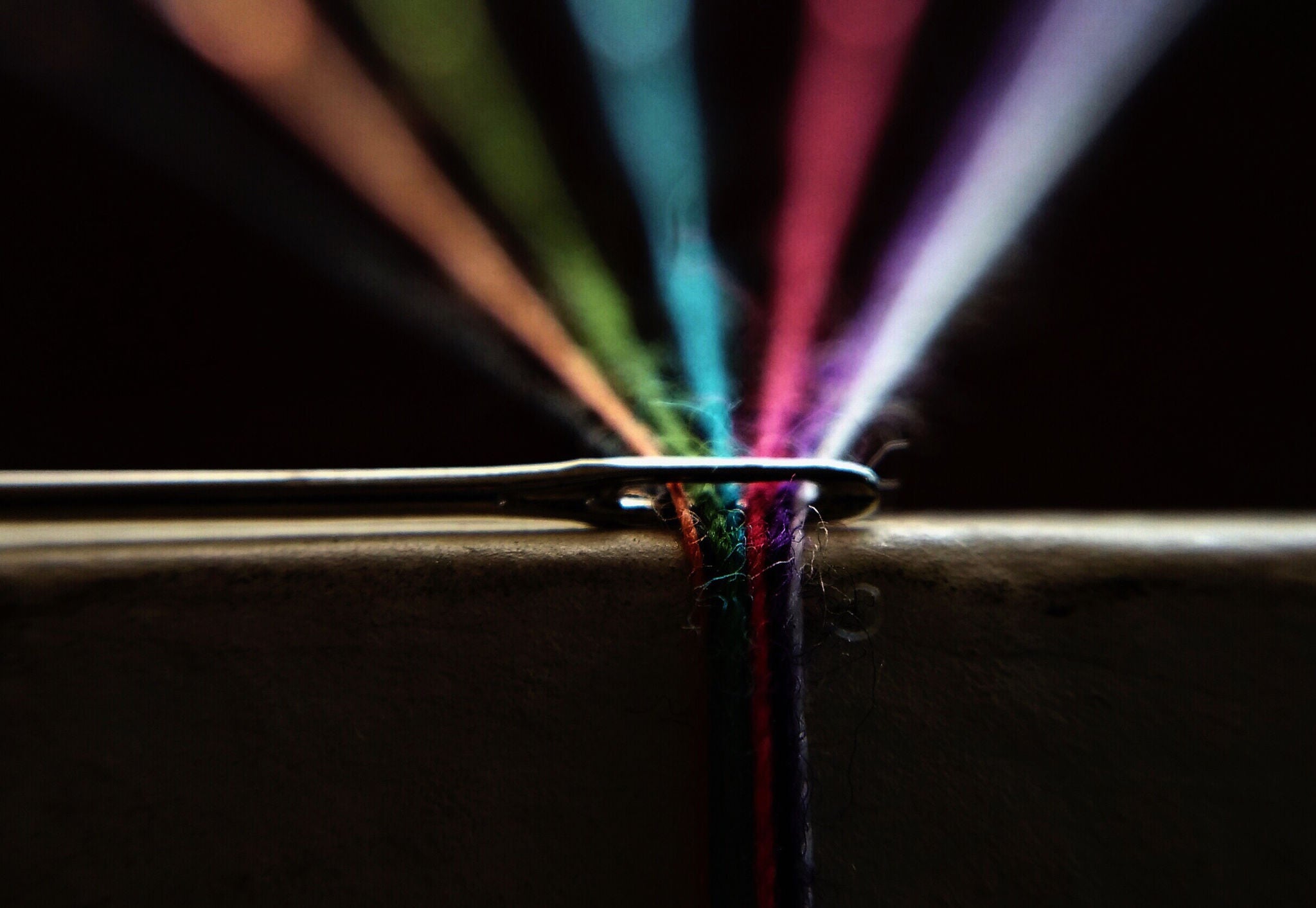
Section 1
EXを先行指標に、カルチャーモデルによる最高の組織文化をつくりだす
イノベーションを起こしたい企業にとって、カルチャーは戦略と同等以上に重要であり、企業変革やDXの推進にも必要なものです。本セミナーでは、唐澤氏が提唱するカルチャーモデルによる実践的な企業文化のつくり方を解説します。

なぜ企業にとってカルチャーが重要なのでしょうか? 唐澤氏は「GAFAMのような企業が成長し続けているのは、独自文化を形成し、組織力を中心に据えることで、企業の競争力にしているからです」と指摘します。
「Appleはカリスマ経営者のスティーブ・ジョブズ氏の退任後も業績を伸ばしていますが、これは彼が作り上げたカルチャーが内部に浸透して引き継がれてきたからです。Netflixも「カルチャーデッキ」と呼ばれるスライドで文化を可視化・言語化し、「自由と責任」という言葉のもと、成果さえ出せば働き方は本人の自由に任せるという姿勢を打ち出し、共感する人材が集まっています。
当然ながら、企業の存在理由は利益を生んで事業継続性を持たせること。そこで従来までは、利益を「売上」と「コスト」に分解し、さらに売上は「顧客数」「顧客単価」、コストは「変動費」「固定費」というようにブレークダウンして管理するアプローチが取られてきました。
従来の経営では、例えば新規顧客の認知が低ければ、広告を強化してテコ入れします。その際にコストは人件費から捻出することになりがちです。人件費をコストと捉えると抑制の対象になり、投資の対象になりません。経営視点では、どこに課題があるのかWhereの議論にとどまり、原因となるWhyの追求に至らず、場当たり的な措置が取られることが多いのです。
一方で、これからのDX時代の経営は、利益を「プロセス」で分解する必要があります。顧客ロイヤリティが高まれば、売上単価や利用頻度が上がり、他の顧客も呼び込めます。
そのプロセスをたどると、顧客満足度(CS)や顧客提供価値があります。それらの価値を生むのは従業員のロイヤリティや生産性で、その背景には従業員満足度(ES)があります。結果として利益が上がるので、従業員に再投資され、好循環が回るのです」(唐澤氏)
このような「サービス・プロフィットチェーン」のフレームワークの下で経営すると結果的に利益が生まれ、売上や利益のすべての背景にある先行指標が「ES」ということになり、そのESを生みだす従業員体験(EX)に帰結されることになります。つまり事業の成果が出ない真の要因はEXにあり、EXのジャーニーの価値を向上し、顧客体験(CX)を高めるという好循環サイクルを回すことが、今後の経営にとって重要になるわけです。
「これはDXを推進していく経営にも直接関わります。デジタル化によってCSもESも数字で追えるため、向上すべき点をデータとして見える化できるようになります。この視点で前出の新規顧客の認知が低いという課題を見ると、入社後の育成不足で効果が低下していたというように、CXやEXのジャーニーから課題を特定でき、組織面の解決により業績が上がることが分かります」(唐澤氏)
ここでDXとは、デジタルを活用してCXを抜本的に向上させることであり、そのためにEXの向上も必要不可欠になります。では、どのようにEXを向上するのでしょう? 人事評価を成果型に変えたり、管理職研修を強化したり、組織風土の改革に着手したり、多くの施策を打っても、能力のある社員から退職することは珍しくありません。
唐澤氏は、その原因が「期待値ギャップ」にあると説明します。社員全員に対して同様に成果主義型であると伝えても期待値の捉え方が異なり、モチベーションや生産性が左右されます。多様性の時代では、期待値のばらつきで一層ギャップが広がりかねません。
「そこで企業としては、EXジャーニーを通じて、課題を可視化し、期待値をそろえる必要があります。その上で一人一人の日々の行動や言動が現場で確実に実行されるように、カルチャーの浸透や発信を欠かさずに行うことが大切です」(唐澤氏)
同氏は自著「カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方」の中で「カルチャーモデル」を提唱しています。空気のように目に見えないカルチャーが悪さをしないように意図的に設計・言語化し、それが組織に浸透すれば期待値ギャップもなくなり、ESも高まって競争力強化につながります。
カルチャーモデルを理論的に設定するために、同氏は「カルチャーは日々の行動・言動の積み重ね。その結果が組織に根付きます。それを構成するのがミッション・ビジョン・バリューやパーパスで、どんな組織を目指し、どういう価値基準や行動指針にするのか、それをベースにカルチャーが形成されます。企業全体で整理し直すと、ビジネスモデルとカルチャーモデルを両輪で描き、組織の面においても事業と同様に計画を立てることが重要です」と力説します。
それを実行するのが日々のビジネスにおけるオペレーションであり、カルチャーにおける人材マネジメントです。結果的にCSやESが向上し、売上や投資の好循環が回ります。
では、どのようにカルチャーをつくり、醸成していくのでしょうか? 唐澤氏は以下5ステップを推奨しており、現在はデジタル庁の改革にも取り組んでいます。
(1)現状のカルチャーの棚卸し
(2)ミッション・ビジョンの設定
(3)カルチャーの方向性の決定
(4)カルチャーの言語化
(5)カルチャーの全社浸透
(1)の棚卸しでは、カルチャーモデルの7Sに沿って、組織の在り方、行動指針、組織の構造・形態、人事制度、採用や育成、組織のスキルや強み、風土を検証します。
その上で(2)で、社会に果たすべきミッションや、中長期的なビジョンなど、組織としての目指す理想の姿を描きます。
唐澤氏は、昨年から民間としてデジタル庁に参画し、人事・組織開発を担っています。そして同庁のミッションに「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」、ビジョンに「Government as a Service」(UXの最大化)と「Government as a Startup」(大胆かつスピーディーなデジタル改革)を定めるプロセスを推進しました。
(3)のカルチャーの方向性として、デジタル庁では非連続な成長でイノベーションを起こし、多様性による化学反応が可能なスタートアップ的なカルチャーを目指して「リボルビングドア」(回転ドア)というコンセプトで進めています。
「これは官と民がグルグル回転しながら往来することを狙ったもの。デジタル庁という組織をハブにして、官公庁・自治体の回転ドアと、民間企業の回転ドアを2つ設けることで、志の高い多様な人材をデジタル庁に集め、能力を発揮して学び合い、DXの知見を官民組織へ持ち帰って波及させるアプローチです」(唐澤氏)
(4)のカルチャーの言語化では、バリューを中核に施策を言語化し、前出の7Sとの整合性を取ります。同庁ではワークショップを繰り返し、バリューにつながる働き方やとるべき行動のアイデアや、個別インタビューで組織課題を集めながら、デジタル庁が理想とする組織像を検討しました。そして、デジタル庁の職員が共通してとるべき行動指針として「この国に暮らす一人ひとりのために、常に目的を問い、あらゆる立場を超えて、成果への挑戦を続けます」という4つのバリューが策定されたのです。
ただしカルチャーの言語化ができても、日々の行動や言動に落とし込めなければ、絵に描いた餅です。そこで(5)のカルチャーの浸透において、コトラーが提唱する5Aのフレームワークを応用した、認知(Aware)→訴求(Appeal)→調査(Ask)→行動(Act)→推奨(Advocate)の5つの浸透プロセスに沿って、デジタル庁での取り組みを以下紹介していきます。
AwareではMVVを可視化し、庁内にポスターを張り、Appealでは共通認識が醸成されるようにEXジャーニーの接点にカルチャーを組み込み、入庁タイミングのオンボーディングとして必ず説明を行っています。Askではカルチャーについて調べれば分かるよう、庁公式note等で幹部や職員のインタビュー記事を掲載。オールハンズと呼ばれる全庁職員が集まっての会議も行い、大臣のメッセージや職員とのディスカッションも庁内でアーカイブ化され配信されています。
またActではカルチャーの体現を実現すべく、人事評価上の行動評価としてバリューを組み込み、360度レビューや、MVV Awardという表彰を行うことでバリューの浸透を進めています。また、カルチャーを内外に広めるAdvocateとして、有志のバリューアンバサダーを組織化して輪を広げています。最終的には組織サーベイで可視化し、エンゲージメントをスコア化することで、改善サイクルを回すよう努めています。
これらの5ステップも参考に、デジタル庁は新たなカルチャーを構築中ですが多くの企業では、カルチャーは売上に直接貢献しないと言われ、その優先順位が上がらないことが悩みです。この点について、同氏はカルチャーがビジネスにどう効くかを強調し、解決できることを説明しました。
「カルチャーが浸透すると、判断基準が組織内で擦り合うので、ビジネスの意思決定が圧倒的に速くなります。カルチャーは価値観なので、ある程度の解釈余地があり、自らが考えて行動する組織風土もできます。またカルチャーを発信すれば、企業ブランディングになり、自社にフィットした良い人材や、外部パートナーが見つかる可能性もあります」(唐澤氏)
最後に同氏は「より良い会社にしたい、もっと楽しく働きたいという変化を生み出すのは、一人ひとりが動き、組織全体で連携しなければできません。自社が最高の組織文化であると胸を張れるように頑張っていきましょう」とエールを送りました。

Section 2
カルチャー変革は伝統的な大企業でも実現可能。1番のポイントはトップのコミットとミドル層の影響力
第2部のトークセッションでは、モデレータの鵜澤 慎一郎が「人事部門に求められる新たなミッション」「大企業でのカルチャー浸透の可否」「転職時に感じる企業カルチャーギャップの克服方法」など、さまざまな質問を投げかけました。

まず鵜澤は「VUCA時代だからこそ、戦略的な人事が大切だと思いますが、人事部門に求められる新たなミッションとは何でしょうか?」と問い掛けました。
唐澤氏は「メンバーシップ型雇用は日本の組織の強みですが、その環境では専門家が育ちにくいという実情があります。これを打破するには人事が変化を受け止めるという受動態ではなく、逆に変化をつくる側に回ることが大切です。変化を恐れずに外部の血を入れ、新しい専門家を中途採用すると、その人から専門性を学べ、周囲の変化が生まれます。彼らと現場を知る社員、それぞれ違う知見を持つ人同士を組み合わせると、互いに補い合える強い組織になると思います」とアドバイスしました。
次に「スタートアップはともかく、伝統的な大企業では従業員規模も大きく、共通のビジョンやカルチャーを浸透させるのは難しいのでは?」という鉄道業界の社員からの質問に対し、唐澤氏は「前提論として社員が100人でも1万人でも組織自体は多様であることに変わりなく、規模による難易度はあっても、必ずしもビジョンやカルチャーの浸透ができないわけではありません」と説明。
その上でカルチャーを浸透させる場合、自分事にしてもらうためにワークショップを全員で行うことを推奨しました。「1万人の企業でも100人のワークショップを100回やれば不可能ではありません。ただ自分一人で全て行うのは難しいので、ワークショップをやれる人を巻き込み、最初のワークショップで100人の講師を育成するわけです。その100人が次の100人ずつに広げてもらうという構造をつくれば、1万人での展開も可能です」と自身のアイデアを披露しました。
「転職時に自身の価値観と、企業カルチャーにギャップがあったとき、どう対処すべきですか?」という質問もありました。
これまで日本マクドナルド、メルカリ、デジタル庁など、文化が異なる組織を経験している唐澤氏は、自身で決めていることがあるそうです。「過去の会社を一度忘れ、新しい会社を把握するために時間を費やすことです。アンラーンと言ったりしますが、一度自分の従来の価値観をリセットし、その会社のカルチャーを自分にインストールすることが大切です。その上で自分のスキルや経験を少しずつ発揮していくことも可能です」と回答しました。
「事業や部門により業務が異なるため、価値観も異なると思います。どこまでコーポレートカルチャーと統一感のあるものにすべきでしょう?」という問いも飛び出しました。
唐澤氏は「事業単位でカルチャーが異なることはあり得ます。事業が違うと顧客も変わるし、ビジネスモデルも違うので、カルチャーモデルも異なる可能性があるからです。一方で、同じ事業体の中で異なる部門や職種ならばカルチャーを共通化し、横断的に共通化すべきです。なぜなら開発部門が顧客ニーズに応えて設計したのに、最後のマーケティングで違う価値基準になったら、お客さまへのメッセージが変わり、混乱させることになりかねないからです。バリューの基本的な基準はそろえるべきで、その上でバリューの範囲の中で、部門ごとにバリューを解釈して落とし込むことでより自部門で使いやすいものにすることは良いと思います」と助言しました。
また「カルチャーを変える時間はどれくらい必要ですか?」という問いには、「日本マクドナルドが日本的な会社から外資系の会社に変わるまでに7、8年かかったと私は感じています。5年、10年計画の長期的スパンで根気が必要です。ただ、その10年の期間を自身が必ずしも全てコミットする必要はなく、2年間のあるフェーズをしっかり担い、次を後任に任せることは問題ないと思います」と答えました。
「企業によってはカルチャーの浸透に差が出ると思いますが、成功させるための1番のポイントとは何でしょうか?」という本質を突く問い掛けもありました。
唐澤氏は「やはりトップが腹をくくってコミットしないと、次の幹部レイヤーが乗ってこないので、会社全体に波及しません。『ここを変える!』ということをトップの声で本気で言ってもらう。そこをグリップすることが重要です。私が取り組む場合は、組織サーベイから始め、現場の声を拾って課題を可視化し、幹部に見せています。そこで幹部と問題を共有化できれば、一緒に頑張ろうと音頭を取ってくれます。これが始まると全員に本気度が伝わり、スイッチが入ります。そこの取り付けができなければ、何年たっても変わりません。ですからトップを巻き込むことが大切です」と強調しました。
サマリー
現代経営では従来のような売上とコストで指標分解する経営管理や、人をコストと捉えるアプローチは時代にそぐわなくなっている。EXとCXの一連のジャーニーを再構築し、顧客と従業員を中心にした新たな経営モデルと企業文化をつくり出す必要があります。EXが向上して、働きがいのある組織が生まれると、優秀な人材が集まり、より企業戦略の実効性が高まります。



