EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2018年新年号 FAAS
FAAS事業部 公認会計士 康 理恵
監査業務を経て、現在、FAAS事業部にて会計アドバイザリー業務に従事。株式公開支援、内部統制の整備支援、IFRS等新会計基準の導入支援などの案件に関与。その他、新基準対応チームのメンバーでもある。
Ⅰ 新収益認識基準について
2017年7月に、企業会計基準委員会は、企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下、新収益認識基準)※1を公表しました。原則適用の時期は、平成33年4月1日以後開始する年度の期首からとされ、早期適用は、平成30年12月31日から平成31年3月31日に終了する年度の年度末から認められています※2。
新収益認識基準は、一部のわが国固有の代替的取扱いなどを除き、すでに公表されている「顧客との契約から生じる収益」(国際財務報告基準(IFRS)第15号(18年1月1日以後開始事業年度から原則適用)(米国会計基準ASC第606号(17年12月15日以後開始事業年度から原則適用))の内容を基礎として定められました。
本稿では、新収益認識基準の導入プロジェクトの進め方と留意すべきポイントについて解説します。なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であることをお断りしておきます。
Ⅱ 企業に与える影響
収益は、企業の営業活動の成果として企業内外から重視されます。その収益の認識・測定に関し、包括的な基準がわが国で初めて定められたことになり、程度の差はあれ、全ての企業にとって影響が生じると言えます。また、財務会計上、つまり会計処理や財務報告はもちろんのこと、事業全般にも影響が生じ得ると考えられます。
影響が大きいのはどのような企業かについては、契約の実態を調査する必要がありますが、一般的に下記のような取引がある場合は、検討が必要であると考えられます。
- 同一顧客に一つの契約内で複数の財又はサービスを販売している
- 契約内容の変更が頻繁にある
- 取引の対価が事後に変動する(値引き、返品、リベート等)
- 顧客は、財又はサービスを追加で取得できる(ポイント、無料更新等)
- 顧客への財又はサービスの販売に当たり、他の当事者の関与がある(消化仕入、委託販売等)
- 契約期間が長期にわたる(割賦基準、重要な金融要素等)
- ライセンスの供与がある
また、新収益認識基準により、財務会計上、収益の認識・測定に一定の影響がある場合には、次の通り企業活動全般にも影響が波及する場合があるので、注意が必要です。
- ビジネス
- 契約書や取引(新収益認識基準に併せた見直し)
- 内部統制
- 業務プロセスの見直し
- 規程やマニュアルの変更(グループ会計方針等)
- 管理会計
- 業績評価(事業や子会社を評価する際の指標の変更)
- 人事評価(収益が営業マン等の人事評価の指標として使用されていた場合、その指標の変更)
- IT
- 事業をシステムでサポートしていた場合に、関連するシステムの変更
- IR
- 新収益認識基準が与える影響に関する投資家への説明
- 新収益認識基準が与える影響に関する投資家への説明
Ⅲ 導入プロジェクトの全体像と基本方針案
<図1>は、日本基準により連結財務諸表を作成し、かつ、比較的論点や商流の数・種類が多いケースを想定した、新収益認識基準の導入アプローチです。
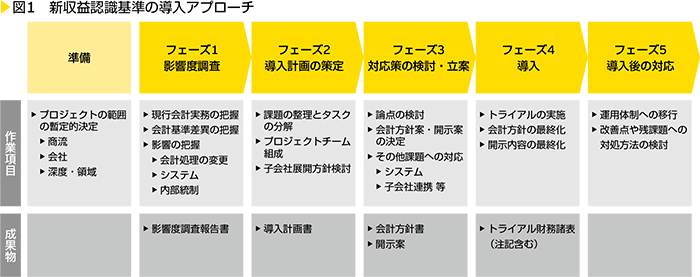
前記ケースに当てはまらない会社、例えば、IFRSをすでに任意適用(もしくは任意適用を予定)している場合には、連結財務諸表ベースではIFRS第15号による対応が進められていると思いますので、個別財務諸表に監査が必要とされる会社への対応が中心になります。
また、論点も商流も限定的で、基準に対する最低限の対応で済ませる場合には、フェーズ1~3を同時並行で対応するケースもあるかもしれません。
会社の実態と、目指す方向性によって、カスタマイズが必要となることにご留意ください。
プロジェクト開始に当たって、まず検討すべきことは、プロジェクトの範囲(対象と深度)です。原則的にはすべての収益が対象とはなるものの、重要な商流及び個別財務諸表の監査対象会社をベースに、対象を絞り込むことも有用と考えられます。
1. 重要な商流
連結財務諸表の収益を商流ごとに整理し、連結財務諸表に与える影響を勘案し、プロジェクトの対象となる商流と会社を抽出し、対象とします。
2. 個別財務諸表の監査対象会社
会社法に基づく会計監査人監査の対象会社など、個別財務諸表に監査が必要とされる場合には範囲に追加します。この際、連結財務諸表に与える影響を勘案して抽出された商流のみならず、個別財務諸表ベースで重要性のある商流についても、対象に追加する必要があります。
3. その他(追加)
① 持分法適用会社
持分法適用会社の場合、新収益認識基準の影響額は、売上に直接反映されるわけではありませんが、損益への影響が大きい場合は調査対象への追加を検討する必要があります。
② 任意の追加
収益が事業部や子会社の業績評価の指標となっている場合など、事業及び管理上の必要性に応じて対象会社を追加します。
4. その他(除外)
IFRS(ないし米国会計基準)適用海外連結子会社であれば、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第18号)」による容認規定を適用している場合、日本基準としての適用準備をする必要はありません。
5. プロジェクトの深度
プロジェクトを、単なる会計基準変更対応にとどめるのか、それとも管理会計などの影響分野まで広げるのか、その他プロジェクトに割くことのできる人員や期間により、プロジェクトの大小が変わります。
① 財務会計上の対応
わが国固有の代替的取扱いを採用する余地がありますが、将来的にIFRS導入の可能性があり、代替的取扱いが連結財務諸表に与える影響が大きい場合、IFRSでは代替的取扱いは認められないので、注意が必要です。
② 管理会計上の対応
管理会計システム、業績評価システム、人事評価システム等、収益の影響を管理会計にも反映させる場合、関連するシステムの改修の必要性についても検討が必要となります。
Ⅳ 導入プロジェクトの各フェーズの説明
1. フェーズ1:影響度調査
ここでは、基準差による影響(検討すべき論点、会計処理・システム・内部統制への影響等)を概略的に把握し、計画策定のための情報を入手します。プロジェクトの手戻りを防ぐ意味でも、ここでしっかり影響を把握することが重要です。
なお、本来であれば、会計処理だけではなく開示に関する調査も含めて実施すべきですが、現時点では開示に関する取扱いが公表されていないので、公表され次第検討が必要です。参考までに、IFRS第15号では残存履行義務の開示が求められており(新収益認識基準に従った受注残や将来収益認識されるタイミングの開示を想定)、長期受注産業は大きな影響を受けると考えられます。
① 調査範囲
前述したプロジェクトの範囲のうち、まずは代表的な商流について調査を実施します。例えば、類似の商取引を親会社及び子会社で展開している場合について、親会社において影響度調査を実施することが考えられます。
② 調査方法
調査方法は、ヒアリングやアンケートによって進めるのが一般的です。商流の全体像を把握する担当者に直接ヒアリングすることが理想的ですが、工数がかかるので、商流に関係する代表的な会社に対してはヒアリング、その他の会社に対してはヒアリング結果を基に作成したアンケートを実施するなど、適宜組み合わせて調査します。
ヒアリングの際に利用するツールとして、事前に、新収益認識基準の規定、対応する現在の会計基準または実務、両者の差異を明らかにした影響度調査のためのチェックリストを作成しておくとよいでしょう。ヒアリング実施時においては、このチェックリストを基に、両者の差異について、会社の現行の会計処理や実務はどのようになっているかを明らかにしていきます。その際に、会計処理への影響だけでなく、システムや内部統制への影響についても確認しておく必要があります。
最終的には、新収益認識基準移行に伴って、会社に影響のある論点の概要、会社の現状、今後の課題を取りまとめます。
2. フェーズ2:導入計画の策定
ここでは、フェーズ1の影響度調査の結果を受けて、対処すべき課題を整理し、前述したプロジェクトの範囲(対象と深度)で、作業工数見積りができるレベルまでタスク分解し、基準の適用までの時間軸を基に、フェーズ3以降の導入計画を策定します。
さらにこの導入計画を基に、どの部署からどういう役割の人員をいつ集めるかを検討し、プロジェクトチームを組成します。またこの段階で、グループ会社についても、いつ誰がどのように展開していくかについて検討し、スケジューリングしておきます。
3. フェーズ3:対応策の検討と立案
ここでは、フェーズ1で概要を把握した論点について、フェーズ2の計画に基づいて、個別に詳細を検討・対応するので、最も作業ボリュームが多いフェーズです。
具体的には、より現場レベルの担当者へヒアリングするとともに、必要に応じて契約書等を入手し、会計処理の変更が必要か否か、変更後の会計処理や開示内容について検討します。この時、検討結果を文書化しておくと、その後の会計方針書の作成や監査人との調整、その後のフェーズがスムーズになります。
また、会計処理及び開示の変更に必要となる情報を入手できるかについても検討し、もし現状のシステムや体制で対応できない場合には、システム変更や業務処理の変更もこの段階でめどを付け、次フェーズでの導入に備えます。
さらに、財務会計にとどまらず、管理会計もプロジェクトの対象とする場合についても、この段階で同様の対応をします。
最終的には、各社・各部署の調整を経て、会計方針案及び開示案を決定し、その内容を会計方針書等にドラフトします。
なお、グループ会社への展開もこの段階で実施します。このとき留意したいのは、類似の商取引に関する会社間での会計処理の整合性です。特にIFRS(ないし米国基準)適用海外子会社については、すでに同等の基準を適用しているため、調整するか検討が必要です。グループ会社への展開の方法は、さまざまなケースがありますが、いずれにしても定期的な連携が必要となり、紙ベースでの報告や会議の実施等を検討しておく必要があります。
4. フェーズ4:導入
ここでは、フェーズ3で策定した会計方針を展開し、実際に導入します。
このとき留意したいのは、原則適用の年度では、法定の期限内に財務諸表を提出する義務があるということです。特に、システム変更を実施するなど導入による影響が大きい場合には、想定したタイミングで想定した数字があがるのかに不安がある可能性もあり、この段階で初めて新収益認識基準を導入することにはリスクが伴います。
従って、四半期ベースでもよいので、事前にトライアルの実施を検討することをお勧めします。もし問題が生じた場合には、当該問題の所在を特定し、解決に向けた検討を実施します。その際に、必要に応じてフェーズ3で実施した内容を修正することもあります。このように、導入に向けた課題を特定し、解決することで原則適用年度に向けて備えることとなります。
5. フェーズ5:導入後の対応
新収益認識基準について、プロジェクト中心の取り組みをルーティン業務へと落とし込むとともに、高度化や改善事項について検討し、精度向上や効率化を図るフェーズになります。また、プロセス、システム、その他の成果物等について更新や変更の必要性を検討し、継続的な改善を行います。
Ⅴ おわりに
新収益認識基準は、現時点においてはまだ公開草案のステータスであり、その対応は先送りされがちです。
しかし、前述のとおり、新収益認識基準は単なる会計基準の変更にとどまらず、ビジネス全般に影響を及ぼす可能性があると考えられます。財務諸表のトップラインとして、投資家から評価されるだけでなく、各事業部や従業員の成績の評価に使用されるなど、さまざまな場面でその数字が利用されています。収益の金額がどのような場面で利用されているかについての現状を把握した上で、単に会計基準の変更の対応のみにとどめられるのか、それ以上の対応をすべきなのかを早期に検討しておく必要があると考えられます。そのため、基準の公表を待たずとも、少しずつ準備を始めていくことが重要といえます。
※1 新収益認識基準の解説については、本誌2017年10月号(Vol.125)参照。
※2 早期適用の場合、適用時期によって方法が異なるため、詳細については基準を参照。



