EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2019年10月号 特別寄稿
獨協大学 法学部教授 高橋 均
一橋大学大学院博士後期課程修了。博士(経営法)。新日本製鐵(株)(現、日本製鉄(株))監査役事務局部長、(社)日本監査役協会常務理事、獨協大学法科大学院教授を経て、現職。東証一部上場会社の社外監査役も務める。専門は、商法・会社法、金商法、企業法務。多数の社内研修の講師も引き受けている。近著として『グループ会社リスク管理の法務(第3版)』中央経済社(2018年)、『監査役監査の実務と対応(第6版)』同文舘出版(2018年)等。
Ⅰ はじめに
監査役監査と会計監査人監査に内部監査を加えて、三様監査と呼称します。三様監査の中で、内部監査は任意監査であるのに対して、監査役監査と会計監査人監査は法定監査となります。三様監査間で連携を深めることは重要ですが、とりわけ法定監査を担う監査役と会計監査人は、相互に補完関係にあるとの認識のもと、法定監査を全うする必要があります。
監査役は、取締役の職務執行を監査した上で、監査役監査報告を作成しなければなりません(会社法381条1項)。監査報告を作成するために、監査役には、取締役や使用人に業務報告を請求したり調査する権限があります(会社法381条2項)。監査役は、執行部門から法的に独立した立場から監査を行うために、取締役や使用人との兼務はできません(会社法335条2項)。業務執行者との兼務は自己監査となってしまうからです。
他方、会計監査人(金融商品取引法上は「監査人」、以下同法の文脈で使用するとき以外はまとめて「会計監査人」)は、株式会社の計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を監査する権限があり、事業年度の会計監査の結果として会計監査報告書の作成義務があります(会社法396条1項)。会計監査人はその職務を遂行するために、いつでも、会計帳簿またはこれに関する資料を閲覧・謄写したり、取締役や使用人に対して、会計に関する報告の請求権があります(会社法396条2項)。会計監査人は、外部の会計の職業的専門家として、公認会計士または監査法人(5名以上の公認会計士を社員として設立された法人)でなければなりません(会社法337条1項)※1。
両者とも、一事業年度の監査業務を通じて、最終的に監査報告書を作成し、株主総会の前に、招集通知や参考書類と同様に株主に通知されます。監査役も会計監査人もともに会社とは委任関係にあることから(会社法330条)、会社に対して善管注意義務を負うことになります(民法644条)。従って、両者ともその職務につき任務懈怠(けたい)が認められる場合には、任務懈怠によって生じた会社の損害に対して、賠償する責任が生じることになります(会社法423条1項)※2。また、同様に第三者が被った損害に対しても、損害賠償責任を負います(会社法429条1項)。仮に、会計関係の不祥事が発生したことによって、会社が損害を被ったときに、監査役と会計監査人がともに任務懈怠責任があると認められれば、会社に対して連帯責任を負うことになります(会社法430条)。
このように、内部監査部門とは異なり、法定監査を担う会社法上の会社機関である両者は、法的責任が明定されていることから、法的権限を行使するに当たっても、会社法上定められた連携義務はもとより、その法的義務を踏まえた実務上の具体的な連携が重要となってきます※3。このような課題意識から、本稿では、会社法制を中心に両者の連携について確認した後、具体的な連携実務、さらには2021年3月期から適用が予定されている金融商品取引法(以下、金商法)上の監査人の監査報告書における「監査上の主要な検討事項」(以下、KAM:Key Audit Matters)の記載への対応※4に向けた監査役と会計監査人との連携実務について解説します。
Ⅱ 会計監査人監査と監査役監査の連携の経緯
1. 明治時代~昭和49年改正商法まで
監査役制度は、明治32年(1899年)の商法時代から存在しており、監査役には会計監査権限がありました。当時は、会計監査人の法的制度が整備されていなかったことから、監査役が業務監査に加えて、会計監査も担っていたことになります。
戦後の昭和25年改正商法において、米国に倣って取締役会に監督機能を付与することと関連して、監査役の業務監査権限は撤廃され、会計監査権限のみとなりました。もっとも、会計の知見を有する監査役ばかりとは限らないことから、会計監査の実効性は不十分と言わざるを得ない状況が続きました。
2. 昭和49年改正商法
その後、山陽特殊製鋼による粉飾決算事件等、企業不祥事が大きな社会問題となったことから、昭和49年改正商法において、監査役に業務監査権限が復活するとともに、職業的専門家である会計監査人による監査制度が創設されることになりました。その際、監査役に付与されていた会計監査権限はそのまま継続されたことから、会計監査については、監査役と会計監査人の両者が行うことになりました。もっとも、会計監査人は会計監査の専門家であることから、実務的には会計監査そのものは、専ら会計監査人が行い、監査役は会計監査の方法と結果の相当性を判断するという形を取ることになりました。このように、昭和49年改正商法をもって、おのおのの特徴を活かした連携の必要性の原型が法制度的に生じるに至ったと理解することができます。
なお、同時に制定された商法特例法(正式名称は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」)において、大会社(当時の定義では、資本の額が5億円以上)では、会計監査人による監査が義務付けられました(商法特例法2条)。大会社の場合には、会計処理は複雑で多岐にわたるために、会計監査人監査が必要と考えられたためです。
3. 昭和56年改正商法~今日
昭和56年改正商法時における商法特例法では、監査役がその職務を行うに際して必要があるときは、会計監査人に対する報告請求権、監査役の全員の同意による会計監査人の解任、取締役に不正や法令・定款違反行為等の重大な事実があったときは会計監査人から監査役への報告義務等が規定されました。昭和56年改正商法を経て、会計監査人と監査役の連携内容が具体的に規定されることとなり、基本的には現行会社法に継承されています(現行法における監査役と会計監査人の両者に関係する内容は<表1>参照)。
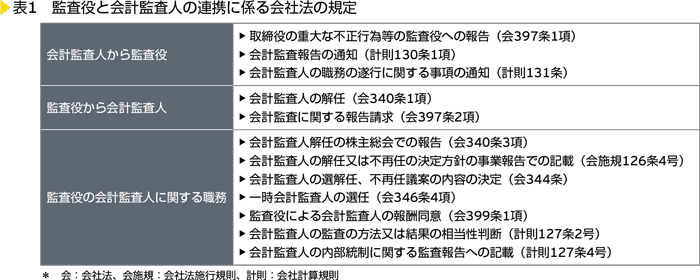
4. 期ずれの問題とインセンティブの捩(ねじ)れの問題
監査役と会計監査人との間の連携に係る主要論点として、「期ずれ問題」と「インセンティブの捩れ」の問題があります。
(1) 期ずれ問題
「期ずれ問題」とは、会社法と金商法との時系列的な差に伴う監査役と会計監査人との関係を表した問題です。内部統制システムを構築し適切に運用する責務を負っているのは取締役であり、内部統制システムを決定・決議した場合には、その内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を事業報告に記載しなければなりません(会社法施行規則118条2号)。それに対して、監査役は、事業報告に記載された内部統制システムの事項についてその内容が相当でないと認めるときには、監査報告の内容としてその旨および理由を記載することになります(会社法施行規則129条1項5号)。監査役は、取締役が内部統制システムを構築し適切に運用しているかについて、取締役の善管注意義務を判断する一環として監査をすることになります。内部統制システムには、会計監査人が直接関与する会計関連の相当性も含むことから、内部統制システムの決議の内容や事業報告の記載内容、並びに内部統制システムに関する取締役の職務執行について指摘すべき点はなく、相当であるとの監査役の判断は、会計監査人の監査の相当性に対する評価も含むことになります。
他方、金商法上の財務報告に係る内部統制システムでは、監査役は統制環境の一部を構成するものと位置付けられており、その中で、会社が作成した財務報告に係る内部統制システムの報告について、監査人が監査証明を付すことになっています(金商法193条の2第2項)。「財務報告に係る」と限定されたものとはいえ、金融庁の実施基準では、全社的な内部統制の評価が求められています。そこで、仮に会社法に基づいた監査役監査報告で内部統制システムが相当である旨の記載を行っても、その後の金商法上の財務報告に係る内部統制システムに対する経営者による有効との評価に監査人が疑義を示した場合には、会社法上の監査役監査報告作成時期と金商法上の監査人の監査証明を付す時期の違いによる期ずれを要因として、監査役と会計監査人の評価が異なったことになります。
(2) インセンティブの捩れの問題
「インセンティブの捩れの問題」とは、会計監査を受ける会社(代表取締役)が会計監査を行う会計監査人の人事権や報酬の決定権を持っていることへの問題を指していました。本問題については、平成26年改正会社法において、会計監査人の人事権は、会社から監査役に移ったこと(会社法344条1項)、一方会計監査人の報酬の決定権は引き続き会社が持つこととなったものの、監査役が報酬に同意をする場合には、公開会社では事業報告にその理由を記載する(会社法施行規則126条2号)規定が置かれ、その実効性が図られたことから、捩れ問題の解消については、一定の進展が図られました。今後は、報酬の決定権についても、監査役に移行する立法措置が行われるか否かが焦点となっています。
Ⅲ KAMの記載も踏まえた会計監査人と監査役の連携の在り方と実務
1. KAMの記載と相互連携の必要性
監査基準によると、「当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項(下線筆者)」を監査人の監査報告に記載することを義務付けるとしています(企業会計審議会、改訂監査基準 第四報告基準二2(2))。従って、監査人は監査役とKAMの記載事項を協議した結果を踏まえて最終的に監査報告を策定することから、KAMの選定を巡って、従来以上に監査役と(会計)監査人との連携が必要となってきます。
KAMについては、「KAMの内容」「当該事項をKAMであると判断した理由」「当該事項に対する監査上の対応」を監査報告に記載します。これらについて、監査役と協議することになるため、監査役としても、自社の業種・業態の特徴に加え、当該事業年度の状況も踏まえた上で、会計監査人との協議に臨む姿勢が大切となります。
以下、KAMの記載制度の導入を見据えて、監査役と会計監査人の連携実務について考えてみます。
2. 期初段階
監査役と会計監査人は、期初の段階で相互に監査計画を説明することが実務では定着しています。その際、KAMを相互に意識して、会計監査人から当該事業年度における監査の基本方針のみならず、重点的に監査を実施しようとしている内容や事業所、さらには具体的な監査の実施要領等について、監査役として説明を受け意見交換を行います。言い換えれば、会計監査人からのKAMの候補項目の説明について、監査役は質疑を通じて意識的に関与する姿勢が求められます。監査役からも、会計監査人に対して重点的に監査の実施を要望する項目があれば、期初の段階で要請します。KAMは、会計監査人の監査結果とは別に、投資家等に対して監査プロセスに関する情報提供としての意義もあることから、積極的な意見交換が望まれます。なお、前年のKAMの記載事項と新年度の記載予定事項との変更の有無についても、期初の意見交換の段階で、監査役は確認すべきです。
加えて、会計監査人からは、会計監査報酬に関係するため、当該事業年度の会計監査延日数と会計監査に携わる会計監査体制について説明を受けます。会計監査延日数は、監査役が執行部門の会計監査人監査報酬案に同意する際の判断基準となりますので、監査役としては、期初の段階で前年実績との差異、新年度において会計監査人の重点監査箇所や項目について納得がいくまで説明を受けるべきです。
3. 期中段階
監査役は、期中時点での節目において、その時点までの会計監査結果の報告を受けます。その際、会計監査の実施状況や会計監査人による経理・財務部門への指摘事項の有無も確認します。会計監査人から経理・財務部門への指摘事項があった場合には、併せて、経理・財務部門との意見の相違が生じたか否かも確認します。会計監査人と経理・財務部門との意見の相違があったとしても、最終的に相互に調整がついていればよいですが、期末時期まで解釈の違いなどにより未調整の場合には、監査役としてどちらの意見が適正であるかの判断も必要となってきます。また、期初に説明を受けた会計監査計画と実績との乖離(かいり)の有無についても確認した上で、乖離があった場合はその理由の説明を受けます。
他方、監査役が実施した期中監査結果の説明を会計監査人にします。監査役の期中監査結果から、グループ会社を含めて会計監査人に対する会計監査の追加要望事項がある場合は、会計監査人に確実に申し入れます。特に、マスメディアで会計不祥事が報道された場合、会計監査人に対して、自社でそのような類似不祥事がないか、追加の重点会計監査の要請を行うこともあり得ます。
KAMとの関連で、期中の段階で発生し将来の財務諸表にも影響を及ぼすと考えられる事象が発生した場合には、事業上のリスク項目としてKAMの記載事項となることも考えられます。特に、事業の不振による減損リスクは、財務諸表にも影響を及ぼす懸念もあります。会計監査人の最終的な監査結果において継続企業の前提に特に疑義がなく、無限定適正意見となれば問題ないといえます。いずれにしても、監査役はKAMに記載される可能性のある事項を特に注視して、会計監査人と重点的に意見交換を行うことになります。また、監査の実施過程において、KAM候補の項目変更が生じた場合には、会計監査人からその理由を含めて説明を受ける機会が適切に設けられるように、日ごろから相互のコミュニケーションと信頼関係を醸成するように心がけるべきです。
4. 期末段階
期末時期においては、監査役は、会計監査結果の報告を受けることが最も重要となります。その際、会計監査人としての会計監査報告を最終的に受領する前段階のドラフト段階で説明を受けた上で、最終的な監査報告とするような段取りが必要です。特に、会計監査人の監査結果として、無限定適正意見の報告書ではないことが想定されるときは、早い段階で相互の意見交換を行うことが重要となってきます。
さらに、監査役は、会計監査人の職務遂行に関する事項、いわゆる会計監査人の内部統制システム状況の確認も必要です。なぜならば、監査役監査報告には、会計監査人の内部統制システムの状況についての記載もあるため、この点について会計監査人から説明を受けます。会計監査人の内部統制システムとは、監査法人の審査体制や責任者に関する事項等であり、会計監査人は書面で監査役に通知義務がありますが(会社計算規則131条)、単に書面で通知を受けるのではなく、直接説明を受けるべきです。その上で、監査役は事業年度を通じて会計監査人の監査の方法と結果の相当性の判断を行い、最終的には、執行部門を通じて株主に提出される監査役監査報告とします。
なお、財務報告に係る内部統制システムやKAMの記載については、金商法上に規定があるため、会社法で定められている監査役監査報告での記載は法定されていません。しかし、財務報告に係る内部統制システムは、全社レベルの内部統制システムにも関係することから、監査人の内部統制システムの評価と監査役の評価に相違がないように、監査役が監査報告を提出する前までに事前に会計監査人と調整しておき、最終的に齟齬(そご)が生じないことが望ましいといえます。前述した期ずれの問題から、内部統制報告書に対する監査人による評価が後ですが、後発事象の問題を除けば、最終的には内部統制システムについて監査役と会計監査人の評価が一致するように、相互に意識すべきです。
またKAMの記載事項についても、金商法の監査報告では必須であるのに対して、会社法上の監査報告への記載は任意となります。仮に会計監査人が会社法上の監査報告にKAMを記載した場合には、会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断する監査役としては、KAMが会計監査人と協議した結果であるとの事情も勘案すれば、監査報告にKAM関連について記載することも十分にあり得ると思います。一方、会計監査人が記載しなかった場合でも金商法上の監査報告では記載が必須となりますので、期ずれ問題も意識して、後に整合性に支障を来さないように監査役としては注意を払うべきです※5。
Ⅳ おわりに
KAMの導入が決定している中、監査役と会計監査人との実効性のある連携はますます重要となってきます。法定監査を行う会社機関として相互の信頼関係を醸成しつつ、監査役は会計監査人の専門性を、会計監査人は監査役の社内状況に精通している特徴を相互に意識して職務を遂行していくことが、コーポレート・ガバナンス上も重要となります。
※1 会計監査人を設置しない会社が、公認会計士や監査法人と監査契約を締結して会計監査を実施することは可能であるが、この場合は会社法上の適用を受けない任意監査となる。
※2 会社法では、任務懈怠の具体的な基準を定めているわけではないので、会計監査人の場合には、例えば企業会計審議会(金融庁長官の諮問機関)が定めた監査基準や日本公認会計士協会が定めた行為準則、監査役の場合には、日本監査役協会が定めた監査役監査基準が一つの目安となる。
※3 九州大学 西山芳喜名誉教授は、監査役と会計監査人との連携の確立は、法による強制ではなく、健全な監査慣行として形成されることであると主張している。西山芳喜『監査役とは何か-日本型企業システムにおける役割-』(同文舘出版、2014年)248ページ
※4 KAMの記載が義務付けられているのは、有価証券報告書提出会社(非上場企業のうち、資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除く)であり、2021年3月決算に係る財務諸表の監査から適用(2020年3月決算からの早期適用も可能)となる。
※5 日本監査役協会と日本公認会計士協会は、平成30年1月25日に「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正している。



