公認会計士 太田 達也
税務上の欠損金が生じた場合の税務上の対応
青色申告法人において税務上の欠損金が生じた場合、前期に繰り戻して還付を請求するか、翌期以降に繰り越して、翌期以降の各年度の所得から控除するかを選択適用することになります。ただし、前期に繰り戻して還付を請求することができるのは、資本金の額または出資金の額が一定額以下である等の一定の法人に限られます。その内容については、前回のコラムをご参照ください。
当期に税務上の欠損金が生じた場合の企業分類について
次のいずれかの要件を満たし、かつ、翌期において、一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる企業は、分類4に該当するものとされています(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」26項)。
① 過去(3年)または当期において、重要な税務上の欠損金が生じている。
② 過去(3年)において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実がある。
③ 当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる。
分類4に該当する場合は、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」27項)。
「重要な税務上の欠損金」の重要性の判断については適用指針において明確にはされていませんが、個々の企業の状況等に応じて判断することが考えられます。当期に発生した欠損金を翌期以降に繰り越す場合に、その欠損金が短期間で解消される、例えば当期に生じた税務上の欠損金が翌期の課税所得によって全額またはほぼ全額解消されるような場合、重要ではないと判断できる場合があると考えられます。逆に、翌期以降一定の年数にわたり控除されることが見込まれる場合のように、その解消に一定の年数を要するような場合には、重要であると判断される場合が多いと考えられます。ただし、一律の形式的な判断基準はなく、個々の企業の状況等に応じて慎重に判断することが必要であると考えられます。
税務上の欠損金を翌期に繰り越す場合の繰延税金資産の回収可能性の判断例
以下、具体的な設例により、説明します。
当期に税務上の欠損金が100生じたが、重要な欠損金ではないと判断され、分類3に該当すると判断され、その判断が適正なものであったものとします。ここで翌期以降5年間の一時差異等加減算前課税所得の見積りに基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断したものとします。
翌期以降(X1期からX5期)の各期の一時差異等加減算前課税所得の見積額、スケジューリングに基づいた当期末の将来加算一時差異および将来減算一時差異のX1期からX5期までの各期の解消見込額が、次の通りであったものとします。
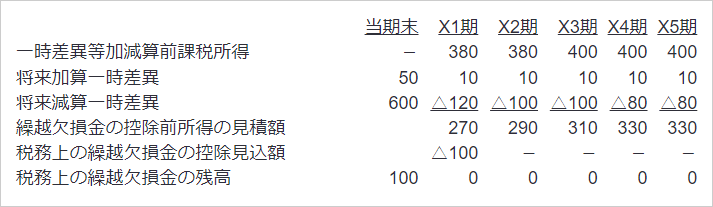
(注)将来減算一時差異のX1期からX5期までの解消見込額の合計額は480(120+100+100+80+80)ですが、当期末の将来減算一時差異600との差額120は、X6期以降に解消が見込まれる額およびスケジューリング不能な将来減算一時差異の額から成っているとします。
上記の例では、税務上の繰越欠損金100はX1期に全額控除できると見込まれており、繰延税金資産の回収可能性はあると判断されます。また、当期末の将来減算一時差異600のうち、480(120+100+100+80+80)について、繰延税金資産の回収可能性はあると判断されます。法定実効税率を30%と仮定すると、(100+480)×30%イコール174の繰延税金資産を計上することが考えられます。
当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。


