EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2019年12月号 押さえておきたい会計・税務・法律
公認会計士 太田 達也
当法人のフェローとして、法律・会計・税務などの幅広い分野で助言・指導を行っている。また、豊富な知識・経験および情報力を生かし、各種実務セミナー講師、講演等において活躍している。著書は多数あるが、代表的なものとして『会社法決算書作成ハンドブック』(商事法務)、『「純資産の部」完全解説』『「解散・清算の実務」完全解説』『「固定資産の税務・会計」完全解説』(以上、税務研究会出版局)、『例解 金融商品の会計・税務』(清文社)、『減損会計実務のすべて』(税務経理協会)などがある。
Ⅰ はじめに
資本金の減少を「減資」といいます。減資は、会社法上、資本金という計数を減少させる行為です。資本金を減少し剰余金に計上するケースが多いわけですが、資本金の減少により生じたその他資本剰余金を原資として剰余金の配当を行ったり、自己株式の取得財源に用いたりすることが可能です。一方、資本金の減少により生じたその他資本剰余金を利益剰余金のマイナスに充当するケースも少なからずみられます。これを「欠損てん補」といいます。
本稿では、資本金の減少について、法律、会計および税務の観点から詳しく解説します。なお、本稿の意見にわたる部分は、筆者の私見であることをお断りしておきます。
Ⅱ 減資の法務
1. 減資の意義
減資とは、会社法上、単に資本金を減少させる行為であり、会社法447条の規定が根拠となります。原則として株主総会の特別決議が必要になりますが、別途会社法449条が定める債権者保護手続(官報公告および催告)を行う必要があります。
会社法において、減資は資本金という計数を減少させるという意味しかありません。①株主に対する払戻し、②欠損てん補(利益剰余金のマイナスに充当)または③株式数の減少を伴うかどうかは、減資とは直接関係がなく、個々の案件ごとに判断されます。
資本金を減少した結果、その他資本剰余金が計上されますが、その他資本剰余金を原資として剰余金の配当を行うのであれば、別途会社法454条による剰余金の配当の決議を採って行うことになりますし、その他資本剰余金による欠損てん補(利益剰余金のマイナスに充当)を行うのであれば、会社法452条による剰余金の処分※1の決議を採って行うことになります。欠損てん補のみを目的とするのであれば、株式数の減少も株主に対する払戻しも行いません。その他資本剰余金として計上したままでも問題ありません。
なお、企業再生の場面において、増資と減資を両方行う、いわゆる増減資が行われることがありますが、この場合は既存の株主の株式を消滅(または減少)させるために、発行済株式数の減少を併せて行う場合が多いと思われます。このケースにおいては、資本金の減少の決議(会社法447条)だけではなく、自己株式の取得の決議(会社法156条、157条)または株式併合の決議(会社法180条)を採って行うことになります※2。また、資本金の減少によって発生したその他資本剰余金は、その全額を欠損てん補に充てる場合が多いと考えられます。
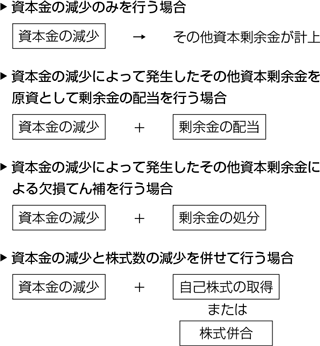
2. 減資の手続
減資を行うときは、株主総会の決議と債権者保護手続(公告、催告)が必要です。株主総会では、次の事項を決議しなければいけません(会社法447条1項)。
<減資の決議事項>
① 減少する資本金の額
② 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額
③ 資本金の額の減少がその効力を生ずる日(効力発生日)
減資は重要な決定事項ですので、原則として、株主総会の特別決議が必要です(会社法309条2項9号)。ただし、定時株主総会で決議する場合で、かつ、資本金の減少額の全額を欠損てん補に充当するものについては、株主への影響がより少ないため、普通決議要件とされています(会社法309条2項9号かっこ書)。
また、官報に公告をし、かつ、知れている債権者に対して催告(個別の通知)を行う必要があります(会社法449条1項)。債権者の中で異議のある者は異議を申し述べることができる旨を公告および催告により知らせるためです。債権者からみれば、資本金が減少し剰余金に計上されることによって、剰余金の配当や自己株式の取得の財源となるため、会社の財産が株主に流出することになる可能性を生じさせることを意味しており、債権者を害する可能性があるからです。ただし、官報公告および定款の定めによる電子公告(または日刊新聞紙による公告)を両方行う場合は、催告を省略することができます(会社法449条3項)。
なお、減資に対して異議を申述する債権者が生じ、異議を撤回しない場合は、個別の弁済、担保提供または信託のいずれかの対応が必要になります(会社法449条5項)。債権者が異議を申述した場合の個別の弁済等の手続が必要な場合は、その手続が終了しない限り、債権者保護手続は終了しないものとされます。債権者保護手続が終了しない限り、減資の効力も生じないこととなる点に留意する必要があります。
3. 欠損てん補のための減資
剰余金の分配可能額がマイナスである場合、将来的に当期純利益が発生しても、そのマイナスを上回らない限り、剰余金の分配可能額は直ちにプラスになりません。当期純利益が発生しても、すぐには剰余金の配当や自己株式の取得を行うことができないということになります。
ところが、減資により欠損てん補をすると、利益剰余金のマイナスがてん補され、剰余金の分配可能額が増加します。剰余金の分配可能額のマイナスを解消しておけば、その後当期純利益が発生したときに、配当や自己株式の取得を行うことが可能となります。このように、業績が好転した後に配当等を行いやすいようにするために、欠損てん補のための減資を行うケースは少なくありません。単に欠損てん補のための減資のみを行う場合もありますし、企業再生の場面で増資と組み合わせて行われる場合もみられます。
減資による欠損てん補を行った場合は、会計上も、資本金の減少と剰余金の増加(=マイナスの減少)を認識します。しかし、税務上は、同じ株主資本の中で振り替えているだけであり、株主に対する払戻しもないため、何もなかったものとして取り扱い、資本金等の額にも利益積立金額にも変動は生じません。この点は後で詳しく解説します。
Ⅲ 減資の会計
会計処理は、会社法の取扱いがベースになります。会社法上、資本金の減少を認識し、剰余金に計上するのであれば、会計上もその内容のとおりの処理を行います。
大きく①欠損てん補のための減資②欠損てん補以外の減資および③剰余金の配当を伴う減資の三つに分けて解説します。
1. 欠損てん補のための減資の会計処理
ここでいう「欠損」の額とは、剰余金の分配可能額のマイナスの額を想定しています。利益剰余金のうちの「繰越利益剰余金」がマイナスになっているものとします。減資の効力発生日に次の仕訳が起きます。
会社法上、資本金の減少と剰余金の処分の規定は別個であり、二つの仕訳の金額や効力発生日が同じでなければならないという制約は特にありません。そのため、二つの仕訳で表しています。
減資の効力発生日以後に到来する決算期においては、貸借対照表の資本金の額と繰越利益剰余金の額は減資後の金額で表示されますし、減資の効力発生日を含む事業年度の株主資本等変動計算書上では、資本金の減少と繰越利益剰余金の増加が表示されます。
なお、企業会計上、利益剰余金がプラスの場合には、その他資本剰余金から利益剰余金に振り替えることは認められていません。企業会計原則で禁じられている「資本と利益の混同」に当たるからです。しかし、利益剰余金がマイナスである場合には、そのマイナスの範囲内でその他資本剰余金から利益剰余金に振り替えることは認められています。この点について、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」第61項において、「利益剰余金がマイナス残高のときにその他資本剰余金で補てんするのは、資本剰余金と利益剰余金の混同にはあたらないと考えられる。もともと払込資本と留保利益の区分が問題になったのは、同じ時点で両者が正の値であるときに、両者の間で残高の一部または全部を振り替えたり、一方に負担させるべき分を他方に負担させるようなケースであった。マイナス残高になった利益剰余金を、将来の利益を待たずにその他資本剰余金で補うのは、払込資本に生じている毀損(きそん)を事実として認識するものであり、払込資本と留保利益の区分の問題にはあたらないと考えられる。」と説明されています。
2. 欠損てん補以外の減資の会計処理
欠損てん補以外の減資の場合、資本金が減少し、その他資本剰余金が計上されます。
減資の効力発生日以後に到来する決算期においては、貸借対照表の資本金の額とその他資本剰余金の額は減資後の金額で表示されますし、減資の効力発生日を含む事業年度の株主資本等変動計算書上では、資本金の減少とその他資本剰余金の増加が表示されます。
3. 剰余金の配当を伴う減資の会計処理
会社法においては、旧商法における「有償減資」(減資に際して株主に対して払戻しを行うこと)という類型はなく、減資と剰余金の配当の二つを組み合わせる方法により行います。
減資によって発生したその他資本剰余金を原資として配当する場合は、減資の効力発生日以後に配当を行うことになります。その他資本剰余金の配当は、後で詳しく説明するように、税務上はみなし配当が生じ得ます。ここでは、みなし配当に係る源泉所得税の徴収が必要であり、徴収した税額が預り金に計上されますが、ここでは捨象します。
Ⅳ 減資の税務
減資の税務ですが、そこで株主に対する払戻し(剰余金の配当)を行うかどうかで大きく異なります。以下、無償減資の場合と剰余金の配当を伴う減資の場合に分けて、税務処理について説明します。
1. 無償減資の税務処理
無償減資の場合、株主資本の中で振り替えているだけであり、株主に対する金銭等の払戻しがありませんので、税務上は何もなかったものとして取り扱います。要するに、資本金等の額にも、利益積立金額にも変動は生じませんし、所得の金額にも影響はありません。欠損てん補のための減資も同様です。
税務上は仕訳なしということになりますが、会計上は先に説明しましたように、次の仕訳が起きます。
<欠損てん補のための減資の場合>
<欠損てん補以外の減資の場合>
欠損てん補以外の減資の場合は、法人税申告書の別表五(一)の「資本金等の額の計算に関する明細書」の1行目「資本金または出資金」の減少欄と、空白欄に「その他資本剰余金」と記載してその増加欄にそれぞれ同額を記載すればよいと考えられます。
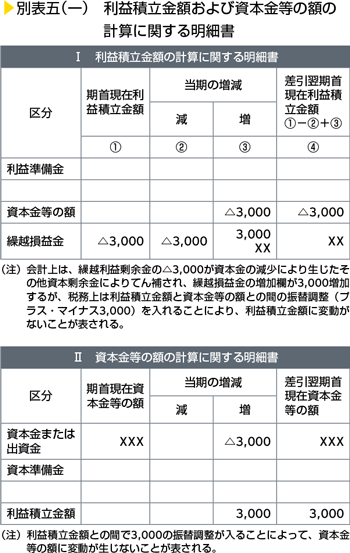
一方、欠損てん補のための減資の場合は、一定の申告調整が必要になります。以下、3,000の欠損てん補をしたものと仮定し、申告調整の方法を示します。
なお、無償減資の場合、法人税法上の資本金等の額に変動は生じませんが、法人住民税の均等割の税率区分の基準となる額の算定上、欠損てん補額を減算することになります(地法23条1項4号の5イ(3))。
2. 剰余金の配当を伴う減資の税務処理
剰余金の配当を伴う減資の場合ですが、資本金の減少とは切り離して、税務上は配当の原資が利益剰余金であるかその他資本剰余金であるかによって処理が異なります。減資によって発生したその他資本剰余金を原資として配当する場合は、次のとおりの処理となります。
(1) 配当した法人の税務処理
その他資本剰余金を原資として配当した場合は、まず①資本金等の額の減算すべき金額(以下、減資資本金額)を計算し、次に②配当の額(交付金銭の額)がその金額(①の金額)を上回る場合に限り、その超過額について利益積立金額を減算します(法令8条1項18号、9条1項12号)。
具体的には、資本金等の額の減算額と利益積立金額の減算額を次のように区分計算する必要があります。
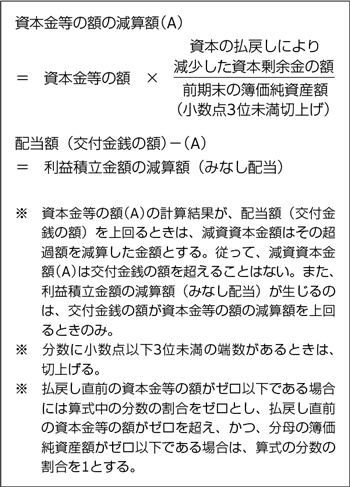
会計上は、その他資本剰余金の減少のみになっていますので、<設例>のような申告調整が必要になります。
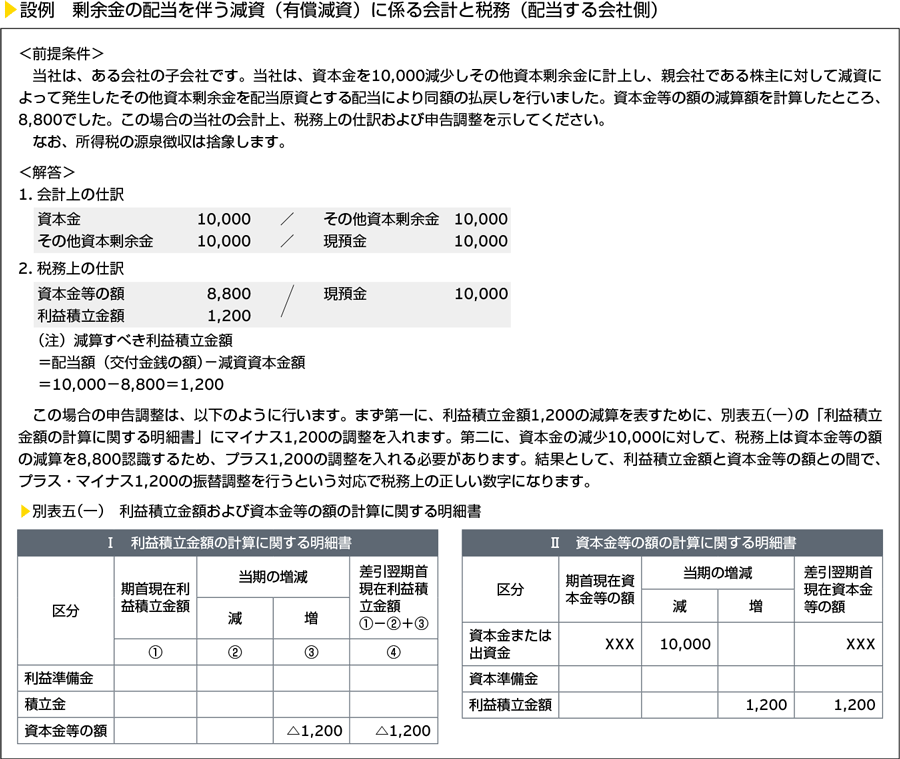
なお、株主が複数である場合は、株式数に基づいて、株主ごとの金額を計算しなければなりません。みなし配当について所得税の源泉徴収が必要ですので、支払通知書も株主ごとに作成し、各株主に送付します。
(2) 株主の税務処理
配当をした法人において利益積立金額の減算が行われた場合は、それは株主にとって「みなし配当」となります(法法24条1項4号、所法25条1項4号)。
資本金等の額に対応する額は、株主にとって株式の譲渡対価の額となり、利益積立金額に対応する額は株主にとって「みなし配当」(法人株主の場合は受取配当金、個人株主の場合は配当所得に係る収入金額)となります。また、株式の譲渡原価の額は、株主の有する株式の帳簿価額に払戻割合(前期末の簿価純資産額に占める資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額の占める割合)を乗じた額となりますが、払戻割合は配当を行った法人から株主に対する通知事項とされています(法令119条の9第2項、所令114条5項)。
なお、株主は、次のように配当を行った法人からの通知により処理を行うことができます。
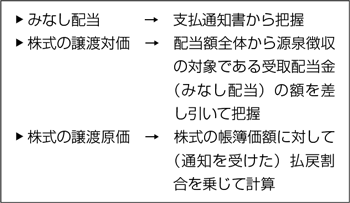
(注) 文中、法令条文等は、以下のとおり略して記載しています。
法法:法人税法
法令:法人税法施行令
所法:所得税法
所令:所得税法施行令
地法:地方税法
※1 剰余金の処分とは、剰余金間の振替を想定した手続であり、別途積立金の積立て・取崩しもこの手続による。また、その他資本剰余金による欠損てん補も、剰余金間の振替に当たるため、この手続が根拠となる。
※2 債務超過会社の場合は、通常無償取得によることになる。また、既存の株主の株式を減少させる方法として、株式併合が用いられる場合もある。



