EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2018年10月号 Tax update
EY税理士法人 税理士・公認会計士 矢嶋 学
1998年、太田昭和アーンストアンドヤング(現EY税理士法人)に入所。法人向けコンプライアンス業務のほか、組織再編及び事業承継コンサルティング、大規模法人を対象とした税務リスク・アドバイザリー業務等に従事。EY税理士法人入所以前は、国税職員として相続税、法人税の調査経験を有する。
Ⅰ はじめに
平成30年度の税制改正において、法人税額を計算する際の原則規定である法人税法第22条関連が改正されました。当該改正は収益認識に関する会計基準の制定に伴って税法上の取扱いを明確化したものであり、今までの法人税の考え方を変える内容ではありません。また、当該改正を受けて法人税基本通達(以下、「通達」又は「法基通」)の改正も行われています。
本稿では、法人税法第22条に関する改正内容と通達により取り扱いが明確化された事項のうち主要なものについて解説します。
Ⅱ 収益認識に関する会計基準の概要
1. 基本となる原則
収益認識の原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識することであり(収益認識に関する会計基準16項)、この原則に従って収益を認識するために五つのステップが適用されます(<図1>参照)。
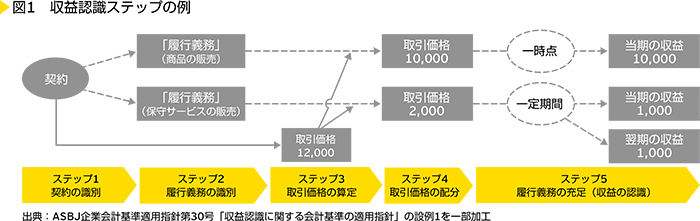
2. 適用対象
収益認識に関する会計基準は、連結財務諸表と個別財務諸表の両方に対して同一の会計処理が適用されます。よって当該基準は、個別財務諸表をもとに計算する法人税の課税所得にも影響を与えることになります。
なお、いわゆる中小企業にあっては、収益認識に関する会計基準を適用することも可能となりますが、一方でこれを適用しないことも認められます。
3. 適用時期
収益認識に関する会計基準は、平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。
ただし、早期適用として、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが可能となっており、また、これに加えて、平成30年12月31日から平成31年3月30日までの間に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができます(収益認識に関する会計基準81から83項)。
Ⅲ 法人税法の改正
1. 平成30年度税制改正
収益認識に関する会計基準の導入を契機として、法人税における収益の認識についても改正が行われました。具体的には、法人税法第22条の2及びこれに関連する法人税法施行令第18条の2が創設され、収益の計上時期、計上額に関する規定が定められました。
収益認識に関する会計基準の「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する」という考え方は、法人税法における実現主義又は権利確定主義の考え方と整合的であるため、一部の例外処理を除き、法人税でもこの考え方を取り込むこととしています。
2. 法人税法第22条と第22条の2の関係
ここで従前からある法人税法第22条と新たに創設された法人税法第22条の2との関係について確認しておきたいと思います。
法人税法第22条は各事業年度の所得の金額を計算する際の通則規定として、益金の額に算入すべき金額や損金の額に算入すべき金額に関する一般原則が定められるとともに、これらの金額は一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算することが規定されています。
一方、法人税法第22条の2は、第1項から第3項に益金の額に算入すべき収益の計上時期を、第4項と第5項に益金の額に算入すべき収益の金額、そして第6項に現物配当を行った場合の収益の額が規定されています。つまり、益金の額について両方の条文に規定が存在することになりますが、そこは今回の改正で法人税法第22条と法人税法第22条の2の規定が抵触する場合には、法人税法第22条の2の規定を優先的に適用することとされました。
例えば、資産の販売もしくは譲渡又は役務の提供(以下、資産の販売等)に係る取引については、別段の定めがあるものを除き、その取引の収益の額を益金の額に算入すべきことが法人税法第22条第2項で規定され、認識の時期及び益金の額をいくらとするかについては法人税法第22条の2の規定、認識の単位は法人税法第22条第4項の規定を用いることになっています。
Ⅳ 具体的な改正点
1. 収益の計上時期
(1) 原則的な取り扱い(原則処理<図2>)
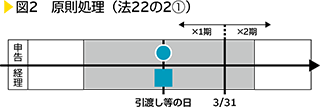
資産の販売等に係る収益の額は、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入されることが明確化されました(法法22の2①)。しかし、税制改正前から通達において引渡しの日や役務提供の時期が定められていたため、実務上の取り扱いに大きな変更はありません。例えば、棚卸資産の引渡しの日は、出荷した日、相手方が検収した日等、引渡しの日として合理的であると認められる日を継続して適用することが従前の通達において示されていました。改正後の通達では、これらに加えて、船積みをした日、相手方に着荷した日などの例も示されています(法基通2-1-2)。
(2) 認められる収益計上時期(例外処理1<図3>)
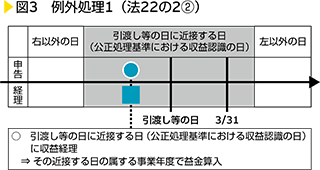
法人税では、委託販売における仕切精算書到達日基準や電気業・ガス業における検針日基準など、引渡しの日以外の日を基準として収益を認識する会計原則・会計慣行に従った処理を是認してきました。このような引渡し等の日以外の日に収益計上した場合への対応として、契約の効力が生ずる日もしくは資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日に近接する日の属する事業年度において収益として経理したときは、これを認めることが明らかにされています(法法22の2②)。
(3) 別表調整による収益計上時期(例外処理2<図4、5>)
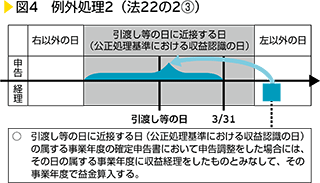
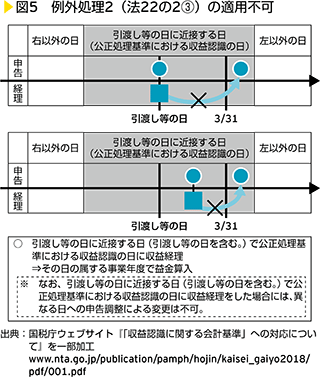
資産の販売等に係る収益計上については、前記(2)に記載の「近接する日」の属する事業年度における法人税の申告書に別表調整の方法で益金の額に算入することもできます。ただし、会計上の収益計上日が前記(1)又は(2)に規定する日である場合には、(1)又は(2)の適用により同日が一般に公正妥当な会計処理の基準に従った益金計上日とされるため、別表調整によって益金計上日を変更することはできません(法法22条の2③)。
(4) 割賦基準・延払基準の廃止
前記(1)から(3)及び改正後の法人税法第63条の規定により、従前は適用可能であった割賦基準・延払基準による収益の計上が法人税において認められないことになります。ただし、平成30年4月1日前に長期割賦販売等(リース譲渡を除く)を行った法人については、一定の経過措置が適用されます。
2. 収益の計上金額
(1) 原則的な取り扱い
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準においては、資産の販売等により企業が権利を得ると見込む対価の額により取引価格を算定し、その取引価格をもって収益の額を計上します。一方、法人税では従前から時価に基づく課税を
原則としており、販売・譲渡をした資産の引渡し時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額(以下、引渡し時の価額等)をもって益金の額に算入することになります。取引価格が引渡し時の価額等と同額であれば税務調整は不要となりますが、同額でないときは法人税申告書において別表調整が必要となります。また、通常の値引き、リベート、返金など、時価をより正確に反映させるための手続きといえる部分は、その反映後の対価をもって引渡し時の価額等とされます。
なお、対価の回収可能性や返品の可能性については、これを取引対価の算定に含めると、法人税で予定している時価とは異なることになるため、次の(2)及び(3)のとおり、対価の額に含めない規定が置かれています。
(2) 貸倒引当金
収益認識に関する会計基準では、対価を回収する可能性を評価した上で取引価格を算定するため、金銭債権の貸倒れ見積り額を控除した後の金額をもって収益計上されます。貸倒引当金相当額は取引価格を算定する際の一要素となりますが、法人税では従前から貸倒引当金は一定の法人を除き損金不算入とされており、また、対価の回収可能性は引渡し時の価額等の算定とも異なるため、これを考慮しないことになっています(法法22条の2④)。
(3) 返品調整引当金
収益認識に関する会計基準では、買戻し特約が付された取引について買戻しによる返金の見込み額を収益の額から控除することとされています。法人税では他の多くの引当金が既に廃止されており、公平性、明確性の観点から一定の経過措置を講じた上で廃止となっています。また、将来の返品の可能性は通常得べき対価の額の算定とも異なるため、益金の額の算定に含まれません(法法22条の2④)。
3. 通達で認められる処理
収益認識に関する会計基準の制定及び法人税法の改正に伴い、次の整備方針の下に通達を改正しています。
- 新会計基準は収益の認識に関する包括的な会計基準である。履行義務の充足により収益を認識するという考え方は、法人税法上の実現主義又は権利確定主義の考え方と齟齬をきたすものではない。そのため、改正通達には、原則としてその新会計基準の考え方を取り込んでいく。
- 一方で、新会計基準について、過度に保守的な取扱いや、恣意的な見積りが行われる場合には、公平な所得計算の観点から問題があるため、税独自の取扱いを定める。
- 中小企業については、引き続き従前の企業会計原則等に則った会計処理も認められることから、従前の取扱いによることも可能とする。
出典:国税庁ウェブサイト『「収益認識に関する会計基準」への対応について』
整備方針の2番目には、税独自の取り扱いを定める旨が掲げられています。例えば、自己発行ポイント等(ポイント又はクーポンその他これらに類するもの)を付与した場合の通達として法基通2-1-1の7が新設されました。ここでは、次のような一定の要件を設けて、会計基準とは異なる取り扱いを定めています。
- 次に掲げる要件の全てに該当するときは、継続適用を条件として、自己発行ポイント等について当初の資産の販売等とは別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとすることができる。
(1) その付与した自己発行ポイント等が当初の資産の販売等の契約を締結しなければ相手方が受け取れない重要な権利を与えるものであること
(2) その付与した自己発行ポイント等が発行年度ごとに区分して管理されていること
(3) 法人がその付与した自己発行ポイント等に関する権利につきその有効期限を経過したこと、規約その他の契約で定める違反事項に相手方が抵触したことその他の当該法人の責に帰さないやむを得ない事情があること以外の理由により一方的に失わせることができないことが規約その他の契約において明らかにされていること
(4) 次のいずれかの要件を満たすこと
イ その付与した自己発行ポイント等の呈示があった場合に値引き等をする金額が明らかにされており、かつ、将来の資産の販売等に際して、たとえ1ポイント又は1枚のクーポンの呈示があっても値引き等をすることとされていること
ロ その付与した自己発行ポイント等が当該法人以外の者が運営するポイント等又は自ら運営する他の自己発行ポイント等で、イに該当するものと所定の交換比率により交換できることとされていること
- 前受けとされた自己発行ポイント等については、原則としてその使用に応じて益金算入する一定期間経過後等の未使用部分の一括収益計上については、商品引換券等の取扱いと同様
出典:国税庁ウェブサイト『「収益認識に関する会計基準」への対応について』
この他にも、法基通2-1-1の11(変動対価)、法基通2-1-39(商品引換券等の発行に係る収益の帰属時期)、法基通2-1-39の2(非行使部分に係る収益の帰属の時期)などで税独自の要件が定められているため、留意が必要です。
また、今後は収益認識に関する会計基準を適用する法人と適用しない法人の両方が存在することになります。整備方針(Ⅳ3.参照)の3番目にあるとおり、従前の取り扱いも残す必要があることから、収益認識に関する会計基準を適用している法人にのみ適用される通達と、全ての法人に対して適用される通達の2種類が存在することになりました。実務上、どちらの通達なのか判断した上で適用することが重要となります。
具体的には、法基通2-1-1(収益の計上の単位の通則)の本文中で定義された「資産の販売等」という用語、そして法基通2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)の本文中で定義された「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という用語を用いた通達(範囲指定された通達番号に限る)が収益認識に関する会計基準を適用した取引に関する通達です。それ以外の通達は全ての法人に対して適用されることになるため、その使い分けに関しては留意が必要です。
(注) 文中、法令条文等は、以下のとおり略して記載している箇所がございます。
法法:法人税法
法基通:法人税基本通達



