EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

情報センサー2017年3月号 会計情報レポート
会計監理部 公認会計士 村田貴広
品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務に従事。主な著書(共著)に『減損会計の実務詳解Q&A』『ここが変わった!税効果会計―繰延税金資産の回収可能性へのインパクト』(いずれも中央経済社)などがある。
Ⅰ はじめに
平成27年12月に公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、回収可能性適用指針)は、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となります。本稿では、回収可能性適用指針の原則適用に係る平成29年3月期決算に当たっての留意事項を解説します。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りします。
Ⅱ 回収可能性適用指針の原則適用に当たっての留意事項
1. 回収可能性適用指針の基本的な考え方
回収可能性適用指針は、これまで繰延税金資産の回収可能性の判断に当たっての指針であった監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(以下、66号)における基本的な枠組みである、企業の「分類」に応じて繰延税金資産の回収可能性を判断するという考え方を踏襲しています。すなわち、企業を(分類1)から(分類5)の五つの分類に分け、それぞれの分類に応じた定めに従い、繰延税金資産の回収可能性を判断するとしたこれまでの方法を基本的に引き継いだ上で、次のような観点から一部の定めを必要に応じて見直しています。
- より企業の実態に沿った結果となるような見直し
- 過去を過度に重視したこれまでの例示区分の見直し
このように、回収可能性適用指針は、66号の基本的な考え方は踏襲しているものの、要件や文言が変更されている箇所があり、適用の影響は各社各様であるため、それぞれ慎重に検討する必要があります。
2. 66号からの主要な改正点
(1) 主要な改正点の概要
回収可能性適用指針では、66号の定めと比べて、<表1>に記載した点などが見直されています。
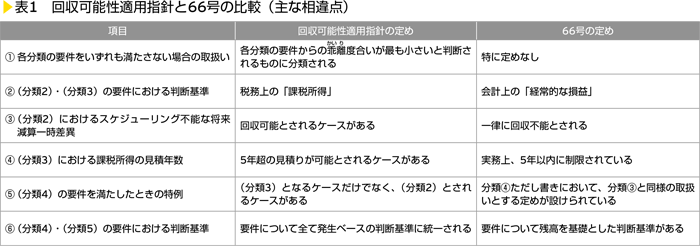
<表1>のうち、③から⑤の項目は、それぞれの原則的な取扱いに対して、「企業が合理的な根拠をもって説明する場合」に限って特例規定が適用となる、いわゆる「反証規定」となっており、会社が自らの意思により説明するかどうかによって、繰延税金資産の計上額が異なることになる点に留意が必要です。
以下では、<表1>の③から⑤の項目について解説します。
(2) (分類2)におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異
回収可能性適用指針では、(分類2)に該当する企業において、原則として従前の66号と同じくスケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産につき、その回収可能性がないものとされています。ただし、将来いずれかの時点で損金に算入される可能性が高いと見込まれるものに関しては、当該将来いずれかの時点で回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合に、この将来減算一時差異に係る繰延税金資産には回収可能性があるものとされています。
回収可能性適用指針では、この定めが用いられる具体的なケースとして、過去に減損処理を行った上場株式(いわゆる政策保有株式)や役員退職慰労引当金が挙げられています。しかし、この定めを適用することができるかどうかは、形式的に政策保有株式や役員退職慰労引当金に係る一時差異に該当するかという判断ではなく、将来いずれかの時点で損金に算入される可能性が高いと見込まれるものに関し、当該将来いずれかの時点において、スケジューリング不能な将来減算一時差異を課税所得が上回る見込みが高いかどうかを慎重に判断することが求められる点に留意が必要です。
(3) (分類3)における課税所得の見積年数
回収可能性適用指針では、(分類3)に該当する企業において、原則として、従前の66号と同じく将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得※の見積額に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断することとされています。また、将来の合理的な見積可能期間が、一定のケースで5年以内のより短い期間となる定めが設けられている点も、66号と同様です。
ただし、66号と異なり、次の点を勘案して、5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされます。
- 臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している原因
- 中長期計画(おおむね3年から5年の計画が想定されている。以下同じ)
- 過去における中長期計画の達成状況
- 過去(3年)及び当期の課税所得の推移 など
なお、この定めは、前述のとおりいわゆる「反証規定」であり、その実態を適切に判断することが求められます。回収可能性適用指針では、5年超の回収可能性が認められる可能性があるケースとして、次のような例を挙げているため、判断に当たっての参考になります。
- 製品の特性により需要変動が長期にわたり予測できるときに、当該需要変動の推移から課税所得が大きく増減している原因を合理的な根拠をもって説明できるような場合
- 長期契約が新たに契約されたことにより、長期的かつ安定的な収益が計上されることが明確になる場合(長期契約の内容を勘案することが必要)
(4) (分類4)の要件を満たしたときの特例
回収可能性適用指針では、(分類4)に該当する企業において、原則として、66号と同じく翌期1年間のみの一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断するとされています。
また、(分類4)の要件を満たす企業で、次の点を勘案し、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときには(分類3)に、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明するときには(分類2)に該当するものとして取り扱われます。
- 重要な税務上の欠損金が生じた原因
- 中長期計画
- 過去における中長期計画の達成状況
- 過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移 など
66号においても、重要な税務上の繰越欠損金等が「非経常的な特別の原因」により発生した場合には、分類④に該当する企業であっても、分類③と同様の回収可能性の判断をする定めが設けられていました。ただし、回収可能性適用指針における(分類4)の要件を満たす企業が(分類3)に該当するケースでは、将来の一時差異等加減算前課税所得の発生見込みが含まれるなど、66号とはその要件が異なっていることに留意が必要です。この(分類4)の要件を満たす企業が(分類3)に該当するケースの例として、回収可能性適用指針では、当期に代替的な原材料が開発されたことにより、業績の回復が見込まれ、その状況が将来も継続することが見込まれるような場合が挙げられています。
また、(分類4)の要件を満たす企業が(分類2)に該当するケースは回収可能性適用指針で新たに設けられた定めです。回収可能性適用指針において、このようなケースは、前述の(分類4)の要件を満たす企業が(分類3)に該当するケースよりも少ないと考えられるとされている点に留意が必要です。この(分類4)の要件を満たす企業が(分類2)に該当するケースの例として、回収可能性適用指針では、当期において災害による損失が発生した場合の例が挙げられています。
(5) 適用初年度の期首において反証規定を適用しなかった場合の取扱い
回収可能性適用指針は、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となるので、適用初年度の期首において前述の(2)から(4)の反証規定を適用しなかった場合、適用初年度の年度末において反証規定を適用することが認められるかが実務上の論点となります。この点、これらの反証規定は、企業の実態をより適切に財務諸表に表すために設けられたものであることから、何ら状況の変化がない中で、期首では当該規定を適用せず、当該年度末では適用するような取扱いが認められると、企業の実態が適切に表されなくなり、反証規定の趣旨に反することになります。従って、期首においてこれら反証規定を適用しなかった場合には、企業の実態に影響を及ぼすような企業内外の何らかの環境変化がない限り、当該年度末においては反証規定を適用することができないと考えられる点に留意が必要です。
3. 経過措置及び適用初年度の開示
(1) 経過措置
回収可能性適用指針には経過措置が設けられており、前年度以前に遡及することなく、適用初年度期首の利益剰余金等に、会計方針の変更に係る影響額を加減算します。
また、回収可能性適用指針の適用による全ての影響を会計方針の変更の影響額として捉えるのではなく、従前の66号の定めの内容を実質的に変更していると考えられる前出<表1>の③、④及び⑤((分類2)に該当するものとした場合)の3項目のみを会計方針の変更の影響額とし、その他の影響に関しては、損益に計上することとされました。
なお、会計方針の変更の注記においても、影響額として注記されるのは前記の「会計方針の変更の影響額」とされる3項目の影響額のみとなります。
(2) 会計方針の変更による影響額がない場合の注記
回収可能性適用指針の適用に当たって、前述の「会計方針の変更の影響額」とされる3項目の影響額がないとき、会計方針の変更の注記が必要となるかどうかが論点となります。この点、「会計方針の変更の影響額」とされる3項目の定めを適用しない限り、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱われないため、会計方針の変更の注記を記載する必要はありません。この場合であっても、回収可能性適用指針を適用した事実を財務諸表利用者に開示するために、追加情報としてその旨を記載することが考えられますが、会計方針の変更ではないことから、影響額の記載は必ずしも想定されていません。
※ 一時差異等加減算前課税所得とは、将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度において解消することが見込まれる当期末に存在する将来加算(減算)一時差異の額(及び該当する場合は、当該事業年度において控除することが見込まれる当期末に存在する税務上の繰越欠損金の額)を除いた額をいう。これは、(分類3)及び(分類4)の企業で、スケジューリングされた将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を判断する際に比較する課税所得の概念を明確化するために回収可能性適用指針において定義されている。



