公認会計士 太田 達也
完全支配関係がある子法人の残余財産の確定に係る税務
平成22年度税制改正により、完全支配関係がある他の内国法人が解散し、残余財産が確定した場合、その清算法人の繰越欠損金のうち未使用のもの(未処理欠損金額)を完全支配関係がある株主法人に引き継ぐこととされました(法法57条2項)。
また、完全支配関係がある子法人が解散し、親法人がその子法人から残余財産の分配を受けないことが確定した場合、親法人において子法人株式の消却損を損金算入しないものとされました(法法61条の2第16項)。
税務上、子法人株式の評価損の計上が認められない場合
子法人の残余財産が確定するよりも前に到来する親法人の決算期において、会計上、子法人株式の評価損を計上するケースがあります。この点については、平成23年6月30日付公布の税制改正では、100%グループ内の他の内国法人が①清算中である場合、②解散(合併による解散を除く)をすることが見込まれる場合、又は③当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるものである場合、以上の三つのケースのいずれかに該当する場合には、その他の内国法人の株式について評価損を計上しないこととされました(法法33条5項、法令68条の3第1項)。
このように改正されたのは、残余財産が確定する前に到来する親法人の決算期における子法人株式の評価損の損金算入を認めてしまうと、親法人にとって子法人株式の評価損と未処理欠損金額の引継ぎという2重のメリットが生じることになり、消却損を損金不算入とした取扱いとのバランスを欠くことになるからです。
完全支配関係がある子法人が上記の①から③のいずれかに該当する場合に、会計上、子法人株式の評価損を計上するときは、その評価損を損金算入することはできませんので、有税で処理(別表4で加算)することになります。
また、子法人株式評価損否認金が残った状態で、子法人の残余財産が確定したときに、どのように処理するかが問題になります。税務上は、親法人がその子法人から残余財産の分配を受けないことが確定した場合、親法人において子法人株式の消却損を認識せず(法法61条の2第16項)、子法人株式の帳簿価額相当額について、資本金等の額の減少を行います(法令8条1項20号)。
以下、具体例により、上記の処理を示します。
有税の評価損否認金と別表調整の方法
100%子法人の残余財産が確定する前に到来する親法人の決算期(X1期)において、会計上、子法人株式の帳簿価額300について全額を減損処理したとします。また、このときにその子法人の解散が見込まれているものとします。法人税申告書の別表4で加算(留保)の調整をすることになります。
1. X1期
別表4 所得の金額の計算に関する明細書
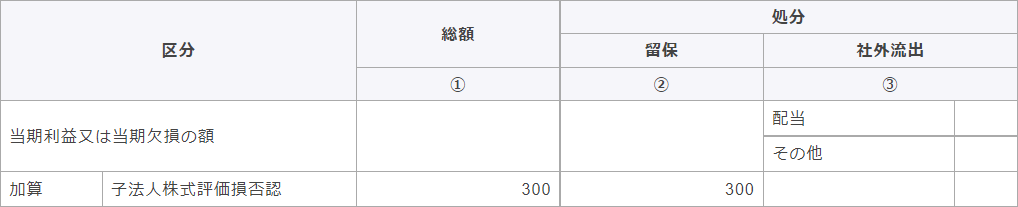
別表5(1) 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書
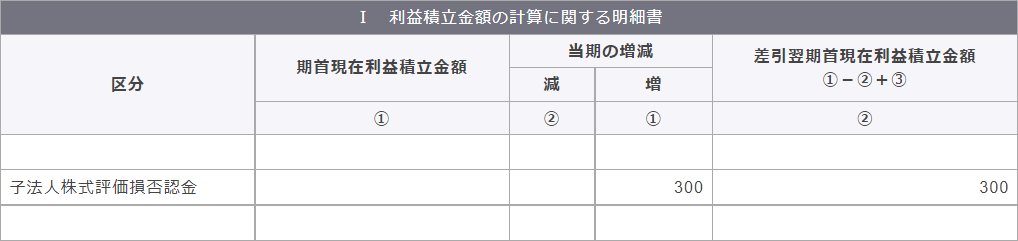
別表5(1)の調整は、子法人株式の会計上の帳簿価額がゼロになったのに対して税務上の帳簿価額は300のままであることを意味します。なお、子法人株式の評価損を計上した時点において、翌期以降の損金算入は見込まれませんので、税効果会計における将来減算一時差異には該当しないと考えられます。
2. X2期
親法人のX2期の途中で、親法人はその子法人から残余財産の分配を受けないことが確定したものとします。X2期において、子法人株式の(税務上の)帳簿価額300について、親法人において資本金等の額が減少しますが、別表には次のように記載することが考えられます。
別表5(1) 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書
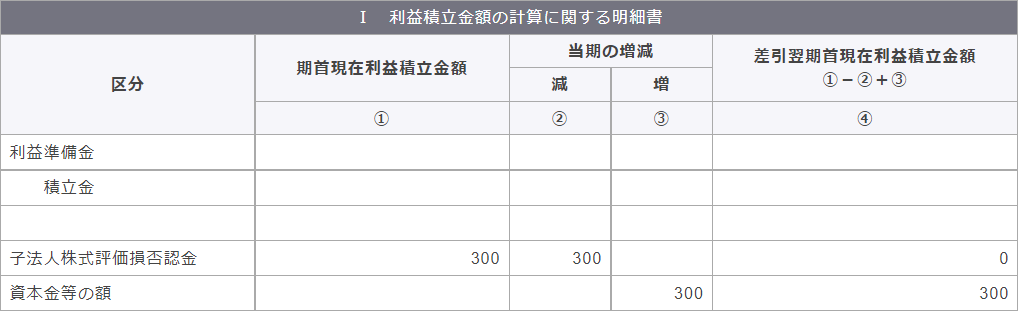
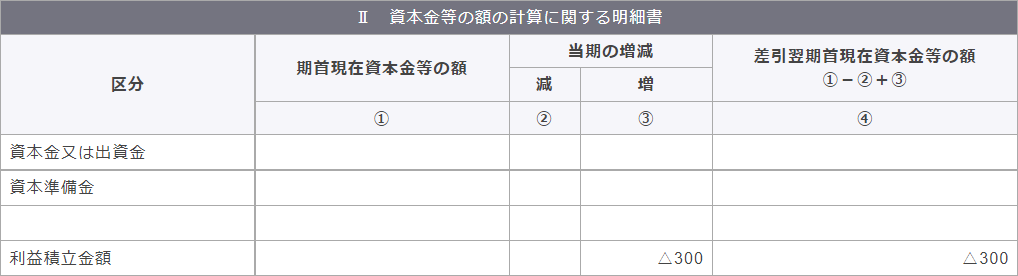
「利益積立金額の計算に関する明細書」と「資本金等の額の計算に関する明細書」との間で、プラス・マイナス300の調整(振替調整)を入れることにより、利益積立金額は変動なし、資本金等の額は300減少という税務上の正しい数字になります。
X2期の別表5(1)において、「利益積立金額の計算に関する明細書」に300、「資本金等の額の計算に関する明細書」にマイナス300の調整が残っていますが、会計と税務のルールの差異に起因して生じた差異であり、解消しない差異であると考えられます。
従って、X1期及びX2期のいずれにおいても、税効果会計の対象にはならないと考えられます。
当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。


