公認会計士 太田 達也
リース取引の区分
リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分されます。企業会計上、このいずれのリース取引に該当するかによって、会計処理の取扱いが異なるため、この区分は重要です。
ファイナンス・リース取引の定義は、①解約不能および②フルペイアウトのいずれも満たすリース取引です(リース適用指針5項)。①解約不能とは、法形式上解約できないリース取引だけでなく、事実上解約不能(例えば、法的形式上は解約可能であっても、解約時に相当の違約金を支払わなければならないなど、事実上解約不能である場合)のリース取引を含みます。②フルペイアウトとは、借手が物件を所有することにより得られるのと同様に、ほとんど全ての経済的利益を享受すること、および借手が物件を使用するに伴って生じるのと同様に、ほとんど全てのコストを負担することを言います。要は、リース資産を使用しているが、自社で所有している場合と同様の効果および費用が生じているものとみなされる場合をフルペイアウトと言います。
具体的な判定要件
企業会計上、リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかについては、上記の要件を満たす必要があり、その経済的実質に基づいて判断すべきですが、次の①現在価値基準または②経済的耐用年数基準のいずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定されます(リース適用指針9項)。
現在価値基準と経済的耐用年数基準
① 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件の借手の見積現金購入価額のおおむね90%以上であること(現在価値基準)
② 解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること(経済的耐用年数基準)
一方、税務上は、中途解約不能かつフルペイアウトのものをリース取引と定義しており、リース取引については売買があったものとして所得計算を行うべきものとされています。また、税務上のフルペイアウトに係る規定ですが、資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額が、その資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、「資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの」に該当すると規定されています(法令131条の2第2項)。
言い換えれば、解約不能のリース期間に係るリース料総額が、その資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超えている場合に、フルペイアウトに該当するものとして判断されます。この内容は、リース適用指針の内容と少し異なります。すなわち、リース適用指針においては、「リース料総額の現在価値」が、見積現金購入価額のおおむね90%以上であるかどうかを判定する内容であるのに対して、税法は現在価値に割り引かない「リース料総額」がその資産の取得のために通常要する価額(借手が購入価額を知り得ないときは、実質的に見積現金購入価額と同義であると考えられます)のおおむね90%相当額を超えているかどうかで判定する内容です。ただし、両者の判定結果が異なるケースは限定的かと思われます。
会計
リース料総額の現在価値 ≧ 見積現金購入価額×90%
税法
リース料総額 > その資産の取得のために通常要する価額×90%
貸手と借手の判定が異なる場合
貸手はリース物件の購入価額を把握していますので、その実際の購入価額に基づいてフルペイアウトかどうかの判定を行います。
一方、借手は貸手の購入価額を知り得ない場合が多く※1 、その場合は見積現金購入価額で判定することになります。貸手における実際の購入価額と見積現金購入価額は一致しないことが多いと考えられるため、貸手と借手のフルペイアウトの判定結果が異なることはあり得ます。例えば、貸手はオペレーティング・リース取引と判定しているにもかかわらず、借手はファイナンス・リース取引と判定するようなケースです。それは、ルール上やむを得ず、判定方法の内容が適切である限り、そのことが問題となることは通常ないと考えられます。
消費税率の認識のずれ
例えば平成25年12月にリース取引を開始したものとします。借手(3月決算会社)はファイナンス・リース取引と判定していたため、最初の課税期間である平成26年3月期にリース期間全体に係る消費税額を5%で一括仕入税額控除したものとします※2。一方、貸手はオペレーティング・リース取引と判定していたため、平成25年12月から平成26年3月までの期間分は5%で請求し、平成26年4月以降から8%の消費税を請求したとします。
借手は、平成26年4月のリース料が8%込みで請求された段階で、貸手がオペレーティング・リース取引と判定していたことに気がつきます。このときの借手の実務対応が問題となります。
借手の実務対応
例えば借手(3月決算会社)が平成26年3月期に5%で一括仕入税額控除をしていたケースで、平成26年4月から平成27年3月まで毎月108,000円(本体100,000円、消費税8,000円)の請求に対して支払を行ったとします。(年間の合計額は1,296,000円(本体1,200,000円、消費税96,000円)です。)
借手の認識と貸手の認識は異なりますが、借手においてはファイナンス・リース取引であることに変わりはなく、賃貸借処理に修正する必要はありません。ただし、消費税の適用税率については、貸手に合わせる必要があります。
そこで、このケースにおける借手の対応は、次のように「仕入対価の返還」を受けたものとして処理すべきものと考えられます。
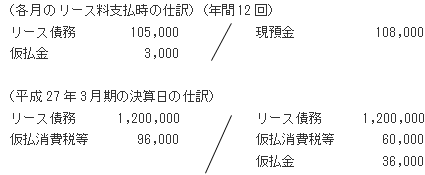
なお、税率差3%相当額のみ仕入税額控除を行う処理で良いと考える向きがあります。しかし、施行日以後、税率引き上げに伴い国分と地方分の割合が異なるため、その処理は正確な仕入税額控除とは言えません。「仕入対価の返還」を受けたものとして処理する必要があると解されている点に留意する必要があります。
※1 貸手がリース会社である場合は、実際の購入価額を把握することは通常不可能です。
※2 ファイナンス・リース取引は、売買があったものとして取り扱うため、最初の課税期間においてリース期間全体に係る消費税額の全額について仕入税額控除を行う必要があります。
当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。


