公認会計士 太田 達也
有価証券の減損処理に係る会計上の取扱い
「金融商品会計に関する実務指針」(以下、実務指針)では、売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行うべきことが示されています。
個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には「著しく下落した」時に該当し、その場合は、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならないとされています。また、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30%以上50%未満であるものについては、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断するものとされています(実務指針91項)。
有価証券の減損処理に係る税務上の取扱い
税務上は、有価証券の事業年度終了の時における価額(時価)がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないときに、上場有価証券等の評価損を計上することができる要件である「有価証券の価額が著しく低下したこと」(法令68条1項2号イ)に該当するものとされています。
以前は、「近い将来その価額の回復が見込まれない」ことの合理的な説明が難しいということで、有税での減損処理を行うケースが少なくなかったようです。しかし、平成21年4月に国税庁から「上場有価証券の評価損に関するQ&A」(以下、Q&A)が公表され、監査法人の監査を受けている法人については、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められるものとされたので、対応がしやすくなったと思われます(Q&AのQ2)。
有税の減損処理に係る税効果の取扱い
有税の減損処理を行った場合、会計上の帳簿価額が税務上の帳簿価額を下回り、その差額が税効果会計における将来減算一時差異に該当します。繰延税金資産の回収可能性があると判断されるときは、繰延税金資産を計上することになります。
有税の減損損失に係る将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する場合の相手勘定は、法人税等調整額です。一方、その他有価証券評価差額金に係る一時差異について繰延税金資産又は繰延税金負債を計上するときは、法人税等調整額を計上せず、評価差額金を直接加減算する処理になります。
有税の減損処理後に時価が回復した場合の税効果の処理
有価証券を減損処理すると、切り下げ後の価額が新たな取得価額となり、翌期以降は期末の時価と新たな取得価額とを比較して、その他有価証券評価差額金を計上します。
有税で減損処理したその他有価証券については、減損処理した分の将来減算一時差異が発生しているわけですが、その後の時価の回復に伴う評価差益については、将来加算一時差異が新たに発生しているわけではなく、将来減算一時差異の減少として認識する必要がある点に留意する必要があります。従って、将来減算一時差異の減少に伴う繰延税金資産の一部取崩の処理が必要となります。
例えば、取得価額100のその他有価証券を30まで減損したものとします。税務上損金不算入扱いとした場合は、将来減算一時差異が70生じていることになります。その後その他有価証券の時価が55まで回復したものとします。その他有価証券評価差額金が25発生したわけですが、この25は新たな将来加算一時差異ではありません。この時点で、将来減算一時差異が、税務上の帳簿価額100と会計上の帳簿価額55との差額である45生じていると見ることになります。次の設例をご参考としていただければと思います。
設例 その他有価証券の減損とその後の時価回復に係る税効果
前提条件
X1年3月期に、その他有価証券の取得価額1,000を時価350まで有税で減損しました。X2年3月期の時価は650まで回復しました。X3年3月期の時価はさらに1,100まで回復しました。法定実効税率を40%とします。なお、繰延税金資産の回収可能性はあるものとします。
解答
1. X1年3月期
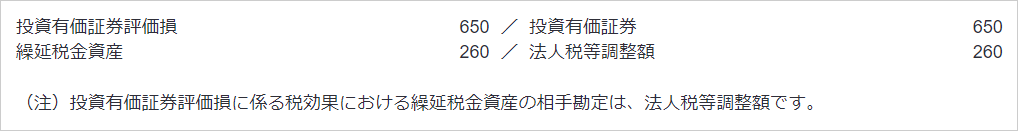
2. X2年3月期
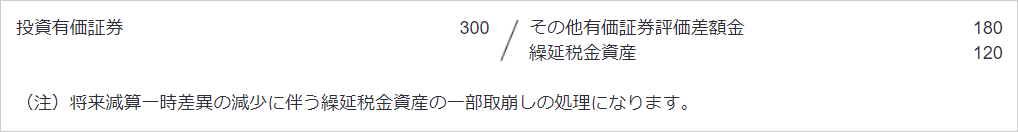
3. X3年3月期
期首(洗替)
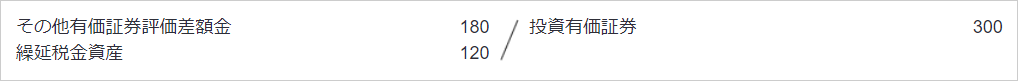
期末
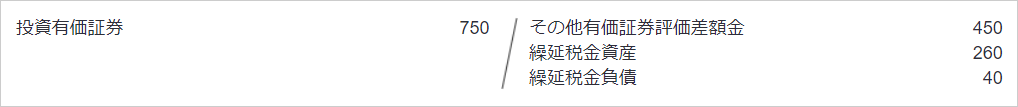
なお、無税で減損処理した場合には、一時差異が発生せず、上記のような処理は必要ありません。
当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。


