公認会計士 太田 達也
税率の変更と繰延税金資産・繰延税金負債の修正
平成23年12月2日付で公布された改正税法により、税率の変更が行われ、それが公布日以後の決算期における税効果会計の処理に影響することは、平成23年度税制改正の会計処理への影響と対応策において詳説したとおりです。税効果会計における一時差異の解消時に適用される税率に基づいて、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算しますが、今回は復興特別法人税(付加税)が3年間に限定して課されるため、複数の税率を用いることになる点もすでに説明したとおりです。
また、既存の繰延税金資産及び繰延税金負債についても、一律旧税率で計算されていますが、改正税法の公布日を含む会計期間において、その一時差異の解消時に適用される税率で再計算することになる点も説明しました。
「修正額」の計算方法について
繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額は、後で説明しますが、財務諸表の注記事項とされています。財務諸表の注記事項である以上、監査法人(または公認会計士)の監査対象であり、正しい数値を計算する必要がある点は言うまでもありません。ところが、この計算方法について誤解が多いことも事実です。
日本の税制では、税率が変更される場合は、「×○年○月○日以後に開始する事業年度から適用する。」と規定されるのが通常です。ということは、改正税法の公布日を含む会計期間において繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算するときには、改正後の税率が期首からではなく、翌期以降に適用されるのが通常です。
繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算するときに、改正後の税率が翌期以降に適用される場合は、既存の繰延税金資産及び繰延税金負債の期首残高ではなく、期末残高に対して税率変更があったものと見なして修正することになります。すなわち、既存の繰延税金資産及び繰延税金負債の期末残高について旧税率で計算した額と新税率で計算した額との差額を「修正額」として注記することになります。一方、改正後の税率が期首から適用される場合は、既存の繰延税金資産及び繰延税金負債の期首残高に対して税率変更があったものと見なして修正することになります。日本の税制を考慮すると、既存の繰延税金資産及び繰延税金負債の期末残高に対して修正するのが一般的ということになります。
3月決算会社の場合
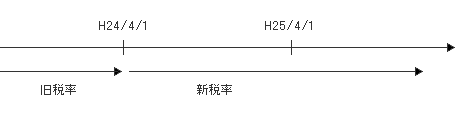
12月決算会社の場合
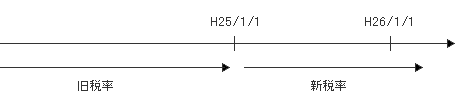
この点について、日本公認会計士協会から公表された「税効果会計に関するQ&Aの改正について」の公開草案段階ではこの点が明確でなかったと思われますが、本年2月14日に公表された確定版において、「(2)税率の変更の注記」が追加され、上記の内容が明確になったものと思われます。
期首残高について修正するか、期末残高について修正するかで、繰延税金資産・繰延税金負債及び法人税等調整額は変わりませんが、注記する「修正額」(=監査対象)が異なるので、十分に留意する必要があります。
具体例
次に、具体例により確認します。
前提条件
税制改正に伴い税率が変更されたため、既存の繰延税金資産の額を修正することになったとします。既存の将来減算一時差異の期首残高が1,000、期末残高が800とします。税率が40.0%から38.0%に変わった場合に、「修正額」はいくらになりますか。
解答
800×(40.0%-38.0%)=16
修正額は、16となります。要するに、既存の(=当期首における)繰延税金資産を構成する一時差異のうち当期中に解消したものは、当期に旧税率で課税され、新税率に修正する必要性がありませんから、当期中に解消しなかった残りの一時差異について修正すればよいということになります。
注記対象となる財務諸表の範囲
税率変更に伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の修正をしたときは、その旨と修正額を注記するというルールは、「税効果会計に係る会計基準」にも定められていますし(税効果会計に係る会計基準第四)、連結財務諸表規則や財務諸表等規則にも定められています(連結財務諸表規則15条の5第1項3号、財務諸表等規則8条の12第1項3号)。
会社法の計算書類については、直接の規定がないため、注記すべきなのかどうかが問題となります。この点については、会社計算規則116条に規定されている「その他の注記」(=追加情報)に該当すると判断されるのであれば、注記すべきものと考えられます。
今回の繰延税金資産・繰延税金負債の修正は、新聞報道でも取り上げられていますが、相当の影響が生じる企業も少なくありません。その点、一定の検討が必要かと思われます。
税率への影響
税制改正による税率変更は、当期の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に乖離(かいり)を生じさせることになります。当該差異が重要である場合には、税率の差異の注記において、主要な項目として掲記されることになります(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の設例7)。
重要な差異であるかどうかの重要性の判断については、連結財務諸表規則及び財務諸表等規則のいずれにも、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の5%以下である場合には、注記を省略することができる旨の規定が置かれている点にも留意してください。
以下、注記例を示します(日本公認会計士協会・会計制度委員会報告「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の設例7より引用)。
(法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳の注記例)
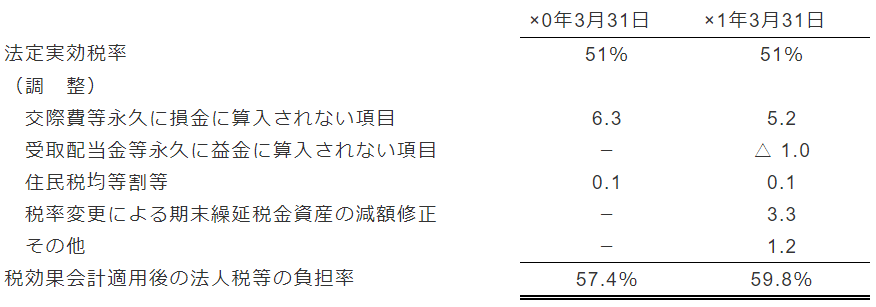
(注) 税率は×1年1月1日の公布により、×1年4月1日以後開始する事業年度から51%に代えて46%を適用する。
当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。


